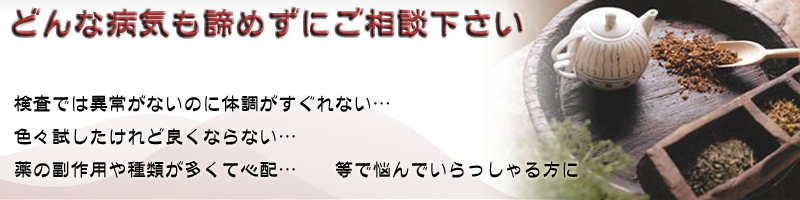
漢方相談無料メールと問診票・どんな病気も諦めずご相談下さい!漢方薬専門店
佐々木漢方薬店ホームページ
山口県岩国市元町2丁目1番18号 佐々木ビル1階 TEL・FAX(0827)23-0873
山口県岩国市元町2丁目1番18号 佐々木ビル1階 TEL・FAX(0827)23-0873
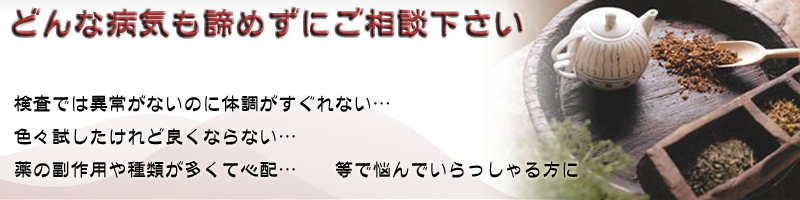
男性性器機能障害・女性性器機能障害・早漏・夜間遺精・夢精・不感症
ED(Executive Director・インポテンツ・勃起不全・性交不能症・
陰痿(陰萎)・陽痿(陽萎))
ED(Executive Director・インポテンツ・勃起不全・性交不能症・
陰痿(陰萎)・陽痿(陽萎))
男性性機能障害
●インポテンツは性的 欲情を感じず陰茎が勃起しない、或いは勃起しても陰茎が硬くならない事をいい、 陰痿・性交不能症・
ED(Executive Director)・勃起不全とも言います。
●早漏は射精までの時間が短く、女性が性的にオーガズムに達する前に男性が我慢する事が出来ず射精してしまうことです。
●遺精とは、体操や運動などにより興奮しすぎた為、又は軽い刺激だけでも勃起して射精したり、
或いは快感を伴わずに精液をもらしたりする事を言います。
●早漏とは眠っている間に性的な夢を見て射精する事を言います。
●夢精とは性的な夢を見て眠っている間に射精する事を言います。
●夜間遺精とは性的な夢を見ていないのに眠っている間に射精する事を言います。
女性性機能障害
●不感症は性的な刺激があるのに性的快感・オーガズム(絶頂感)に達す事が出来ない事をいいます。
| 加味帰脾湯 (かみきひとう) |
● |
| 加味逍遥散 (かみしょうようさん) |
●手や足がだるく、頭痛や頭重或いは顔が急に真っ赤になり或いはめまいがして、
イライラしやすく、時にはウサギの糞状の大便が出る者。 ●胸や脇のあたりが張って苦しく、疲れやすく、のぼせやすく、様々な神経症状を伴う者を目標とする。 *のぼせがひどく、動悸・めまい・不眠症・便秘など有れば、女神散が良い。 |
| 金匱腎気丸 (きんきじんきがん) |
●身体弱く、疲れやすく、下腹がつって痛み、腰痛があり、小便の出が悪い又は
出過ぎる者。 ●脚気により脚や下腹部がしびれて力がはいらない者。 ●のどが大いに渇き水を欲しがり、水を飲めば飲んだだけ小便に出る者。 (夜中にのどが渇いて水を飲む者、或いは少し眠り、夜中に目が覚めて口中が乾く者、八味丸の証多い。) ●小便の出は普通だが、息切れしやすい者。 婦人で息切れがして、夜眠れなく、手や足が火照る者。 ●口渇があり、尿量が多く、咳をする度に小便が洩れる者。 *帯下や排尿痛に八味丸が応ぜず、龍胆潟肝湯で効く事がある。 下腹部が軟らかく膨れている者には八味丸の証がよくある。) *お腹は臍から下辺りが軟弱無力で、ブワブワして手応えのない場合と、腹直筋が下腹部で拘攣して硬く、自ら下腹が張って苦しいと 訴える者とがあります。 *もし口渇、或いは口乾があり、利尿が減少し、頻尿があり、排尿痛がある者で、胃腸障害があれば、猪苓湯・ 五苓散などを考えましょう。 *胃腸障害(悪心・嘔吐・心下痞硬などの胃の症状を伴う下痢)がある者や、胃内停水が著明な者には八味丸を用いてはならない。 本方を服して食欲が減ったり、下痢をしだしたら、八味丸の適応症ではない。 |
| 桂枝加附子湯 (けいしかじゅつぶとう) |
●熱があり、悪寒が多く、汗がしきりに出て止まず小便の出が悪く、 手や足が引きつって伸びず、屈伸するのが不自由な者。 |
| 桂枝加竜骨牡蛎湯 (けいしかりゅうこつぼれいとう) |
●身体疲れやすく、動悸やめまいがして、頭が重く或いは頭がボーッとし或いは
フラフラし、驚きやすく、汗をかきやすい者。 ●身体弱く、神経過敏でちょっとした事で興奮し、のぼせがあり、頭にフケがよく出て、抜け毛が多い者。 ●物忘れが激しく、或いは精神状態が異常で些細なことでもイライラしたり急に怒りだしたり、或いは眠ることが出来きない者で、 腹中が引きつり、動悸が高ぶる者。 ●気が落ち込んでいる者で、呼吸が早くなり、胸や腹で動悸する者。 *この処方を用いて効のない者は上盛下虚に属する。清心蓮子飲がよい。 |
| 柴胡桂枝乾姜湯 (さいこけいしかんきょうとう) |
●胸や脇がはり、内部に締め付けられるようで苦しく、小便が出にくく、
のどが渇いて水を欲しがり、頭だけから汗が出て、寒気がしたり熱がったりし、精神の不安感が有る者。 ●胸や脇のあたりが張って苦しく、のぼせやすく頭から異常に汗が出て肌は乾燥しやすく、大便は軟らかいか下痢をして尿量少なく、 暑がりかと思えば寒がったりという者に用いる。 ●わりと横腹に圧痛や不快感があったり、お腹の裏側(背の中部あたり)の不快感や痛みを訴える者が多い。 |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯 (さいこかりゅうこつぼれいとう) |
●胸の中がいっぱいに詰まった感じがあり、気持ちが落ち着かず、驚きやすく、
動悸がし、小便の出が悪く、うわごとの様な事を言い、体中がだるく重くなり、身体を動かす事が出来ない者。
(大病中や、平素から気鬱になっている者がこの様な病症を現す事が多い) ●大柴胡湯の証で、臍の辺りで動悸が亢進し、物に驚きやすく、興奮しやすいなど神経症状のある者。 (心悸亢進・不眠・めまい等を訴えることが多い) ●桂枝加竜骨牡蛎湯の証で、少し実証で、腹力があり、便秘する。 ●柴薑桂湯(虚証)を用いる様な動悸で、この方を用いても効のない時は、柴胡加竜骨牡蛎湯(実証)を用いる。 (この時、胸満・煩驚がなくとも動悸をおさめてくれる) |
| 滋陰降火湯 (じいんこうかとう) |
● |
| 四逆散 (しぎゃくさん) |
●比較的体力があり、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表す者で、手や足が冷え、
或いは咳が出たり、或いは動悸を感じたり、或いは小便の出が悪く、或いは腹中痛み、或いは下痢してお腹がしぶる者。 ●大柴胡湯証よりも熱状がが少なく、虚証になった者に用いる。胸脇苦満・心下痞硬の程度が軽く、腹直筋は硬く緊張して臍の方にまで 及んでいる者。 |
| 蛇床子散 (じゃしょうしさん) |
● |
| 十全大補湯 (じゅうぜんたいほとう) |
●慢性病・大病後・諸熱性病後・癰疽後・虚弱人・老人・幼児などで、体力・気力とも
に衰えた者を目標とする。大病後、栄養衰え体力回復せず、胃腸に働きも弱り、疲労感や倦怠感を訴え、皮膚光沢を失って枯燥し、貧血の
症状がある者。 ●長い間病気になり弱り果て、口が乾き食事が少なく、咳をし、物音などに驚きやすく動悸がして発熱する者。 *これらの症状がある遺精の者に用いる。 |
| 小柴胡湯 (しょうさいことう) |
●身に熱があり、食欲無く、吐き気がし、始めに悪寒がしてその後熱が急に上がり、
或いは朝は熱無く、午後になって熱が上がり(悪寒なき者あり)、咳をして胸がはり、或いは頭痛して胸中塞がった感じがあり、或いは
胸の脇より背中にかけて張った感じがしたり痛み有る者。 ●発汗剤などで熱がある程度下がったが、奥の熱がとれず、元気なく、只ウツラウツラして横になり、食物を欲しからず、時々のどが渇いて 水分を欲しがり、或いはのど渇かず心中が苦しくてもがき、寝る事も出来ず、大便が出ない者。 ●胸が張り、食欲無く、胸焼けがして、口の中がネバネバして口臭が気になる者。 |
| 清心蓮子飲 (せいしんれんしいん) |
●心中に積を蓄え時に心中がもだえ苦しみ、色々なことを慎重に深く考えすぎ、
独り内にこもり、悲しみ嘆き、小便の色が赤く濁り、或いは尿中に砂の様な混濁があり、夢精し、尿を少し洩らしそれと同時に渋る痛みが
あり、便は血の様な色をする者、或いはお酒を大量に服した為に上盛下虚になり、心臓が上逆し、その為に肺に負担がかかり熱を受け、
その熱が腎に及んで腎気も濁り、口中が苦く、のどが乾燥し、いくら水を飲んでも口渇がとれず、横になってゆっくり眠ることが出来ず、
両手足が疲れてだるい者。 ●日頃から胃腸が弱く血色が悪く痩せ型で体質虚弱な者が、過食や過度の肉体疲労をしたり、強い精神的ストレスなどにより、心・肺に 虚熱の病症が現れ、その熱が腎・膀胱に入り込み、尿の混濁・頻尿・残尿感・遺精・帯下などの症状を現す者を治す。 (胃腸が弱く、冷えたり疲れたりすると膀胱炎になると言う者本方を与えよ。) ●上部の心熱が盛んになって下焦の腎の働きが弱くなり、上下の調和を失い下焦にあたる泌尿器に症状を現す者。 (尿が出そうで出ず気持ち悪い者、或いは尿がかってに洩れる者あり。) ●糖尿病で、神経症を兼ねて体力衰え、食欲少なく、全身倦怠感を訴える者。 *大抵胃腸が弱っていて、地黄剤を服すると食欲が落ちたり、大便がゆるくなる者に用いる。 *この処方は心を清くし、神を養い、精を秘し虚を補い、脾・腎を滋潤し、気・血を調潤する。 *この処方を用いて効のない者は上盛下虚に属さない。桂枝加竜骨牡蛎湯がよい。 *もしもこの処方を用いて心火がひどくなり、性的な夢を見て精液を自然に洩らす者は竜胆潟肝湯がよい。 |
| 大柴胡湯 (だいさいことう) |
●小柴胡湯よりも胸脇苦満の程度が強く、腹力が有り、更に吐き気多く、
胃の辺りが締め付けられる感じが有り、口渇を訴え、舌は乾燥し黄苔又は黄褐色で、脈は沈・実で、熱があまりない者。 ●身体の奥に熱があり、時々嘔吐し、或いは物を食べる時に吐き、或いは食事をすると汗が出て、或いは前文の症状が出ずに苦しがり みぞおちの辺りが痛く、便秘をしている者。 *小柴胡湯の証で、便秘すると頭重などが起こると言う者に、この処方が合うことが多い。 *小柴胡湯を用いても、嘔吐止まず、便秘し、口渇があり、舌が乾いて、褐色の苔が付いている者には大柴胡湯を用いる。 *大柴胡湯を用いる様な者で、臍の辺りで動悸が亢進して、神経症状の強い者には、柴胡加竜骨牡蛎湯を用いる。 *大柴胡湯を用いる様な者で、物音に敏感で動悸がしたり、或いは興奮したりする病状が有り、安眠できない者には、柴胡加竜骨牡蛎湯を 用いる。 *もしも大柴胡湯を服し、腹満して下痢し、気持ちが悪くなる者は、この処方の適用症ではない。 *小柴胡湯・大柴胡湯・柴胡加竜骨牡蛎湯・柴胡桂枝乾姜湯などの柴胡剤は、その病気が何であろうと腹証により用いる。 *胸元が張り、ベルトなどすると苦しいと言う者、目の付け処なり。 |
| 当帰建中湯 (とうきけんちゅうとう) |
● |
| 当帰芍薬散 (とうきしゃくやくさん) |
●貧血又は低血圧又は体温が低く、冷え症で疲れやすく、小便少なく又は回数多く、
時に下痢をし腹痛甚だしく、めまいやのどが渇いて水を欲しがる者。 ●虚証のオ(ヤマイダレ+於)血(血虚)と水毒による症状の者。 |
| 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 (とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう) |
● |
| 人参養栄湯 (にんじんようえいとう) |
● |
| 補中益気湯 (ほちゅうえっきとう) |
●心身ともに疲労して、或いは朝昼夜の決まった時間に食欲出ずムラがあり飲食する
事が出来ず、それにより体がついていかず疲れて怠く弱っている者。 ●体の奥の方に熱が有って頭痛がしてもがき苦しみ、悪寒して、口渇が有り、頭から汗がボタボタと出やすく或いは寝汗をかき、 息切れする者。 ●顔色赤く悪寒し、時に下痢をし或いは軟便が出て、舌に白い苔が有り口中が白く泡のような唾が出てめばっこくなり、食事には味が 感じられず、熱い飲食を好み、臍の下辺りに動悸を感じがする者。病状の重い者は眠りにつく事も出来ず、眼が充血し、うわごとを言い 理解できない事を話し、手足が重だるく力が入らず、言葉を発しても力なく、眼にも勢いも力も感じられない者。 ●消化作用が弱い者で、それ程胸脇苦満や往来寒熱が激しくなく、脈もお腹も比較的軟弱で、疲労しやすく、食欲あまり無く、 体力・気力とも衰えている者。 *本方の目標として ①手足倦怠 ②語言軽微 ③眼勢無力 ④口中白沫生じる ⑤食味失う ⑥熱湯好む ⑦臍下動悸 ⑧脈散大無力 *身体が疲れると寝汗をかくと言う者には本方が合う。 *食事をすると体がだるく、眠たくなる者、本方を用いる目標の一つである。 |
| 抑肝散 (よくかんさん) |
●日頃から身体が弱く、血色すぐれず、神経質で癇が高ぶり、刺激症状が激しく、よく泣き、よく怒ったりし、原因不明の熱を出し、或いは発熱する度に痙攣を起こす者。 ●感情が高ぶりやすく、怒りっぽくイライラし、手足や腹部の筋肉が突っ張り引きつり、みぞおちが硬い者で、頭痛・めまい・を起こす者。 *腹直筋の緊張がある者が多い。 |
| 抑肝散加陳皮半夏 (よくかんさんかちんぴはんげ) |
●抑肝散の証で、左臍傍から心下部にかけて大きく長い胡瓜の様な形をしたものが触れ動悸が著しく亢進し、腹部は全体に軟らかく陥没し、食欲が無い者。 *腹直筋の緊張がある者が多い。 *陳皮・半夏は共に燥湿化痰の働きが有る。 半夏は胃を調え上逆を降し、陳皮は脾を健にして気を調える。 2味を合わせれば胃気の不和により起こる胃部の膨満感、悪心、嘔吐を去り、肝の熱を冷ます。 |
| 龍胆潟肝湯 (りゅうたんしゃかんとう) |
●比較的体力があり、脈にも力があり、下腹部の筋肉が緊張して充実している者。 ●皮膚が浅黒く、手や足の裏が湿気て潤っている者。 *肝経の実火と湿熱を治す。 *体力が衰えていたり、冷え症や貧血の者には用いない。 |
| etc・・・・・・・ | |
| 明日葉 (あしたば) |
|
| 萎ズイ(草冠+豕+生) (いずい) |
|
| 淫羊カク(草冠+霍) (いんようかく) |
|
| カワラケツメイ | |
| 五加皮 (ごかひ) |
|
| 山茱萸 (さんしゅゆ) |
●お酒に浸けたものを服用すれば老人や病後などの滋養強壮薬になり、強精薬にも
効果があります。 ●山茱萸酒の作り方は、種子を取り除き乾燥させたサンシュユの果肉200gとほぼ同量の氷砂糖をホワイトリカー 1.8㍑ に 浸し、そのまま2~3ヶ月冷暗所に放置した後、布などでこし、盃一杯ずつ服用します。煎じる時は山茱萸 1日量 5~8gと、お水 300ccと共に弱火で半量になるまで煎じ、三回に分けて食前又は食間に服用します。 |
| 山薬 (さんやく) |
|
| 海狗腎 (かいくじん) |
|
| 海馬 (かいま) |
●男性ホルモンのような作用があり強壮作用をもたらすので、ED(勃起不能障害・ インポテンツ)や精力減退、遺精に効果があります。海馬1日量 2~6gを煎じて服用する。丸剤、散剤として服しても可。 |
| 韮子 (きゅうし) |
|
| 蛤カイ(虫+介) (ごうかい) |
●腎の陽気が不足してきれいな血が弱り欠乏し、インポテンツや精力が減退した者。
*最強部位は尾 *酒に浸けて服用すると効果的。 *雄(蛤)雌(カイ(虫+介))一対で蛤カイ(虫+介)となる |
| 女貞 (じょてい) |
|
| 西瓜糖 (すいかとう) |
|
| 石斛 (せっこく) |
|
| 大棗 (たいそう) |
|
| 田七人参 (でんしちにんじん) |
●精力減退には、採取した田七人参の皮をむいて乾燥させて粉末状にしたもを 1回量1g~5g 1日1~3回服用。 |
| 杜仲 (とちゅう) |
●腰や膝や背の痛みを治し、内臓の諸機能を補い、元気を増し、筋骨を堅くし、意志・精神力を強くし、常に服用すると身体の動きを軽くし老しない。 ●精力を使い果たし疲れきった肉体には、杜仲をお酒に漬けて服用すると効果的です。 (杜仲 100g お酒 1リットル) *刻んだ杜仲樹皮を 1日量3~30g 又、杜仲葉は 1日量10~30g を煎じて服用する。 |
| タラ根皮 (たらこんぴ) |
|
| 忍冬 (にんどう) |
|
| 反鼻 (はんび) |
|
| 附子 (ぶし) |
|
| 鼈 (べつ) |
|
| 蓮 (れん) |
|
| 鹿茸 (ろくじょう) |
|
| 和肉ジュ(草冠+従)蓉 (わにくじゅよう) |
|
| etc・・・・・・・ |