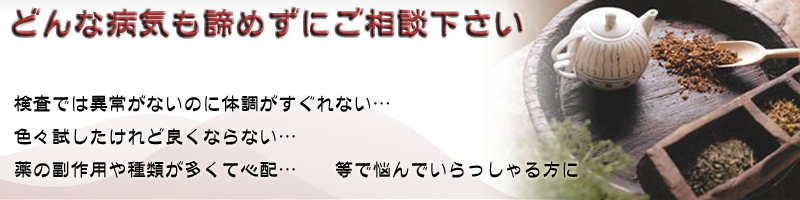
���@���@���@�k�@���@���@���@�[�@���@�Ɓ@��@�f�@�[�@�E�@�ǁ@��@�ȁ@�a�@�C�@���@ ���@�߁@���@���@���@�k�@���@���@���@�I�@������@��@��@�X
���@�X�@�@���@���@��@�X�@�z�@�[�@���@�y�@�[�@�W
�R�@���@���@��@���@�s�@���@���@�Q�@���@�ځ@�P�@�ԁ@�P�@�W�@���@�@���X�r���@�P�K�@�@�@�@ �@�@�@�s�d�k�E�e�`�w�@(�@0�@8�@2�@7�@)�@2�@3�@-�@0�@8�@7�@3
�R�@���@���@��@���@�s�@���@���@�Q�@���@�ځ@�P�@�ԁ@�P�@�W�@���@�@���X�r���@�P�K�@�@�@�@ �@�@�@�s�d�k�E�e�`�w�@(�@0�@8�@2�@7�@)�@2�@3�@-�@0�@8�@7�@3
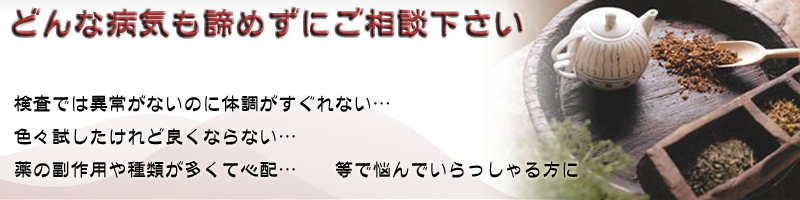
�@�X�V���@�@1990�N(����2)11��20���`2024�N(�ߘa6�N)1��26��
�����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�������܂ł�������͕a���ł͌��߂܂���B
�@�@�̎��A�a�ǂɍ��킹�đI�т܂��B�Q�l�ɂ��ĉ������B
�@���ꏈ���̒��ɓ����l�ȕa���E�nj���܂����A�������������B
�@���܂������������Ă���܂���A�����f�������������܂��B
| ���������� | �������e | �a���E�nj� | ���p�E�ڕW�E�K�� | |
| �� | �s�����E�t ���P�U (�����傤����) |
���P �n���� ���� �ǐm �Ñ� ���� |
�� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
|
| �s�����E�t () |
�� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
|||
| ���h��(�����Ƃ�) �����_�U(�ɂ債��) �ɋL�� |
||||
| �s�����E�t �����U (���イ����) |
�j�} ���Ӎ� ���y 䠍� �k�� �t�Ñ� �ǛI |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�� �� ���쐬���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E |
|
| �� | �s�����E�t �ݕ��� (���ӂ��Ƃ�) |
���A 䉖� �췭� (�����{�|) �l�Q ���Q 䨗� �j�} �� |
�������咰�� ������������ ����ᇐ��咰�� ���݉����� ���ݒ����� �������� ���~���E�� ���~������ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�������Ɍo�߂�����̏�ԂɂȂ����҂̉����ŁA��������łȂ������đ咰�Ⓖ�����ɖ����̉��ǂ�����Ƃ��ɗp��
��B ������ݒ��̋���̐l�Ŋ���Ȃǂɂ���ĉ������N�����₷���A�����Ɍo�߂��đ̗͂�����ɌX���A���ǂ͑�̐�����߂����c�����̂��� �ŏ�������łȂ��咰�Ⓖ���ɋy��ł���ҁB ���ւ͓�֖��͕s�����֖��͐��l�ւ̎�������A���ɏ����S�t�⌌�t�������邱�Ƃ�����B�����̉͂���������Ȃ��B�����������ē� �炩���B |
| �s�����E�t ���(�����{��)�䓒 (�����Ƃ�) |
����� �R���q �剩 |
�����t�����M ������ ���A�ʌ��� ������ �������� ����� ����ڒ� ���r�C ���t���̕��� ���q�{�o�� ����ꕉ� ���H�~�s�U ���@�� ���̂ǂ̋l�܂芴 �������E�}���̉� ���E�C���X���̉� �������̉� ���@���] ���畆�a ���_�X�� ���_�Ώ� ���}���X�� ���s���� ���s���� �������_�o������ ���m�C���[�[ �����̓��� ���o�Z�h�[�a ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����t���A�M���o�āA���ւ̗ʂ��������A�������Ɋ��������o�āA�̂ǂ������Đ�����_���̗L�镨��~������ҁB ���������M���A���X����������A�H�~�������A���ւ̏o�������A�ዅ���������F�����Ă���ҁB ���㕠���������͂�A�S������苹�����͐S�����ɂ����Ă������ꂵ��s�������L��A�����ǂ������l�Ȋ��������A�����E�֔�E���� �E���֕s���E�����E��῁E�����ȂǗL��ҁB �����t�������Ă����ɂ������Ă���Â��M���ݒ��ɗ����A�C���o�����ǂ���Ē��ɂ��܂�A�H��������Ƃ��̔M���S���ɔ���A�߂܂��� ���ċ������������ꂵ�ގҁB �������ʂ��A�֔邪���ŁA��r�I�̗͂�����A�������A�@���]���o��ҁB ���������̂̎������A���e�ꖞ������A��Čӓ�����������B ���H�ŁE���ŁE�M�ł̎O�łɂ�蔭���鉩�t�a�B ���z���a�ɑ����闠�i�ݒ��j�̎��M�������鏈���B �����̗l�ȕa�ǂ��L��҂͕֔邵�Ă��邩�c�֊�������B ���K���������t���L��҂Ƃ͌���Ȃ��B ���֔�Ⴕ���͕֔�C���̎҂ɗp����B �i�K�������A���̌���ł͂Ȃ��B�j ������䓒�̏ɂ��ĉ������͓�ւ̎҂ɂ���ܗ�U��p����B |
|
| �s�����E�t ���(�����{��)�ܗ�U (���ꂢ����) |
�� ���� 䨗� ���Q �j�} ����� |
�����t ��������� ���}��������̉� ���̍d�� ������ �����֕s�� ���q�f ������ ���l�t���[�[ ���t�� ����ڒ� ���s���� �������_�o������ �����˕a ������ ���_�X�� ���_�Ώ� ���}���ݒ��� �����] ���畆�� ���@���] ������i�ނ��݁j �������� ����� ���s���� ���m�C���[�[ ���o�Z�h�[�a �����j�G�[���nj�Q ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����t������A�̂ǂ������Đ����K�u�K�u���݂�����i�������݉߂��A�f���҂���j�A���ցi�Z�����F�`�ԐF�j�̗�
���Ȃ��҂ɗp����B(�̂��ނ��ގ��L��A����̖����ꍇ�A�������o�Ă鎖�L��) ������䓒���y�ǂŁA���Ɏ��M���Ȃ��ꍇ�B ���K���������t���L��҂Ƃ͌���Ȃ��B �������͊̑��̋@�\��ɂ��A�A���𑣂��B �������Ⴕ���͓�ւ̎҂ɗp����B ��䟒ܗ�U�̏ɂ��āA�֔閔�͕֔�C���̎҂ɂ�����䓒��p����B |
|
| �� | �s�����E�t �G�~�� (��������) |
�G�~ �אh ���I ���A ���A ���q �잣 �j�} �l�Q ���� |
���H���� ���\��w��峕a ���m�C���[�[ ���ݒ�� ���s���� ���ݎ_�ߑ��� �����l�� �������� ����M����� ��etc�E�E�E�E�E�E |
���葫���₦�A�g�̂ɕ���ݏ��Ȃ��A���X�f���C���Â��A�����ウ�ė����������A���ɂ͖ウ���R�Ǝ��܂�C�����鎖 �������Ă��A�H����H����ƕ��⋹�����ウ��ҁB���H���ł̎��A���̗l�ȏǏ悭����܂��B������������A�ݒ��̒��q�������Ȃ�A�����ɕ��p�𒆎~����B |
| �s�����E�t ���o�� (�����Ƃ�) |
���� ���A �싇 䉖� �l�Q �j�} ���P �Ñ� ���I ����~ ���O�� ����� |
���s������o���@���n�� �����o�s���@�������o ���s����o���@���s�D�� ���I(�ϲ��ځ{��)���� �������@ ������ �������ǁ@����� �����o���̉��� �������@�\�s�S �����Ɂ@���֔�� �������̔��M �����Ɂ@���s���� ���_�o�ǁ@���m�C���[�[ ���f���C�@���P�u ���q�{����ǁ@���@�� ����ጁi�����₯�j �������_�o������ ���X�N����Q �����̓��ǁ@���ƕw���] ���菶�p���ǁ@����� ����{�����^�� ����̕��̉ΏƂ� ���O������̊��� ���������̊��� ����M�����@���₦�� ���s�D�ǁ@���q�{�o�� ���q�{����s�S ���q�{���� ����������� ���X�N���̎q�{�o�� ���q�{���@�������� ���@�E�����@�����Y�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���w�l�ʼn����������Ă�A��⑫���ΏƂ�A�����������ĐO���K�T�K�T�ɂȂ���ҁB�����͂��̂悤�ȏǏ�
���艺�����������~�܂Ȃ��ҁB�����͌��o�s������������A���������肷��ҁB�����͌��o�̗ʂ������ҁB�����͗₦�ǂׁ̈A�s�D�ǂ�
�Ȃ��Ă���ҁB�����͗₦���Ђǂ����ɂ��A���o�s���̎ҁB�����͏㔼�g���ΏƂ�A�����g�͗₦��ҁB�����ɉ̖����ҁB �������������ɉ��L��A�C�����悭��������Ȃ��҂ɂ͌j��ۂ��ǂ��B������X�ɏd���҂͓��j���C����p����B �����C�����A�n�����῁A��������ݓ����A�q�{�̋@�\�������ė₦��ҁB �����o���~�܂炸�A���X���������R��邪���L�͖����A���͕X���S�����ĂĂ��邩�̔@���₦��ҁB ���I(�ϲ��ځ{��)���������Ɏ~�܂�A����Ȃ��҂́A�O��������������܂��B �i�O����������������A�@�E����������҂�����j ���X�N���Ɏq�{�o�����������~�܂���ҁB�i�����Ɏ�����ҁj |
|
| �s�����E�t ������ (��������) |
���A �n�� 䉖� �췭� (�����{�|) ����� (�����{��) ���A ���� �R���q |
���X�N����Q ���Ĕ����A�t�^ ���������@�����o�� ���q�퐫��� ���w�l�R�� (�q�{�o�� �E�s������o��) �����g���p�`�[�q�{�� (�q�{����E�q�{�̊�) ���щ��@���n�� �����Ɂ@���� ���x�[�`�F�b�g�nj�Q �����o�s���@�����o���� �����̓��ǁ@���_�o�� ���̔�(����) �����G�^�v�� ���������@���̏�Q ���s���ǁ��ᐸ��J ���葫�̉ΏƂ� ���葫�̂��т� ����̂Ђъ��� �����ނ�Ԃ聜���� ���N����ᇁ��t�����j ���@���]�@�����] ���畆�~�y�� ���畆�ߕq�� ���A�g�s�[���畆�� ���A�����M�[���畆�� ���V�l���畆���] �������@������� ���@���@���\�� �����A�@�������� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����]��畆��(�u�]��)������҂ŁA��������������(���������Ԃ����オ��ꍇ���L��)�Ԑg��тсA�ܔM�����L��A
�y�݂��Ђǂ��A�����~���ƕ������ڂꕪ�啨���قƂ�ǖ����B(��ʁE������̔畆��������) ���q�{�o�������͑щ��A�����͒j�q�̉������~�܂��A��F�͉����F�ʼn��������i�ዅ�͉��F���Ȃ��j�A�����Ђǂ��ɂ݁A���r����������� �ҁB ���̂��߂����Ă���Ét���͂�A�畆���������A������������Ƃ��Č��M����ҁB �����̏����́A�̂����߁A�C��₢�A����{���A�𐴂܂��A�̓��̉ߏ�ȔM����菜���B |
|
| �� | �s�����E�t �z�X���Q�� (�����҂�����Ƃ�) |
���� �p ���I �垥 �Ñ� ���Q |
���A�g�s�[���畆�� ���߃��E�}�` �������� ������� ���}�������� ���畆�a ���t���N�e�����p������ �������Ö��g���� �i�o���b�N�X�a�j ���|���[�v ���P���C�h ����A�� ���o�Z�h�[�a ���ό`���G�߉� ������ ��������� �����^�� ����� ������ ����ᝋ� ������ �����ނ� ���畆�a���t�� ���m� ���牺�^� ���؉� ���l�t���[�[ ������ ���r�C ���}���t�� �������t�� ����� �����] ������ ���G�ߒ� ������ ���s���� ���p���� ���Γ��� ���ܔX�� �����E�}�`�������a ���g���R�[�} ���g���z�[�� ���Γ��� �������� �����֕s�� �����t ���g���� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���S�g�ɐ������A���t���o�Ĕ畆�̐F���F���A���ւ��o�ɂ����ҁB �����ւ��悭�o�邪�A�̂ǂ������Đ���~������A�������ނ��߂ɐ��C���Ƃ�Ȃ��ҁB ���O�W���O�W���Ƃ����畆��������A�����R�����ė����K�N�K�N�Ƃ��ė͂�����Ȃ��ҁB ���̓��ɐ��������܂�畆�a�ŕ��啨�������A�̂ǂ���������~������A���ւ̉��������o�ɂ��������肷��҂⊾���o�ď��ւ� �o�ɂ����ҁB ���̓��̐����\�ɂ����ꕂ��݁A�����o�āA���ւ��o�ɂ�����ڕW�Ƃ���B ����a�ł͖ڂ��[�����A�܂����ӂ�₷���A���̎��肪ࣂ��ҁB �i���܂��Ђǂ��Ȃ鎞�́A�Ă����~�̕��ŁA���ׂ��Ђ�����A�₽�����ɓ��������肵�Ă������Ȃ�A�ƌ����l�������B�j ���̗͂�����A���₨���ɂ��͂�����A�M�������Ă���߉��ɗp����B ������̏�Ԃ▬�̌`�͕������̗l�ŁA�b�P�������A�ċz���}�ɔ��藈��ҁB ���n���������A�H�~�s�U�∫�S�ȂLjݒ���Q�̖����ꍇ�ŁA���ɗ͂��L��A����E�A���������A�������ꂵ�ގҁB �����E�}�`�������a�̏����ŁA�̗͂�����҂ɗp���Č�����B�����������҂ɂ͎Čӌj�}�����l����B ���ό`���̕G�߉��ɉz�X���Q���Ɩh�߉��˓�����������ꍇ����B ��������G��ƔM��������B�����̏`�͈��L����肪�����B ���Γ���ŁA�p���̍����E�[���E���ɁE�ڂ̒ɂ݂�����ҁB ��r�I�y���ꍇ�ɗp���邱�Ƃ������B ������ ����ւ͑�̂����ƕς��Ȃ��҂������B �����������Ă��Ă��C�ɂȂ炸�A�X�b�L�����ċC�������悢�Ƃ������́A�ݒ���Q�̉����ł͂Ȃ��̂ŁA�{����p���ėǂ��� �@���ɂ╠��������A���������������Ƃ������ɂ͖{���͗p���Ȃ��B �������܂�D�w�̕���ɗp����ƁA���Y���邨���ꂪ����̂Œ��ӂ���B ������̕���ɗp����B����ɂ͗p���Ȃ��B ����ҁE����ҁE����������҂ɂ͒��ӂ��K�v�B ���������Aႂ������A�S�{�S�{�Ɖ������ĂĊP���������҂́A���������p��p����B ���̗͖����A�ؓ�����炩���ė͖����A�u���u���Ƃ��Ē��܂�̖����҂ɂ́A�h�߉��˓����ǂ��B ���ɕ��̔���̎������łȂ��A���킱��p���Ă���ƁA�����\�h������ʂ����邪�A�H�~�s�U���J���ӊ��Ȃǂ̏Ǐ� �o�邱�Ƃ�����̂ŁA���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �������ɋL�ڂ��Ă���w���x�Ƃ́A�@���E�܁E�����̏`(�̉t)�Ƃ��u�������čl������B |
| �s�����E�����v���t ���ˌj�}�ܕ��� (�����������������Ƃ�) |
����3g �j�}3g ��Z3g ���G6g �垥4g |
�����g�s�� ���m�o��� �����] ���A�g�s�[���畆�� �����т� ����� ������ �����M ������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���F���Ŕ畆���_�炩���A�����ׂ��҂��A�}�ɑ傢�Ɋ��������A�g�̂�Ⴢ�ē����Ȃ��Ȃ�A
�����a�̗l�Ȕ��g���s���ɂȂ����ҁB ���͐�����萏�Ƃ����ŁA�ڒ����������فB ����Ⴢ̕a�ŁA�g�̂������a�̗l�Ɏ��R�ɂȂ�Ȃ��ҁB �� �� |
|
| �s�����E�����v���t ���ˌ����� (���������イ�Ƃ�) |
����1.5g �j�}3g ��Z6g �Ñ�3g ���G3g �垥4g �P��26g |
�����g�s�� ���m�o��� �����] ���A�g�s�[���畆�� �����т� ����� ������ �����M ������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���g�̏d���C�͏��Ȃ��A���o���o�Ղ��A���͕��ɗL��A���͉����L��A���͕֔�L��A
���͐O�������������ɂ���ҁA���͋r�キ�G���K�N�K�N����ҁB �� �� �� |
|
| �� | �s�����E�t �����(�����{��)�� (��������Ƃ�) �V�������(�����{��)�� (�Ă����������Ƃ�) |
����� �Ñ� 䉖� �垥 |
������ �����a �����a ���H���� ���}������ ������ ���ݒ��^���` (��ٽ�������a) ���咰�� �������s�Ǐ� ���}�������� ���q�{�t���퉊 ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����M���ĉ������A���ɂ���ҁB�����͓��ɁA�����͊��C�A�����͂̂ǂ������ҁB�����͂��������������Ԃ�A������
�������ҁB�����͔����ĊO�ɔM���Ȃ��A����ɔM���L�艺�����A�̂ǂ������ҁB �����ɔS�t�ւ����ւ��o�āA�p�ɂɕֈӂ��Â����r�ւ͏��Ȃ��A�`�̂����肪�}�����̒ɂ݂ŋꂵ�ގҁB ���������ĐS���������A����������������l�ɂ���̂ŕ������}�Ɉ�����A���M�E���ɁE�q�f�E���q�E����������ҁB�D��ցE �S�t�ւ̂��Ƃ������A�`���̕��ɂ��B ���הM�����z�̈ʂɂ���A���ɔ��艺�����A�����̕a�������z�ɂ��y�сA���z�Ə��z�̍��a�ɂ�鉺���E���ɂɗǂ��B |
| �s�����E�t ���y�� (�����ǂƂ�) |
���y �n�� ���Q ���P �����(�����{��) �t�� �{���q |
���� ���]���� ���]�o�� �����A ������ ���ƌ� ���f�� �����o�� �����o�� �����o�� ���������� ��������� �������� �������a �������� ���n�� ���^�� �������_�o�s���� ���m�C���[�[ ���^���_�o�� �����Y�� ���s���� ���q�{�o�� �� �� �� �� �� ��eyc�E�E�E�E�E�E�E |
���̗́A�h�{�A���ɐ����A�n�����āA�畆�͊������A�C�̏�t�A�S�ρA�菶�ϔM�A�g�M�����A���ɁA���֕s���A�����A
�����͔���̂���ҁB �������͓��ŁA�S��Ⴢ��A�����̓����A�`�����ɗ͂Ȃ��A���͔��גx�A�����͋فB ��������ᇁA�������A�����A�����a�ȂǂŁA�^���~�܂��A���ɁA���֕s���A�n���̎ҁB �����o���ŁA��ւ���ɏo�āA���̌�ɏo������ҁB �������ŁA�A�Ɨz�݂͌��ɓ������炢�ł��邪�A�����͓�㖳�͂ŁA�S���y�ѕ����哮���͋������A�S���ɂ�����c���������邪�A �`���͊��o�������͂����炸�A�O�\�ɂ͔ϔM�A�����A�����͔ϔM�ƈ����Ƃ����݂ɂ��āA�l���Ƃ�킯�菶�A���G�ɂ͔ϔM�A�Η�A �����͔ϔM�ƙΗ�Ƃ���サ�A�A�ʌ������ĉ������₷���A�w�Ǐ�ɏ���̏o��������̂ŁA�T�ˏ��a�̌o�ߒ��A�����͏o�����v�̌�A���̏�v�����̂Ȃ�A��ʂɕn������̌�A�����܂��V�ɏ����đ����͒���Ȃ�҂Ƃ� �� �����y�����𐮂��A�����~�߁A��������A��������A�P�t�A�ݔ��A�f���A�ƌ��A���R�A�A���A��Ȃǂ������B���ʁE���f�E�~���܁B ���P�E�n���E�Ñ����~���Ƌ��ɑ��� ���Q�E���q���݂̋C��₤�B �����(�����{��)���n���Ƌ��Ɍ��M���܂��B �������� http://www10.plala.or.jp/t-hirano/hubowomitoru 00.htm |
|
| �s�����E�t ���s���s�U (�����ӂ邬�傤����) |
���s���s �����(�����{�H�{�)�חt �K���썪���� �Ñ� �잣 ����� (�����{��) ���G 䉖� ���p |
���菝 ���h���� ����p�� ���~����p ���Y�㏝ �����̓����� ���@�� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���n���Ȃǂɂ�菝����ꂽ����A�|�̎h���A���Ȃǂɂ�菝����ꂽ���A
�ΔM���萶�����O���E�n���E�畆�a�������B ���o�����~�߂Ēɂ݂����������A�h���o�����A��დ����������A�����ɕ��p����ΐg���y�����ĘV����}����B ���傫�ȏ��ɂ͂P��Q�����A�����ȏ��ł���Ώ����ɎU�z���邾���ł��ǂ��B �� |
|
| �s�����E�t ���A���P�� (��������傤�Ƃ�) |
���A �����(�����{��) 䉖� ���P ���� |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��eyc�E�E�E�E�E�E�E |
�� ���E�E�E�E�E�E�E�쐬���E�E�E�E�E�E�E |
|
| �s�����E�t ���A��œ� (������ǂ��Ƃ�) |
���s���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��eyc�E�E�E�E�E�E�E |
���x�X�悭���A�S���ɔ��藈�銴���̂��̂�����ҁB �����A��œ����A�������͋����\���\�����āA�������ĊႪ�Ⴆ�S�R����Ȃ��҂́A�ǂ����ɗ₦������҂������B�l�Q���Ȃlj��߂� �������l���Ă݂Ă��������B |
||
| �s�����E�t ���A�� (�������Ƃ�) |
���A �Ñ� ���I �l�Q �j�} �垥 ���� |
���H���� ���}���݉� ���}������ ������ ���}�������� ������� �������� �������� ������ ���_�o�� �����L �����p�� ������ ���� ���M���a ���_�Ώ� ���{���� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���g�M���蕠���ɂ����J���J���ēf�������ҁB���͚q�f����ҁB���͉������A���͉����������ɐg�̊�ʂȂǍg��
�Ȃ�ΏƂ�ҁB���͕��ׂȂǂŔ��M�E���C�E�q�f�E���ɁE�����ウ�A���͋C�����������Ȃ��ҁB �������ɔM�������āA�ݒ��Ɋ�������A���ɂƚq�f����ҁB���͕��ɂ������������ҁB |
|
| �� | �s�����E�t ��(�����{�J�{�)�����C�U (�����������傤������) |
���Q ���� 䨗� ���p �� �垥 �j�[ ��(�����{ �J�{�)�� ���V (�����{�~) �Ñ� ���I �啠�� ���h�t |
������ ���}���M�a ���}���ݒ��� ���ċG�ݒ��J�^�� ���ĕ��� �����˕a ���Y�O�Y��̐_�o������ �������s�� ���������� ���Ẳ����� �����M ������ ������ ���q�f �������� ������ �����S �������c���� �����ꂵ�� ���g�̌��ӊ� ���H�~�s�U �����o��Q ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���ĂɃN�[���[���@�̕��ɂ����肷���A���L�̕a�ǂ�����ҁB ���^�Ăɗ₽������Ȃܕ������H���߂��A���L�̏Ǐ���ҁB���A���������������������Ă���B |
| �s�����E�t �������A�����(�����{��)�� (���������������Ƃ�) �������(�����{��)�A�� (����������Ƃ�) |
���� ���A ����� (�����{��) �� |
���}������ ���ې������� ���ԗ� �����`�t�X �������� ���ܔX�� ���g���R�[�} �������� ������� ���O�� �����] ���������� ���_�o�� ���s���� �������� �������� �������� ������ ������ ���Ώ���̔��M ��������̔��M �����ɂ��a�Lj��� ���s���� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����������Ċ����o�āA��������̂��������́A�̂ǂ��[�C�[�C�Ɖ������Ă���A��w���ɂ����Ă����A����
������҂͐g�̂̉��ɔM���L��B�����ځA�\�ʂɔM���Ȃ������ł��A���̕��ɔM�͕K������B ���g�̂̉��ɔM����ŁA�畆�̕\�ʂɂ��M����������ׂɈ݂̂����肪�����A�������Ă̂ǂ��[�C�[�C�Ɖ������āA�����o�Đg�̂����� �Ă���t�������A������w���ɂ����Ă����A����������̂�ڕW�ɂ���B |
|
| �s�����E�t �����A�B�� (���݂��ЂƂ�) |
���� ���A �R���q �l�Q ���Q 䨗� �_���m ����� �Č� ���u �垥 �Ñ� ���I �؍� |
���n���@�����Y�� �������@���T�a ���ݒ�� ���_�o���S�����i�� ���H�~�s�U ���q�X�e���[ ����@���ጌ�� ���Q�� ���֔�@�����M ���s���ǁ@���v���ߓx �����o�s�� ���_�o���� �����̓��� �����Í�p ���X��t�@ �����o����̐��� �����Ɂ@���ᜂ̒�� �������Ҏ� ���p���`�a�@���߂܂� ����������� �������_�o������ �����_�s�� ������@�������� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
������̎��ŁA���F�����n���̌X��������A�_�o�ǁA���_�s���A�s���ǁA���M��������ҁB ���A�B���̏ɂ��āA�����M���тт��҂ɗp����B �������A�B���́A�A�B���ɎČӂƎR���q���������������B |
|
| �s�����E�t ����疗y�U (���݂��傤�悤����) �O��疗y�U (�����傤�悤����) |
���A 䉖� ���Q 䨗� �Č� �Ñ� ���G ���� ���O�� �R���q |
������(��ᝋ�) ���������� �������d���� �����Փ����� �������̉��@�������� �������^�R�@�����a ���A�����@���N���� ���畆�� ���A�g�s�[���畆�� ���A�����M�[���畆�� ���̍d�Ϗ� ���q�X�e���b�N�nj�Q ���s���ǁ@���s�D�� ���ڂ̏[���@���̂ڂ��� ���D�w�^�얞 (�����g�얞��) �����M�@���@�� �����Ɂ@�����d ���߂܂��@�����o�s�� ���V�~��\�o�J�X�@���֔� ����J���@���l�����ӊ� �������@������ ���X�N����Q �����j�G�[���a ���щ� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
����⑫�����邭�A���ɂ⓪�d�����͊炪�}�ɐ^���ԂɂȂ舽���͂߂܂������āA�C���C�����₷���A���ɂ̓E�T�M��
����̑�ւ��o��ҁB ������e�̂����肪�����ċꂵ���A���₷���A�̂ڂ��₷���A�l�X�Ȑ_�o�Ǐ���҂�ڕW�Ƃ���B ���̂ڂ����Ђǂ��A�����E�߂܂��E�s���ǁE�֔�ȂǗL��A���_�U���ǂ��B |
|
| �Ñ��b�S�� (�������Ⴕ��Ƃ�) |
||||
| �s�����E�����_�t �Ñ��� (�����Ƃ�) |
�� | ������ �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����A�a�ňɂގҁB ���Ñ�����^���Ă��A�̒ɂ݂����P����Ȃ��҂ɂ͋j�[����^����B ���E�E�E�쐬���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E |
|
| �s�����E�t �Ô��垥�� (��������������Ƃ�) |
�Ñ� �垥 ���� |
���J�T�� ���q�X�e���[ �����_����� ����� ������� ���݃A�g�j�[ �����z�� ���s���� ���_�o���� ���m�C���[�[ ���`�b�N�a ���������� �������� �����V�a �����̔�J �����L �������_�o������ ���X�N����Q ���� ���Ђ��� ���ӎ����� �������a ���o ���N�a ���T�a �����_�a ���q�{�z�� ���z�����P�u ���{���ɂ�镠�ɁE�q�f ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���w�l�̎҂ŁA�����ɕs�������L��A�����̎��ł��߂�����������A�H�~�����A�������C���N���炸�A���L����
�ł�҂������B �����L���悭�o�āA���������ς��Ă���ҁB ���x�X�悭���A�����̕ӂ肪�Â�ҁB ���钆�ɓˑR�ڂ��o�߂āA���ꂵ���Ȃ�A���������̂ǂɓ˂��グ�Ă��銴�������A�����������Ă���Ԃɖ閾���߂��ɂȂ�ƁA���̏Ǐ� ���s�^�b�Ǝ��܂�A���L���肷��ҁB ���_�o�̋����̂Ђǂ��҂���Â����A�����͏��z���Ǐ���ɉ�������Ƃ��ɗp����B ���Â�����H�ׂ�Ƃ����̃c�b�p�������Ȃ��Ȃ�ƌ����҂ɂ͂��̏����������B �����͂��Ǝキ�A���̎҂������B |
|
| �s�����E�����_�t �j�[�� (�����傤�Ƃ�) |
�j�[ �� |
������ �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����A�a�ňɂ݁A�Ñ��������Ă�����Ȃ��ҁB �� ���쐬���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E |
|
| �� | ���(����+�|)�A�P䈓� (���イ�����傤�����Ƃ�) |
�췭�(����+�|) �Ñ� 䈗t ���A 䉖� �n�� ���P |
���q�{�o�� �����A �����o�� �����r�₦ ���������� �����o�ߑ� ���Y��̎q�{���k�s�S�ɂ��o�� �����������������a �������� ������ �����d ����� ������ῂ� ���ጌ�� ����̉��� ���葫��Ⴢ� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���w�l�̌��o�s������ɁA��������a�A���Y��̉����̕Ȃ��t���Č��o���̑��ɂ��`���R�`���R�Əo������҂������B ���D�P���̉����y�ѕ��ɂ���҂₻�َ̑��̔����������B ���E�E�E�E�E�E |
| �P䈓�(���傤�����Ƃ�)�� ���(����+�|)�A�P䈓��ɋL�� |
||||
| �P䈎l����(���傤���������Ƃ�)�� ���(����+�|)�A�P䈓��ɋL�� |
||||
| �I�j��(���傤�����Ƃ�)�� �Čӌj�}���I���ɋL�� |
||||
| �s�����E�t �ʛ����U (���傭�ւ��ӂ�����) |
���� ���Q �h�� |
���Q�� ������ �������@�� ���}���@�� ����J�� �����ӊ� ������̎� �������� ���A�����M�[���@�� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����ɒ���ƈ������A�₦�ɂ��@�����o�n�߂�ƁA�������܂��Ċ����o��҂������B ���g�̂����₷���A���������Ƃ����ɕ��ׂ��Ђ��Ă��܂��ҁB ���E�E�E�E�E�E�E�쐬���E�E�E�E�E�E�E |
|
| �����t�C�ہ������ۂɋL�� | ||||
| �� | �s�����E�t ��Q��(������Ƃ�) |
��Q | �������i��ᝋہj ���^���V �������� �����] �������� ���畆���y�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���A���̔��]�A�y�݁A������A�������ꓙ�ɁA�������t���邩���z�܂Ƃ��ēh�z����B |
| �s�����E�����ϐ����t �앗��œ� (���ӂ����ǂ��Ƃ�) |
�h�� ����q �t�H �A�� 㳊� �Ñ� �j�[ �p |
�� �� �� �� �� ���W�t�e���A ���G���� ���G�����͉� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�� �� ���쐬���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E |
|
| �� | �s�����E�t �t�H�A�ɓ� (����������傤�Ƃ�) |
�y���a��t�z �t�H�E�A�� �h���E���A �싇�E䉖� �ČӁE�k�k ����� (�����{��) ���V (�����{�~) �j�[�E�Ñ� �R���q �y��ѓ��z �t�H�E�A�� �h���E���A �싇�E䉖� �ČӁE�k�k ����� (�����{��) ���V (�����{�~) �j�[�E�Ñ� �R���q �n���E���A ���� |
���A�g�s�[���畆�� ���A�����M�[���畆�� ���畆�a�@���@���] �����]�@���E�я� ���Ô��ǁ@������ ���������@���O���� ����{�����^�� ���s���ǁ@������ ���߂܂��@������ ���S�����i�@�������� ���]���� ���}���E���������� ���~�^�ǁ@��������@�� ���G���B�� ���ƌ�(�@��) ���j�L�r(���) ���B�a���̎����P�� ����ŏǑ̎����P�� (�̋@�\�ቺ�i��) ���x�Z���@���x���j ���_�o����(�m�C���[�[) ���S���|���@���H�~�s�U ���l�����ӊ� ����A�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���畆�����a���F�i�Ê��F�j�ŁA��⑫�̗��ɖ��������A���^���₷���A���͋قŁA���͒������S�̂ɋْ����āi�̌o�ƈo�ɑ���
���āA���̍S����F�߂鎖�������j����ҁB ����ɏ�łɔ����������̉��ǂ�ړI�Ƃ���B �����a��t�̌t�H�A�ɓ��ɒn���E���A�E�����������������̂���ѓ��̌t�H�A�ɓ��ł��B |
| �s�����E�t �j�}�����˓� (���������������Ƃ�) |
�������X�g���t���X ���A�g�s�[���畆�� ���畆�a �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc....... |
|||
| �s�����E�t �j�}��䉖� (�����������Ⴍ�₭�Ƃ�) |
�j�} �Ñ� 䉖� �垥 ���I |
������ ���P ���� ���畆�a ������ �������� �����j�������� ���ؓ��� ���߉� ���A�g�s�[�����] ���A�g�s�[���畆�� ������ ���Q�Ⴂ ���A�����M�[���畆�� ������ �������i��ᝋہj ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����ׂȂǂł���������A���ɂ���ҁB���͂�����������ҁB�₦�ׂ̈ɂ���������A���ɂ���ҁB�C�{���Œɂ� �����ҁB����֔邠����܂����p������������A���ɂ���ҁB | |
| �s�����E�����_�t �j�}�����q�� (���������Ԃ��Ƃ�) |
�j�} 䉖� ���I �Ñ� �垥 �{���q |
���_�o�� ���s���� �������� �����g�s�� �����͌��� ��������� ���Y��̒E�� �����z�� �����E�}�` ����� �����тꊴ �������ߑ� ���m�o��Q �����^�� ���畆�a ������ ������ ���₦�� �����M ������ ��etc....... |
���M������A�����������A����������ɏo�Ď~�܂����ւ̏o�������A��⑫���������ĐL�т��A���L����̂��s���R �ȎҁB | |
| �s�����E�����_�t �j�}�� (�������Ƃ�) |
�j�} 䉖� ���I �Ñ� �垥 |
�� �� �� �� ��etc....... |
�����z�����ɒ��Ă���Ɨz�C�������Ă��ĉA�C���キ�Ȃ�B
�z�C�����҂͔M�����R�ɔ����A�C����܂�҂͊����o�Ȃ��Ȃ�B
��̒��ő̂��������߂���l�Ƀ]�N�]�N�Ɗ��C�����A�����ɔ��ł���l�Ƀ]�[�]�[�Ɗ��C�����A
�H�̉��̉������̗l�Ƀ|�b�|�b�ƔM���o�āA�@��A���q����҂͌j�}����^����B ���́A�@���l�܂��ăY�[�Y�[�Ɩ�A�Q�[�Q�[�Ɖ�����̚q���Â��҂͌j�}����^����B �����z�a�ŁA���ɁA���M�A�����o�āA��������҂͌j�}����^����B �����z�a�������ĉ�����������A���z�ɏW�܂��Ă���C����������A�ɓ˂��オ���Ă���҂͌j�}����^����B ���̎��A������Ղ��Ȃ��҂́A�a���\���狎�낤�Ƃ�����͖̂�������j�}����^���Ă͂����Ȃ��B �����z�a���ĎO���o���A���̊Ԃɔ�����������A�f��������A��������A���I���������A����ł��Ȃ������Ȃ��҂́A ����͉�a������j�}����^���Ă͂����Ȃ��B ��a�ŁA�����قŁA���M���Ċ����o�Ȃ��҂ɂ́A�j�}����^���Ă͂����Ȃ��B �j�}���͖{���A�畆�ɍ݂�s���a���������̂ł���B �����ɕ\��Ă��閬�ƏƂ��悭�ώ@���A�ǂ������t��Ƃ����̂���m��A�o�Ă���،�ɍ����Ă���������Ă��B ���������݉߂����ׂɎ����甭�����a�̏ꍇ���j�}����^���Ă͂����Ȃ��B �j�}����ۂނƓf���C���N����B ���q�̕a�ɂȂ����҂͊Â������D�܂Ȃ�����ł���B�Â������ݒ��ɖ�����ƚq����B ����́A�j�}�������ׂɓf���Â����҂́A���̓f������ɕK���^�⌌��f���o�����̂ł���B �����z�a�ɂȂ�A���ߌj�}����ۂ܂����Ƃ���a���y���Ȃ�ǂ��납�����ĕa�l���ꂵ�݂����a�������Ȃ��҂́A �悸���r�ƕ��{���I���h���A�����Čj�}����^����Ύ���B ���j�}�����đ傢�Ɋ����o�āA�����o��Ɠ����ɖ����^��ɂȂ�҂ɂ́A�j�}����^����O�� �O�@�ɏ]���悸���r�ƕ��{���I���h���Ă��B �������j�}�����A�傢�Ɋ����o�Ă���a��ንa�̗l��1����2������N�����҂́A ���R�Ɋ����o��ΕK���悭�Ȃ�B ���j�}������R�����o����A�����M����A�������Ĉ���ɂ悭�Ȃ炸�A���̏㖬���^��ɂȂ�҂́A ���Չ��l�Q����^����B �����M�������������ƌj�}����������֔邷�邩��Ɖ����Ă݂����A�������⍀������ɂ݁A �|�b�|�b�ƔM���o�āA�M�͏o�邪���͏o���A �݂������ď����ɂ݂��o���A���ւ��o�Ȃ��҂́A�j�}������j�}����菜��䨗�Ɣ��Q������������(�j�}�����j��䨗蔒�Q��)��^����B �������a�����ŁA���R�Ɋ����o�āA���ւ̉����A�s�������L��A�������C�����āA�r����������l�܂�҂ɔ����Čj�}����^���A ���̕\���U�߂悤�Ɗ�����������̂͌��ł���B �������������ׂɋt�Ɏ葫���₽���Ȃ�A �������J���J���Ɋ����A���̊����������Ȃ�������ꂵ�݂����A ������ɓf�������ɂȂ�҂ɂ͊Ñ����I����^���A ���ɂ�莸��ꂽ�z�C�������Ă��B ���a���j�}���̌`����Ă��邩��@�ɏ]���j�}����^�������A�a�������Ď葫���₽���Ȃ�A �����������A���r�̕G���牺���Ȃ����ĐL�тȂ��Ȃ�A���킲�Ƃ������o�����B ���̏ꍇ�A�ߑO�뎞�ɂȂ�Ύ葫�����R���܂�A�S�}���Ă��闼�r�������ɐL�т�͂��B ����͐���������Ȃ�A���̕��͕����痈�āA���̑�͋������ׂɏo�����̂�����A���͔畆���������M���N�������A ���͗������������点��B ���a���j�}���̏�\���Ă��邩��j�}�������A�܂����������Ă��邩�畍�q�������Ċ��������������A ���q�͌o�����߂邪�A�z�C���������ׂɎ葫���₦�A�����������Ă������ꂵ�݁A�z���̌o�ɗz�C�����荞�݁A �C�����������B ���������҂ɂ́A�X�ɊÑ����I����ۂ܂���A�钆�ɂȂ��ėz�C���҂��Ă��邩�痼�r�͓��R���܂��Ă���B �z���̌o�́A�������������Ȃ���l�܂��Ă��邩��A�d�˂�䉖�Ñ�����^���Ă��B ����ɂ��r�͐L�т�B���C����p���ď��������Ă��A���̂��킲�Ƃ������̂��~�ށB ��etc....... |
|
| �s�����E�t () |
�� �� �� ��etc....... |
�� | ||
| �s�����E�t �j�}���������a�� (����������イ���ڂꂢ�Ƃ�) |
�j�} 䉖� �垥 ���I �Ñ� ���� ���a |
������ ��� ����������J ���_�o�� ���_�o�ߕq�ǁi�ϋ��j �����I�_�o�ߕq�� �����I�ߘJ�� ���A�s������ �����Y�� ���t�P ���̂ڂ� �������E�� ���A�s�E�A�X�̗₦ ���₦�� �������_�o������ ���_�o���� ���m�C���[�[ ���`�b�N�a ����A�� ���s���� �����Ӕ�J�� ���]�쌌 ���������� �����쐫�p�� ������ ���߂܂� �����d �����` ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���g�̔��₷���A������߂܂������āA�����d�������͓����{�[�b�Ƃ������̓t���t�����A�����₷���A����������
�����ҁB ���g�̎キ�A�_�o�ߕq�ł�����Ƃ������ŋ������A�̂ڂ�������A���Ƀt�P���悭�o�āA�����т������ҁB �����Y�ꂪ�������A�����͐��_��Ԃ��ُ�ō��ׂȂ��Ƃł��C���C��������}�ɓ{�肾������A�����͖��邱�Ƃ��o�����Ȃ��҂ŁA������ ������A���������Ԃ�ҁB ���C����������ł���҂ŁA�ċz�������Ȃ�A���╠�œ�������ҁB �����̏�����p���Č��̂Ȃ��҂͏㐷�����ɑ�����B���S�@�q�����悢�B |
|
| �s�����E�t �j�}����Q���� (���������ꂢ����ԂƂ�) |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc....... |
|||
| �s�����E�t �j�}����Q���� (����������傤����ԂƂ�) |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc....... |
|||
| �s�����E�t �j�}�l�Q�� (�������ɂ�Ƃ�) |
�j�} �l�Q ���Q �� ���I |
������ ���C���t���G���U ���}������ ���}���咰�� ���Γ��� ����K������ ���݉����� ���f���C ���₦�� ������ ���P ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����M���Ĉ���������A�������犾�������A��������҂������B���̗l�ȕa��̎҂͑��݂̂����肪�d���s������ ����A���ɂ�f���C�̂���҂������B�ݒ����₦�Ă��āA�畆�̕\�ʂɂ͔M������ƌ�����B | |
| �s�����E�t �j�}䨗�� (�������Ԃ���傤���� �j��� (�����ꂢ����) �Ð��� (���������Ƃ�) �D���O(��) (���߂�����(����)) |
�j�} 䨗� ���m 䉖� ���O�� �I�� |
�����o����� ���q�{������ ���q�{�؎�@���q�X�e���[ ���s���ǁ@���֔�� �������@�\�s�S �����͎ҁ@�������� ���������ǁ@���Ŗo�� ���ނ��ł��ǁ@���C�{�� �����܁@���Ђ� �������i�����₯�j �������_�o������ ���X�N���nj�Q �����Փ����� �������X��@���~�^�� ���ݒ�ᇁ@�����o�ߑ��� ���щ�(�������) ���s�D�ǁ@�����B�� �������a�@���畆�� �����]�@���@���] ��������@���Ԗ��� ���x�[�`�F�b�g�a ���m�C���[�[�@������ ���T�a�@���� ��������@������ �����Ɂ@���߂܂� ���̂ڂ��@�������� �����o�s�� ���q�{�o�� ���w�l�얞�� ���s������o�� ���ٔՎc���@�����Y�� �����ف@���@�� ������Ɂ@�������� ���₦�ǁ@�����s�̏o�� �����݁@�������� �����o���@���Q�Ⴂ �����j�G�[���a ���Ίۉ��@���p���� ���O���B���� �������t�� �������d���� ���̉��@�����E�}�` �������_�o�� ���b��B�� ���o�Z�h�[�a ���C�ǎx�b�� ����A�ǁ@���Ö�� �������i��ᝋہj ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���̂ڂ�������A���X�@�����͎��s����o������ҁB �����킩��̂ڂ�������A�I(�ϲ��ځ{��)���i�h���h�����Ă������������j�̏̕a�ɗp����B ���������ɓ��������A�w�\�̎������������ƒɂގҁB �����^�C�v�ŐԂ�炪�����A�����̂�����͏[�����A�葫�₦��ҁB �����̏����p��������ƁA�������Ȃ��Ȃ鎖������܂��B���̎��͕⌌��p�̓��A�܂��K�v�ƂȂ�܂��B �����̏������ĕ֔�ɂȂ�̂� |
|
| ���a���� �h�k�O (��������) |
�l�� ���� ���] �l�Q �ԍg�� �����q ���� �Ï� �j�� ���_ ���q �؍� �Ñ� ���G |
��SAD ���Ќ�s����Q ���s���� �����|�� �������_�o������ ������ ������ ����J�� ������̎� ���Z�C ���T�a �����ӊ� ���_�o�ߕq�� ���������݂₷�� ������ �����f�͒ቺ ���߂܂� ����������� ���n�� ���M���� ���M�˕a ���s���� ���Q�������� ���X�g���X�nj�Q ���_�o�� ��������� �����M �����M ���H�~�s�U ���W���͂̒ቺ ���敨���� ���ݒ� �������s�� ������ ������ �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
||
| �s�����E�t �[�B�� (�����ЂƂ�) |
�l�Q ���Q 䨗� �@�� �R�� �� �� �Ñ� ���I �垥 �R���q |
�������ݒ��J�^�� �������j �������� ���݉����� �������s�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�������Ԃ̎҂̐��l�������ǁB�����̏����s�ǏǁB�a��̈ݒ��̋��s�܂Ƃ��Ă� �p������B����̎��̎҂ŁA�n���̌X��������A�������ɖ��͓��ŁA�H�~�s�U�A�����ۂ����������������A ���X���ɂ�q�f�C���̎ҁB | |
| �j�������ہ������ۂɋL�� | ||||
| �j���������� �l�Q���ɋL�� |
||||
| ���B��႓��� �Z�N�q���ɋL�� |
||||
| ���������^�����ɋL�� | ||||
| �� | �s�����E�t ���h�U (����������) |
�� �� ���I �����q ���h�t |
���T�a �����M ������ ������ ���ݒ��^���` ���V�l�̕��nj�Q ������̎��̕��� �����S ���q�f ������ ���H���� ���@���] �����o�~�i�o�j ������ ���k�o�E�� ���X�N����Q ���A�g�s�[���畆�� ���A�����M�[���@�� ���~�^�� ���@�� �������_�o������ ���_�o���� ���_�o���݉� �������E�}���݉� ���ݒ��_�o�� ������ ������ �����d ����� ���q�X�e���[ ��etc�E�E�E�E�E�E |
���̗́E�C�͖����A��R�͖����A�����ɕ��ׂ��Ђ��Ă��܂��ҁB ���ݒ�����ׂ̈ɕ����E���ɁE���S�E�q�f�̂���ҁB ���C�T�E���ɁE������E����E���`�E�S���|�NJ��E�ݒ�����̎ҁB ���{���͋���ނ�H�ׂċN�������@���]�ɗǂ������B�i������j ���y�����ׂŌj�}���⊋���������ɂ������ҁB ���t��̕��ׂŁA����������̕K�v���Ȃ��ҁB ���C�T�̌X��������_�o���̎��ŁA�C���d���A����S�����ɂ�����������ҁB ���_�o���̕��ɂŁA�ČӍ܁E�������ނ̍���Ȃ��ҁB ���C�̉T�ɂ�錎�o�~�̎ҁB ���C�T�ɂ��A���̖����Ȃ��ҁB�i���A��������j ����܁E���̖�E�G�����q�܂Ȃǂ��v�����p����ƁA���ɂ�����ċC�����������Ȃ�ҁB ���������N���������Ȏ��̗\�h�ɂȂ�B �����z�a�B�C�T�\�����B |
| �s�����E�t �ܗ�U (���ꂢ����) |
�� ���� 䨗� ���Q �j�} �d�� |
���ᒁ@���S���a ���@���]�@���畆�a ���̍d�ρ@���s���� �����N ���A�g�s�[���畆�� ���A�����M�[���畆�� ������� ���C���t���G���U ���͂��� �������i��ᝋہj �������� ���m�C���[�[ �����j�G�[���nj�Q ���ԕ��� ���C�ǎx�b�� ��������@������ ���A�������@���q�f �������� ������i�ނ��݁j �����M�@������ �������s�ǁ@���f���C ���s���� ���}�����J�^�� ���t���@���l�t���[�[ ���݊g�� ���݃A�g�j�[ �����A�a ���}���N���� ���A�X����@�������� �������X�g���t���X ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���g�̂��M���ۂ��A�����o�āA�̂ǂ������Đ���~������A���ւ��o�ɂ����ҁB �����ւ̏o�������A�̂ǂ������Đ����K�u�K�u�ƈ��݁A���߂��ǂ������Ȃ�����A���ǂ����肷��ҁB ������g�̂ɒɂ݂�����A�M���o�Ĉ������A�����o�Ă͂̂ǂ������A�������������݁A���߂����ɓf���ҁB |
|
| �� | �s�����E�t �ČӉ��������a�� (����������イ���ڂꂢ�Ƃ�) |
�Č� ���� �垥 ���I �l�Q ���O �j�} 䨗� �剩 ���� ���a (�������) (�����O) |
���_�o���@���_�o�ߕq ���m�C���[�[�@���r�C ���_�o���� ���q�X�e���[ ���X�N����Q ���s���_�o�� ���T�a�@���N�a ���Ώ���̔��M �������_�o������ ���S���_�o�� ���S���ٖ��� �����S�ǁ@���E�я� �����쐫���쐫�p�� ���b��B�@�\���i�� ���s���ǁ@�����e�ꖞ ��������@���l�\�r ���\���@���S�����i ��������� ���㕠���c�� ����Ɂ@���щ� ���H�~�s�U�@���̂ڂ� ��������(���낻����) ���_�o���A�~ �����͌��� ���������� �������d���� ���]�쌌�@����ʖ�� �����g�s��(���g���) �������E�}���t�� ���l�t���[�[ ���A�ŏǁ@���ޏk�t ���������E�}�` ���Ă� ������(������)�@�����d �����o�s�� �����̓��� ���o�Z�h�[�a ���ߌċz�nj�Q �����_�����a �i���������ǁj ���m�o��Q�@�����Ă� ���߂܂��@����������� �������Q�@���s���� ��������e��(�鋃��) ������ǁi�Q�ڂ���j ����A�ǁ@������ ���߃��E�}�` �����˕a�@���̍d�� ���Ó��a�i���яǁj ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����̒��������ς��ɋl�܂�������������A�C�����������������A�����₷���A���������A���ւ̏o�������A���킲��
�̗l�Ȏ��������A�̒������邭�d���Ȃ�A�g�̂��������o���Ȃ��ҁB �i��a����A���f����C�T�ɂȂ��Ă���҂����̗l�ȕa�ǂ� �������������j ����Čӓ��̏ŁA�`�̕ӂ�œ��������i���A���ɋ����₷���A�������₷���Ȃǐ_�o�Ǐ�̂���ҁB�i�S�����i�E�s���E�߂܂�����i�� �邱�Ƃ������j ���j�}���������a���̏ŁA�������ŁA���͂�����A�֔邷��B �����G�j���i���j��p����l�ȓ����ŁA���̕���p���Ă����̂Ȃ����́A�ČӉ��������a���i���j��p����B�i���̎��A�����E�ϋ��� �Ȃ��Ƃ������������߂Ă����j ������ł͉��O���g�킸�A�����(�����{��)���g���B |
| �s�����E�t �Čӌj�}���I�� (���������������傤�Ƃ�) �Čӌj�I�� (�������������傤�Ƃ�) �ČӛI�j�� (���������傤�����Ƃ�) �Čj�I�� (�����������傤�Ƃ�) �ěI�j�� (�������傤�����Ƃ�) �I�j�� (���傤�����Ƃ�) |
�Č� �j�} ����� (�����{��) ���a ���I �Ñ� ���ꍪ |
���ᜁi�邢�ꂫ�j ���ݒ�� ���}���t�� ���l�t���[�[ ���̉� ���C�ǎx�� �������_�o������ ���ݒ��_�o�� �������a ���_�o�s���� �������̒ɂ� ������ ���߉� ���n���� ���X�N����Q ���O�̊��� ���Q�� ������ ���P ���\�� ������ ���m�C���[�[ ���_�o�� �����̓��� ���_�X�� ���ݎ_�ߑ��� ���@���] ���b�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
������e������A�����ɒ��ߕt������悤�ŋꂵ���A���ւ��o�ɂ����A�̂ǂ������Đ���~������A���������犾��
�o�āA���C��������M�������肵�A���_�̕s�������L��ҁB ������e�̂����肪�����ċꂵ���A�̂ڂ��₷��������ُ�Ɋ����o�Ĕ��͊������₷���A��ւ͓�炩�������������ĔA�ʏ��Ȃ��A���� �肩�Ǝv���Ί���������Ƃ����҂ɗp����B���Ɖ����Ɉ��ɂ�s��������������A�����̗����i�w�̒���������j�̕s������ɂ݂�i�� ��҂������B |
|
| �s�����E�t �Čӑa�̓� (������������Ƃ�) |
�Č� 䉖� �k�� �Ñ� �삫�イ(����+�|) �����q �� |
���i�j |
���l�t�U�̏ŁA�X�ɋC�̟T�������A���e�ɁA���e�ɁA���Ɍ������}�A�Ջt�A�c�����̋����� �l�t�U�ɐ삫�イ(�����{�|)�E�����q�E������������� |
|
| ���������ہ������ۂɋL�� | ||||
| �Ð������j�}䨗�ۂɋL�� | ||||
| �s�����E�t �ė蓒 (�����ꂢ�Ƃ�) ���Čӓ����ܗ�U (���傤�������Ƃ����� �@�@�@�@�@�@���ꂢ����) |
�����o�s�� ���s�D�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
|||
| �s�����E�t �_���m�� (�����ɂ�Ƃ�) �_���� (�����Ƃ�) |
�_���m �m�� �췭� (�����{�|) 䨗� �Ñ� |
���s���� �������_�o������ ���s���_�o�� ���������� ���S���_�o�� ���T�a �����Y�� ������ ���S�����i�� ���m�C���[�[ ���S�J �����d ������ �������� �����̔�J ���H�~�s�U ���n���� ������(�Q��) �����(�߂܂�) ������ ���_�o�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���̗͐�����J���₷���A���_�E�_�o���N�^�N�^�ɂȂ�A���鎖���o���Ȃ��ҁA�����͋���̎��⍂��҂ȂǂŁA���
�Ⴊ�Ⴆ�Ė���Ȃ��ҁB ���������狕��Ȏ҂ŁA�}�ɋ����������Ė��鎖���o���Ȃ��҂͖{���̏ł���B�S�z���Ȃǂ��L��A����Ȃ��҂͖{���ł͎����ɂ����B ���Q�߂��č���ƌ����҂Ɍ������L��B �������א��̎ґ����B |
|
| �s�����E�t �O�������(�����{��)�� (�������������Ƃ�) |
����� (�����{��) ��Q ���n�� |
���m�C���[�[ ���s���� �������� �����؏o�� ���f�� ������ ���Ώ� ���w�l���̓� ���Ă̋r�C ���X�N����Q �������i��ᝋہj �����Ă� ���@���] ����ᝁi���ނ��j ����� �������_�o�s����� ���葫�̂قĂ� ���Y��M�a ���x���j ������ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���Y�㕗�ׂ��Ђ��A��⑫���ΏƂ�ҁB ����⑫���ΏƂ�A�̂ǂ���������~������A���͌������������ċꂵ���ҁB ���g�̂̉��ɔM���L��A���ׂ̈ɓ��ɂ����A�����͎�⑫���ΏƂ�ނ��y���ҁB ���q�{�̔M���S�g�ɋy�сA���Ɏ�⑫���M���Ȃ�ꂵ�ݖウ��҂������B ���̗͂��Ƃ���҂ŁA�ĂɂȂ�Ǝ�̕��⑫�̗����Ă���l�ɉΏƂ�ꂵ�݁A���鎖���o���Ȃ��҂������B �i��⑫���ΏƂ�Ƒ������邭�ɂ���ґ����j �����̏����͎葫�̔ϔM����Ƃ��錌�M�A�����������B 1 |
|
| �� | �s�����E�t ���A�~�Γ� (���������Ƃ�) |
���A 䉖� �n�� �� ���Q �m�� ���� �Ñ� �V��~ ����~ |
���P ��� ���ċz���� �����A�a �����M ������ �������a ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���̂ǂɏ����������Aႂ͂قƂ�Ǐo�Ȃ����P���ގҁB �����������ɂ��̉t�i�Ét�j�s���ʼnΏƂ�ҁB ���x�t�A���B |
| �s�����E�t ���_�p (������) |
���A ���� ���X �Ӗ��� �؎� |
��������@����� ���A�g�s�[���畆�� ������ �����Ԃ�@���p��� �������@���^�o�] ���j�L�r �����v ���w���y�X ���킫�� ���~�`�E�я� ���O�̊��� ���������畆�� ���O�� �������₯ ����������@���Ђ� ���Ώ��@���C�{ �������� �������i��ᝋہj �����̖ځ@�������̏� ���������@����� ���������� �����݁@������ �����v��� �������� �����菝�@���菝 ���E�яǁ@�������� ������ ���@���̏� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���畆�������A�r�^��ǂ����A����̔����𑣂��B ����M�A��ŁA�E�ۂ̌��ʂ�����܂��B ���d�x�̉Ώ��ɂ͒����p�⑾���p�̕����ǂ��ł��傤�B ���������łȂ��Ƃ��A������畆�̕a�ɊO�p����ƁA�ƂĂ��ǂ�����������̓�p�ł��B �����_�p����؎�����苎�������������p�ł��B ���_�p�͉؉��F�Ƃ������������p����ɍl�Ă��č��ꂽ�����ł��B |
|
| �s�����E�t �l�t�U (�����Ⴍ����) |
�Č� �k�� 䉖� �Ñ� |
����@�����͌��� �����_���C���|�e���c ���l���t��@���P ���b���@���C�ǎx�� �������@���S�����i �����֕s�� ���}���E�����咰�� �����J�^���@�������� ��������ᇁ@�������� ���ݒɁ@���ݎ_�ߑ��� ���_�o���݉� ���ݒ��_�o�� ���]�����@���]�Ԑ_�o�� ���݁E�\��w����� ���ߕq�������� �������@���֔� ���@�J�^���@���s���� �����Ɂ@������ ���_�Ώǁ@���_�X�� ���t���a�@�����g�s�� ���_�o�ߕq�@���_�o�� ���q�X�e���[�@���T�a �����j�������� �������_�o������ ���X�N���nj�Q ���}���E�����̉� ���_�������� ���_���W�X�L�l�W�[ ���N���_�o�� �����o�s�� �����o����� �����o�O���nj�Q ���H�~�s�U�@�����M �����Ӕ�J�@���x���j ��������@���� ��ᒏǁ@����{�����i�~�^�ǁj ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����A�̕a�ɂȂ����҂ŁA��⑫���₦�A�����͊P���o����A�����͓�������������A�����͏��ւ̏o������������A
�����͕������ɂ݁A�����͉������Ă��������Ԃ�҂ɗp����B ���M������҂����邪�A�����҂�����B���������͉��ɔM���L��B ���A�����������ċꂵ�݁A�݂������ӂ肪�����铙�̏Ǐ�ɂ��p����B ����Čӓ������M���Ȃ��A���ɂȂ����҂ɗp����B���e�ꖞ�E�S���|�d�̒��x���y���A�����͍d���ْ������`�̕��ɂ܂� �y��ł���ҁB �����M���� ���l�t�U�Ǝl�t���͈Ⴄ�����Ȃ̂ŁA�ԈႢ�̖����悤���ӂ��ĉ������B |
|
| �s�����E�t �l�t�� (�����Ⴍ�Ƃ�) |
�� ���I ���q |
���₦�� ���}������ ������̎� ���S�؍[�� ������ ������ ������ ���H���� ���C���t���G���U �������s�Ǐ� ����������� ���������� �������� ���f���C ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�������̉����A��⑫������悤�ɗ₽���A�葫���k���܂�ҁB �����J���J�Ɠf���C������A�葫���₦�A���M���Ċ��C�����A�g�̂����邭�A�������������ǐ��͗~�����Ȃ��ҁB �����M���Ċ������o�ĕ��ɂ��L��A���͉������Ċ��C���Â��A��⑫���ɓx�ɗ₦��ҁB �����܂�p���ĉ��������A�������~�܂Ȃ��ҁB ���������������A�葫���₦�A���C�����Č��C�Ȃ��Ȃ����ҁB �����͐G��Ă��L�邩�ǂ����킩��Ȃ����炢�̎ア���ł��B ���o���������Ď葫���₦�A���ɁA���C�A���M����ҁB ���l�t�U�Ǝl�t���͈Ⴄ�����Ȃ̂ŁA�ԈႢ�̖����悤���ӂ��ĉ������B |
|
| �s�����E�t �l�N�q�� (�����Ƃ�) |
�l�Q ���Q 䨗� �Ñ� |
���݃A�g�j�[ ���������� �����o�� ���n�� ���ݒ����� ���H�~�s�U ���q�f �������� ���l���̖��͏� �������� ���E�� �����g�s�� ����ʐ_�o��� ����A�� ����A�� ���݉����� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���ݒ�����ŕn���X���̎ҁB�ݒ��ɐ�������₷���A�H�~�s�U�E�S�̓I�Ɍ��C�̐����Ă���ҁB ���n���C���Ŋ�F�������A����ɗ͂������A�葫���ӂŁA���ɗ͂��Ȃ��ҁB |
|
| �s�����E�t �l���� (�����Ƃ�) |
���A �췭� (�����{�|) 䉖� �n�n�� |
���n�� ���߂܂� ���₦�� ����������� ������ ���畆���� ���A�g�s�[���畆�� ���A�����M�[���畆�� ���畆�a ������ ���ٓ��s�� ���������� ���h�{�s�� ���s���� ���� ����ጁi�����₯�j �����͌��� �������a ���X�N����Q �������_�o������ �����͏�Q �����o ���H�����o �������o �����o�s�� ���q�{�o�� ���q�{����s�� �����o����� ���o�Y���̏o�� ���s�D�� �������� ���t�܂� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���畆���������₷���A���̐F�����Ɉ����A�Y�㈽���͗��Y��̔�J�E���o�s���E�₦�ǁE���̓��ǂȂǂ̎ҁB ���n���̌X��������A�畆�������A���͒���Ŏキ�A�����͓����`��ɓ���������ҁB ���w�l�a�̌��̓��ǂƌ�����_�o�Ǐ����Â�����B ���ݒ���Q�̖����҂ɗp����B ���O�̐F�������ƂȂ��Ă���ҁA�ڂ̉��܂т̗����������҂͍��x�̕n��������B �����A�͕⌌�A���ÁA�q�{�̋���₤�B �@�n���͐t�������A����₢�A���ÁA�q�{�̋���₢�A�������v���B �@䉖�͕⌌�A�T����a�ʂ��Č��s��ǂ����A�q�{�̋���₤�B �@�싇�͟T����a�ʂ��Č��s��ǂ����A�C�����点��B ���l�����͗{���E�⌌�E��̂̍�p������B�������B ���l�����͌����ɑ����{�I���܂ō�����������ɍL���p�����Ă���B |
|
| �s�����E�t �����p (�������) |
���� ���A �Ӗ� �����X |
�������� ����� ���A�g�s�[���畆�� ������ �����Ԃ� ���p��� ������ ���^�o�] ���j�L�r �����v ���w���y�X ���킫�� ���~�`�E�я� ���O�̊��� ���������畆�� ���O�� �������₯ ���������� ���Ђ� ���Ώ� ���C�{ �������� �������i��ᝋہj �����̖� �������̏� �������� ����� ���������� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���畆�������A�r�^��ǂ����A����̔����𑣂��B ����M�A��ŁA�E�ۂ̌��ʂ�����܂��B ���d�x�̉Ώ��ɂ͒����p�⑾���p�̕����ǂ��ł��傤�B ���������łȂ��Ƃ��A������畆�̕a�ɊO�p����ƁA�ƂĂ��ǂ�����������̓�p�ł��B �������p�ɓ؎����������������_�p�ł��B �����p�͖��̎���ɊO�Ȑ��@�Ƃ��������ɋL�ڂ���Ă��܂��B |
|
| �s�����E�t 䉖�Ñ��� (���Ⴍ�₭�����Ƃ�) |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���P�����鎞�ɑ�ւ��k���ҁB �������̖���ɂ��̏����͗ǂ������܂����A����p���Ă����ʂ��Ȃ����͊Ô��垥����}�̎U���l���܂��傤�B |
||
| �s�����E�t �\�S��ⓒ (���イ�����قƂ�) |
�l�Q ���� ���Q ���A 䨗� 䉖� �j�} �Ñ� �췭� (�����{�|) �n�n�� |
���X�N����Q�@���n�� ���Y��̉�p ����p���p �����ŃJ���G�X ���ҒŃJ���G�X ���Ҋߌ��j�@���� �������a�@������ ���_�o����@��� �����͌��ށ@���q�{�� ���щ��E���I ����A�ǁ@���H�~�s�U ���葫�̗₦(�₦��) ����p��̔r�^�@�����M �����������i�Q���j �����̌��� �������@������ ���߂܂��@���P ���������M�@������� �������Ɂ@�����֒Z�� ����֊����@����� ���E��@���p�A ����J���@���g�̐��� ����ᑁ@���t�f���� �������@������ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�������a�E��a��E���M���a��E��s��E����l�E�V�l�E�c���ȂǂŁA�̗́E�C�͂Ƃ��ɐ������҂�ڕW�Ƃ���B ����a��A�h�{�����̗͉����A�ݒ��ɓ��������A��J���⌑�ӊ���i���A�畆����������Č͑����A�n���̏Ǐ���ҁB ���Y��A���͗��Y��ȂǂŁA�̗́A�C�͂Ƃ��ɐ������҂̑щ��ɗp����B ���C�����ɋ������ҁB �����M�������A�Q���������A�葫�̂����Ă��邭�Ȃ�A�����͓��ɁE�߂܂��E��������ҁB �������ԕa�C�ɂȂ���ʂāA���������H�������Ȃ��A�P�����A�����Ȃǂɋ����₷�����������Ĕ��M����ҁB ���l�N�q�����l�����̔������Ɍj�}�Ɖ��˂������������ł���B ���������B |
|
| �s�����E�t �\���s�œ� (���イ�݂͂��ǂ��Ƃ�) |
�Č� �j�[ �h�� �췭� (�����{�|) ���� 䨗� �Ɗ� �t�H �Ñ� ���G |
�������i��ᝋہj ���t�����P�� ���J���u���P�� �������� ���O���� �������p�B�� �������� ���畆���^�� �����] ���@���] �������X�g���t���X ���A�g�s�[���畆�� ���A�����M�[���畆�� �����B�� �������p�B�� ����{���̒~�^ �����v�i�j�L�r�j ���t�����N���[�W�X �i���ł��j �������^�R ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����^�Ǐ����ŁA���M�A�����A�u�Ɂi�������ɂށj�̂���ҁB �����e�ꖞ�i����e�̂����肪�����ċꂵ���j������A���^�ǂ̎ҁB ���M�̂��鉻�^�ǂŒɂ݂̂���ҁB |
|
| �s�����E�t �������� (���傤���イ�Ƃ�) |
�j�} ���I �垥 䉖� �Ñ� �P�� |
�����̔�J�@������ ���߂܂��@����������� �������@���֔� �����t�@���ؓ��� �����������M�nj�Q ���_�o���S�����i�� ���G���B���� ���x�僊���p�B� �����j�������� ���݃A�g�j�[������ ���ݎ_�ߑ��� ���ݎ_���R�� ���ݒ�ᇁ@���݊� �������s�ǁ@���E�� ���E��@����A�� ���C�ǎx�b���@���� ���A�g�s�[�����] ���鋃���@���r�C ���ጌ���� ���������� �������a�@�����o�� ���t���N�e���������� ���ݒ��_�o�� �������̉� �������݉� ���\��w����� ���ݒ�����̏����̕��� ���p�A�@���t�d���� ���O���B���� ������������ ���m�C���[�[ ��������K������ ���w���j�A �����o�� ���������@���E�я� ����@���ߘJ�� ���ăo�e�@���_�Ώ� ���̍d�ρ@��������� ���������@���S���ٖ��� �������d���ǁ@���x�C�� ���]�����@���ǂ��� �����Ɂ@���V���t ���������������͌��ށ@���݉��� ���_�o���� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���g�̔��₷���A��⑫�̗����ΏƂ����肵�A���ɕ@�����o���A���ɂ��L������A����������A��⑫�����邭��
������ɂ݂��o���肷��ҁB ����F�D�ꂸ�A�g�̂��₹�āA������������A���ɂ��L��A���ւ������ҁB ���₽�����H�����ĕ��ɂƋ��ɉ������Ĕ���҂ɂ́A���̏������ǂ������B�j�}��䉖����̏ł��B �������ŁA�悭���������킵�₷���A���ׂ��Ђ��ƌ����ҁB ������������⒆�v�C�����̊Ö��܂��A����Ђǂ��Ȃ����҂ɂ͕�C���������ǂ��B |
|
| �s�����E�t ���Čӓ� (���傤�������Ƃ�) �O�֓� (����Ƃ�) |
�Č� ���� ���I ����� (�����{��) �垥 �l�Q �Ñ� |
���A�����M�[���畆�� ���A�g�s�[���畆�� ���@���]�@�����M �����M�@������ �����M�@���H�~�s�U �����e�ꖞ�@������ ������@���s���� ���f���C�@���q�f �����ہ@������ ���]�����i�������j ���]�Ԑ_�o�� ���я��v�]�i�w���y�X�j �����t�@���݉� ���ݎ_�ߑ��� ���ݎ_���R�� ���ݒ�ᇁ@���ݒ� �����Ă��@�����l�ˋN�� �������B���@�������ӂ� �����B���@�������� ���w�l�t���퉊 ���Y��M�@�����̓��� ���A���~�y�� �����(�����₯) �������� ���_�o�� ���_�o���s�H�a ���m�C���[�[ �����Ⴍ���� �����j�E�C�{�� ���C���t���G���U �����ׁi���`�j ���}�����A ���`�t�X �������E�}���̉� ���̍d�� ���̑��� ���̋@�\��Q ���_�X�� ���_�Ώ� ���P ��� ���C�ǎx�� ���͂����i���]�j ���x�� ���x�C�� ���^�� ���x���j ����Ȃ߂��� (������̍r��) �������p�B�� ���Ó��a(�~�`�E�я�) �����j�������p�B�� ���G���� �������� ���O���� ���t�� ���t�f���� ���t᱉� ���N���� ���Ίۉ� �����Ίۉ� ������ ������ ���ǂ��� ���ᒁiᒕa�j �����_�����a ���Ђ��� ����蕨���� �������X�g���t���X ���X�N����Q �����͌��� ���畆�a �����^�� ���_�o���� �����W ���֔� ���C�ǎx�b�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���g�ɔM������A�H�~�����A�f���C�����A�n�߂Ɉ��������Ă��̌�M���}�ɏオ��A�����͒��͔M�����A�ߌ�ɂȂ���
�M���オ��i�����Ȃ��҂���j�A�P�����ċ����͂�A�����͓��ɂ��ċ����ǂ���������������A�����͋��̘e���w���ɂ����Ē���������
��������ɂݗL��ҁB �������܂ȂǂŔM��������x�����������A���̔M���Ƃꂸ�A���C�Ȃ��A���E�c���E�c�����ĉ��ɂȂ�A�H����~�����炸�A���X�̂ǂ����� �Đ�����~������A�����͂̂NJ������S�����ꂵ���Ă������A�Q�鎖���o�����A��ւ��o�Ȃ��ҁB ����������A�H�~�����A���Ă������āA���̒����l�o�l�o���Č��L���C�ɂȂ�ҁB �@ |
|
| �s�����E�t ���Čӓ����j�[�p (���傤�������Ƃ��� �@�@�@�����傤��������) |
�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
|||
| �s�����E�t ���Čӓ���䨗艩�A (���傤�������Ƃ��� �@�@�Ԃ���傤�������) |
������ �����M ���P �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
|||
| ���Čӓ����ܗ�U ���ė蓒�ɋL�� |
||||
| �s�����E�t �����U (���傤�ӂ�����) |
���A �n�� �p �h�� ���Q �ؒ� ��� ��Q �t�H �m�� �Ӗ� �Ñ� ����q |
�������i��ᝋہj �����] �����] �����v ���A�g�s�[���畆�� ���@���] ���畆�a ���X�g���t���X ���畆�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���������ʼnāA�����͉��g�����Ɉ�������畆�a�̎ҁB �����ɔM���L��A�̂ǂ���������~������A���啨�������A�o��i�J�T�u�^�j���`�����A�n�����Ԃ݂����сA�ƂĂ��y�݂��Ђǂ��畆�a�� �ҁB �����M���܂��A���������������ł��B�i�����M�悷��a�j ���P���C�h�ɂȂ������̂ɂ́A ****************************************�Â� |
|
| �t�C�ہ������ۂɋL�� | ||||
| �s�����E�t �^���� (����ԂƂ�) ������ (����ԂƂ�) ���z������ (����悤�肷���Ƃ�) |
䨗� 䉖� ���I ���Q ���q |
�����M ������ ���߂܂� ����������� ���g�̐U�� ������ ���A�ʌ��� ���l�����d ������ ���P ������ ���C�ǎx�� ���x�� ���]���� ���S���a ���t���a ���ݒ��a �����J�^�� ���咰�J�^�� �������j ���������� ���ጌ���� ����� ���_�o�� ���ؓ����E�}�` ���畆�a ���₦�� �����j�G�[���nj�Q ���C���t���G���U ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�������Ђǂ��C�������Ȃ�悤�ŁA�����Ă����Ȃ��ҁB �������ɂ݁A�������Đg�̑S�̂��d���ɂ݁A���ւ̏o�������A�ނ��݂�����ҁA�����͎��ɊP���o����A�f���C���Â��ҁA�����͊P������ �x�ɏ��ւ��R���ҁB �����͔����ɐG��čׂ��A��������Ȃ���������A���ɁA���ւ̏o�������A��⑫�ȂǕ����ŏd�����ɂ݁A��������ҁB ���ǂ�����͗͂Ȃ��ア�B |
|
| �s�����E�t �Q�蔒�Q�U (����ꂢ(��傤) �тႭ�������) |
�l�Q ���Q 䨗� �R�� �@�� �j�[ �k�� �Ñ� ָ䏐m ���G�� |
�������s�� �������ݒ��� ���n���� ���l�t���[�[�nj�Q �������݉� ����֖��͉��� ������i�ނ��݁j ���P ��� ������������ ���������y�� �������s�Ǐ� �������j ���݉����� ���щ��i������́j ����J�� ���H�~�s�U ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���ݒ�����ŐH�~�s�U�őS�g���ӂ�����A���l�������i�����������E���ǂ��Ȃ��̂ŏL�������Ȃ��j���₷���ҁB ����a��̔�J���E�H�~�s�U�E�щ��i�F�͔����Ĕ����ʂ������j�E���R�Ȃǂɉ��p�����B ���ꖡ�ŗ�₷��p�̂��銿������āA�����E�H�~�s�U�ɂȂ����҂́A�����ɕ���𒆎~���A�Q�蔒�Q�U��^����Ɨǂ��B ���ݒ�����ŁA���ɔ��M�∫���͖����A�����g�̂����邭�A�H�~�������ҁB�i�����H���Ă��݂⋹�̂����肪������j ���ݒ��������Ȃ��������ꂽ���ɑ�������݂₷���ҁB ���ݒ�����ŁA�P��ႁi�F�͔����Ĕ����A�ʑ��߁j���Ȃ��Ȃ�����Ȃ��ҁB |
|
| �� | ||||
| �� | �s�����E�t �����v�C�� (�������傦�����Ƃ�) (�������傦�����Ƃ�) 1.��w�Z�v�̐����v�C�� 2.���O���٘f�_�̐����v�C 3.�B�ݘ_�̐����v�C�� 4.�����̐����v�C�� |
���P�� �l�Q�E���Q ��E�Ñ� �����E���A ���� ����~ �ܖ��q ���Q�� �l�Q�E���Q ��E�Ñ� �����E���A ���� ����~ �ܖ��q �_���E���b ��E���� ���Q�E���� ���R�� �l�Q�E���Q ��E�Ñ� �����E���A ���� ����~ �ܖ��q �_���E���b ��E���� ���Q�E���� ���I�E�垥 ���S�� �Ν́E�Ñ� �d�āE���A �m��E�@�[ ���m�Q ����~ �W�|�t |
||
| �s�����E�t �����(�u�{�)�ɓ� (�������傤������Ƃ�) |
���A �췭� (�����{�|) ���V (�����{�~) ����� (㳁{�) �Ɗ� �h�� ���I ���Q ����� (�����{��) �e�� �אh �Ñ� ����~ ���t�q |
�������E�}������ ���Γ��� �����o������ ����{��ᇂ��u�� ���]��ᇂɂ�铪�� ���X�N����Q ����ʒ� ����ʐ_�o�� (�O���_�o��) ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����Ɠ����̋C���T�E��C�E���ŁE�����Ȃǂ�ڕW�Ƃ��ėp����B �����M�ɂ���Ă�����҂ɂ͏㕔�̉T�M�𐴂��A��������A�M��y���A�����������Ă��B����ɂ͐����(�u�{�)�ɓ����ǂ��B |
���@|
| �s�����E�t ����h���� (�������傤�ڂ��ӂ��Ƃ�) |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
|||
| �s�����E�t ���S�@�q�� (������������) |
�@�� �l�Q ���� 䨗� ����� (�����{��) �Ñ� ����~ �n���� �ԑO�q |
���t�����j �������Ҏ� �������N���� �������t᱉� ���щ� ���X�N����Q ���m�C���[�[ ���A���� ���s���� �������_�o������ ���t�f���� ���_�o�� ���O���B���� ���O���B�� ���葫�̉ΏƂ� ���P ���b�� ������ ������ �������~����p �����A�a �����I�_�o���� �������� ���A�ӕp�� ���A���� ��� ����A ���C���|�e���c ���̂ڂ��� �����_�����a ���ݒ����� ���c�A�� �����㊣�� ����̒ɂ� ���₦�� ������ ���l�����ӊ� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���S���ɐς�~�����ɐS�����������ꂵ�݁A�F�X�Ȃ��Ƃ�T�d�ɐ[���l�������A�Ƃ���ɂ�����A�߂��ݒQ���A���ւ�
�F���Ԃ�����A�����͔A���ɍ��̗l�ȍ���������A�������A�A�������k�炵����Ɠ����ɏa��ɂ݂�����A�ւ͌��̗l�ȐF������ҁA����
�͂������ʂɕ������ׂɏ㐷�����ɂȂ�A�S������t���A���ׂ̈ɔx�ɕ��S��������M���A���̔M���t�ɋy��Őt�C������A������
�ꂭ�A�̂ǂ��������A�����琅������ł��������Ƃꂸ�A���ɂȂ��Ă�����薰�邱�Ƃ��o�����A���葫�����Ă��邭�A�j���͔A�ُ̈�
�⌋�Ȃǂ̎����ɂȂ�A�����͕Ă̂Ƃ��`�̗l�Ȕ����������щ������ʂɏo�āA�A�����Ԃ�ࣂ��҂ɗp����B ����������ݒ����キ���F�����������^�ő̎�����Ȏ҂��A�ߐH��ߓx�̓��̔�J��������A�������_�I�X�g���X�Ȃǂɂ��A�S�E�x�ɋ� �M�̕a�ǂ�����A���̔M���t�E�N���ɓ��荞�݁A�A�̍����E�p�A�E�c�A���E��E�щ��Ȃǂ̏Ǐ�������҂������B �i�ݒ����キ�A�₦�����ꂽ�肷����N�����ɂȂ�ƌ����Җ{����^����B�j ���㕔�̐S�M������ɂȂ��ĉ��ł̐t�̓������キ�Ȃ�A�㉺�̒��a���������łɂ������A��ɏǏ�������ҁB �i�A���o�����ŏo���C���������ҁA�����͔A�������Ăɉk���҂���B�j �����A�a�ŁA�_�o�ǂ����˂đ̗͐����A�H�~���Ȃ��A�S�g���ӊ���i����ҁB �����ݒ�������Ă��āA�n���܂���ƐH�~����������A��ւ���邭�Ȃ�҂ɗp����B �����̏����͐S�𐴂����A�_��{���A����邵����₢�A�B�E�t���������A�C�E��������B �����̏�����p���Č��̂Ȃ��҂͏㐷�����ɑ����Ȃ��B�j�}���������a�����悢�B �����������̏�����p���ĐS���Ђǂ��Ȃ�A���I�Ȗ������Đ��t�����R�ɉk�炷�҂͗��_���̓����悢�B |
|
| �� | �s�����E���a��t�t �a�o������ (�������������Ƃ�) |
���A ���n ���Q ���G �� �З�� ���m �췭�(�����{�|) ���h�� ���(�+�)�� �h�� ���_�� ���(����+�~) 䨗� �Ñ� ���A ���I |
���Րg���ɂ��Ďh�����@�������ɂނ��Ɩނ��r�������������B���͌��ɑ����B
�����͎�F�����Ɉ����ċؖ���������j�莼�M���Ɋ����M���ɕ�܂�鎞�͑������ؗ���j��B�������ȂĒ��Ɍy����͏d���B
�X�����ȂČo��a�����������������s�炷���B���𔒌�ߕ��ɂ���s���B����E�����������B ���葫�̊߂⍘���牺���͌��E��E�r�����ɂ݁A���̕��ʂ����Ɏ���Ⴢ����������Ԃɒɂ݂������Ȃ舽�͊���E���C�ɂ�� ��������ҁB �� �� �� |
|
| �� | �s�����E�t �剩���O�瓒 (���������ڂ���҂Ƃ�) �剩���O�� (���������ڂ���Ƃ�) |
�剩 ���m 䊏� �~�Z�q ���O�� |
�������i��ᝋہj ���}������������ ���������̏����@�����j �����Փ����� �����Օ����� ���l�a�����p�B�� ���֔�@�������d���� ���畆�a�@���������� �������牺�^� ����͉� ���\���t�����P�� ���q�{�t���퉊 �i���lj��E�������j ���o���g�������B�� ���q�{������ ���X�N����Q ���咰���@�������� ���������@���t᱉� ���t�f���@���ҕa ���A�@���O���B���� ���A�����@���Y��M ���щ��i������́j �����B���@���s���� ���Ŗo�@����a �����Ɂ@������ �����ł� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���֔�̌X��������A�������������̉��ǁi���j�A�����͕����A�����͕��ɁA�����͉��^�ǂ̎ҁB���ǁA���^��
��蔭�M������҂�����B �������Ɏ���V�R����������A�����ɐG���Ό������ɂ݁A���ւ̏o�͕��ʂ�����ǁA�����ɒɂ݂�����ׂɏ��ւ�����x�ɂЂт��� �ɂ݁A���X���M���Ċ��������A���̔M�����������㏭�����Ĉ���������܂����M���Ċ��������Ƃ������Ǐ���J��Ԃ��҂́A���̒��� �^��ł���O���ł���B���̗l�Ȃ��̂ɂ͂��̏������厡����Ƃ���ł���B �����ɂ��������M�������A��ւ������A���̗���������ɂ��A�傫�Ȏ�ꕨ�������B �����̏����͋�I(�ϲ��ځ{��)���܂��b���܂ɂ��\������A���^�ׂ̈ɋN�������I(�ϲ��ځ{��)���z��Q������ ���Ƃɂ��A���ǂ�����������̂ƍl�����܂��B ���D�w�͗��Y�̋��ꂪ����̂ŕ��p�͔�����B |
| �s�����E�t ��Čӓ� (�����������Ƃ�) |
�Č� ����� (�����{��) 䉖� ���� �k�� �剩 �垥 ���I |
���_�Ώǁ@���֔� �����t�@���_�o���� ���@���]�@�����] �����d�@������ ��������@����J�� ���P�@���C�ǎx�b�� ���C�ǎx�g���� ���x�C��@����ʒ� ���ԗ��@���咰�� ���A�~�@��� �����Ɂ@�����A ���r�A�Ɂ@������ ���߂܂��@�����@�o�� �����S�E���� ���m�C���[�[�@���C�T�� ���S���ٖ��ǁ@���~�� ���S�؍[�ǁ@���S�X�� ���S�����b���@���X���� ���h�t�E��������� ���r�C�@���� ����@����A��� �����Ɂ@���Ô��� ����s�@���t�P�� ���b���@���ݎ_�ߑ��� ���\��w����� ���_�Ώ� ���ݒ��J�^���@������ ���咰�J�^���@���x�� ���]�����@���������� ���]�o���@���_�X�� ������ǁE�얞�� ���s���ǁ@���̍d�� �����A�a�@���p�A ���]��ǁE�]�[�Ǐ� �����g�s���@�������Q �����s�����` �i�C���t���G���U�j ���������@�����`�t�X ���͍g�M�@���O�� ���}���E�����t�� ���l�t���[�[ ���ޏk�t�@���t�f���� �����ʖїl�̉� ���p�����@���}�����A ���c�A���@�������� ���̉��@�@���}���ݒ��� ���ݒ�ᇁ@�����L�� ���������@�������� �����ӊ��@���w���y�X ���s�D�� ���]�Ԑ_�o�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����Čӓ��������e�ꖞ�̒��x�������A���͂��L��A�X�ɓf���C�����A�݂̕ӂ肪���ߕt�����銴�����L��A����
��i���A��͊��������ۖ��͉����F�ŁA���͒��E���ŁA�M�����܂�Ȃ��ҁB ���g�̂̉��ɔM������A���X�q�f���A�����͕���H�ׂ鎞�ɓf���A�����͐H��������Ɗ����o�āA�����͑O���̏Ǐo���ɋꂵ����݂� �����̕ӂ肪�ɂ��A�֔�����Ă���ҁB �����ׂ��Ђ��A�M������A�����������M�������炸�A�݂̕ӂ肪�����ďd�ꂵ���Ȃ�A�g�̂̉��ɔM������A�f���ҁB �����Čӓ��̏ŁA�֔邷��Ɠ��d�Ȃǂ��N����ƌ����҂ɁA���̏������������Ƃ������B �����Čӓ���p���Ă��A�q�f�~�܂��A�֔邵�A����������A�オ�����āA���F�̑ۂ��t���Ă���҂ɂ͑�Čӓ���p����B ����Čӓ���p����l�Ȏ҂ŁA�`�̕ӂ�œ��������i���āA�_�o�Ǐ�̋����҂ɂ́A�ČӉ��������a����p����B ����Čӓ���p����l�Ȏ҂ŁA�����ɕq���œ�����������A�����͋��������肷��a�L��A�����ł��Ȃ��҂ɂ́A�ČӉ��������a���� �p����B �@��������Čӓ����A�������ĉ������A�C�����������Ȃ�҂́A���̏����̓K�p�ǂł͂Ȃ��B �����Čӓ��E��Čӓ��E�ČӉ��������a���E�Čӌj�}���I���Ȃǂ̎ČӍ܂́A���̕a�C�����ł��낤�ƕ��ɂ��p����B ������������A�x���g�Ȃǂ���Ƌꂵ���ƌ����ҁA�ڂ̕t�����ł���B |
|
| �s�����E�t �����p (��������) |
���A �j�� �剩 䉖� �n�� ���Q ���V (�����{�~) ���X �Ӗ��� |
���O�� ���������� ���Ђ� ���Ώ� ���C�{ �������� �������i��ᝋہj �����̖� �������� �������� ����� ���A�g�s�[���畆�� �����Ԃ� ���^�o�] ���j�L�r �����v ���������� �������� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����_�p�Ɠ��l�ɂ�����畆�a�Ɍ��ʓI�ł��B ���M���̋������^�ɂƂĂ��ǂ������܂��B �������p�Ǝ��_�p�ƒ����p�̎g�������́A�������畆�a�ɂ͎��_�p�A�����p�̓W���N�W���N����畆�a�A�M���������畆�a�ɑ����p���g�p���Ă݂ĉ������B |
|
| �s�����E�t ���b�� (��������Ƃ�) |
�� ���Q |
�����j�G�[���nj�Q ���߂܂� �����` ���݉����� ���݃A�g�j�[�� ����蕨���� ���t�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���������l�܂��ċꂵ���A���ꂪ���A���̏�ɉ����킳���Ă��邩�̔@���������L��A�߂܂������͓����{�[�b�� ���ď��ւ̏o�������ҁB���̎��̂߂܂��͋N���オ������A�������肷�鎞�ɖ�ῂ��������łȂ��A�A�Q���Â��ɂ��Ċ���҂��Ă� �Ă��ڂ����A�g�C���ɂ��s���Ȃ��Ƃ������̎҂ɂ��p���܂��B | |
| �D���O(��)�� �j�}䨗�ۂɋL�� |
||||
| �O���ꡎU�� ����疗y�U�ɋL�� |
||||
| �� | �s�����E�t �����p (���イ��������) |
�T�� ���� ���X �Ӗ��� |
���}�����^���畆���� ����ꕨ ���P�� ���Ŗo ���Ώ� �����Ă� �������� ���E�� ���u�� �����ł� �������� �������� �����Ԃ� ��������� ���@���] �����] ���Ƃт� ������(��ᝋ�) ���^���V ������ ���т�畆�� ���Ђ� ���������� �����r�� ���A�g�s�[���畆�� ���߉� ������ �������� ���ؓ��� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���Ŗo���Ă��̎���ɏ�������A���z�܂��\��Ȃ����ɓh�邩�h�z����B ���M�����̒ɂ݂��y�݂ɗǂ������O�p�܂ł��B |
| �����v�C�� (���傤���イ�������Ƃ�) |
||||
| �s�����E�t �ޓ��U (���傤�Ƃ�����) |
�k�� ���� 䨗� �l�Q �e�� �h�� �p �Ñ� ���G �ޓ��b ����~ |
�����j�G�[���nj�Q ��ᒐ� ������ ���V�l�̊�ł� ���ɂ�߂܂� ����῁i�߂܂��j �������� �����w�S�} ���ዅ�[�� ���T�a ����ԔF�m��Q(�F�m��) ���m�C���[�[ ���X�N����Q �������d���� �������_�o������ ���������� ���]�����d���� ���]���Ǐ�Q ������ ���s���� ���_�o�� �������t�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���_�o�ǂŋC�̏�Ղ��Ђǂ��A�̂ڂ��E���ɁE�߂܂��E������E���w���������z�����ċ��L���鎖���o�����A�ዅ��
�[�����₷���ҁB ���C�����d���A�����Q���œ��ɂ�����A�N���サ�炭���ē��ɂ���ҁB |
|
| �s�����E�����G�a�_�t ���蓒 (����ꂢ�Ƃ�) |
���� 䨗� ���� �V�b ���P |
���t�� ���N���� �����A�� ���A�H�̉��� ���l�t���[�[ ���t�Ώ� ���N������ ���A�H���� ���A���� ���Ҏ��� ���A�ӕp�� ���r�A�� ���t᱉� ���t�����j ���q�{�o�� �����o�� ���\�� �����֕s�� ������ ��������� ������ ������ ���Ђ��� ���� ���s���� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���������ɔM�L��ď��ւ��o�Ȃ��ҁB ���M���L��A�����o�āA�A�����đ傢�ɐ������݁A���ւ��o�Ȃ��ҁB �����ւ̉������������o�����̓s�x�傢�ɒɂގҁB �����ł̟T�M�ɂ�艺���̋C�Ɛ����ʗ������A�C�̏�Ղ��������҂ŁA���������A�x�X�A�ӂ����邪�A���قƂ�Ǐo�Ȃ��ŒɂގҁB �����������������A�����������A�C���C�����ĕ������C�ɂ����鏬�ւ��o�ɂ����ҁB �����ւ��o���A�����ꂵ���A�����̎ҁB ���z���a�ŁA�������M�������֕s���̎ҁB �����ӁI�I�@�z���a�Ŋ������o�Ċ�����҂͒��蓒��^���Ă͂����Ȃ��B���������o���ׂɈݒ��������Ă���̂ɁA �X�ɒ��蓒�����ւ��o���Ă��܂��Η]�v�Ɉݒ����������Ă��܂��B ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
|
| �ĉv�C���� �Z�N�q���ɋL�� |
||||
| �� | ||||
| �� | ||||
| �� | �s�����E�t ���j���C�� (�Ƃ��������傤���Ƃ�) ���m���C�� (�Ƃ��ɂ傤���Ƃ�) |
���m �j�} �剩 䊏� �Ñ� |
�������i��ᝋہj ������i���̗₦�j �������Ɂ@������ �������g�̉��^ �����o�s�� �����o����� ���]���o�� ���������� ���A�g�s�[���畆�� ���}�������咰�J�^�� ���N�����@���N������ ���b���@�����̓��� ���q�X�e���[�@���s���� ����῁i�߂܂��j �����Ɂ@�������� �����Ɂ@�������_�o�� �������g�J���u���P�� �����j�i�C�{���j ����͉��@���K�����֔� �������_�o������ ���X�N���nj�Q �����Ɂ@���@�� �����Փ����� �����Փ����� ���q�{������ ���t���퉊�@����a �����ڐÖ�� �����ǖ����@������ �����M������ ������@������ �������@�����Y�� �����g���p�`�[ (�N���o���j ���s�D�ǁ@�����Y�� ���o���g�������B�� ���m�C���[�[�@���� �����N�a�@�������d���� ���]�����@�����S�� ���~�^�ǁ@���T�a �����B���@���Ŗo�� ���̂ڂ��@���@���] ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���֔�̌X��������A�Ԃ��ɂȂ�₷���A�����₦�A�����͉����ɂ�����A�����͍��ɂ��L��A�����͉����g��
���^������ҁB ���������̟T���������\�I�ȋ�I(�ϲ��ځ{��)���܂ł��B ���D�w�͗��Y�̋��ꂪ����̂ŕ��p�͔�����B |
| �s�����E�t ���A������ (�Ƃ������イ�Ƃ�) |
�� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�� | ||
| �s�����E�t ���A�U (�Ƃ�������) |
���A 䉖� �췭� (�����{�|) ����� (�����{��) ���Q ���{�� |
�����Y�� ���Y��{�� ���Y��a ���s�D�� �������� ���C�{�� �����֕s�� ���֔� ������ ���q�{����� ���q�{�z�� ���q�{������ ���n�� ����J���� ����� ����������� ������ ����� �����Y ���p�A ���D�P���ŏ� ������ �����d ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
��������荘�ɂ����Ēɂ݁A�����͂����������Ēɂ݁A�����͐H�~�͗L�邯�Lj��H������������Ēɂ݁A������
�g�̂ɗ͂����炸���ꂷ��ҁB ���D�P���A��ɕ�����ΐԎq�i�َ��j�̔���E���Y�ɗǂ��B ���Y��A���ւ̉����ʂ����Ȃ��ҁE���֎��ւ��₷���Ȃ����ҁE���ɂȂ����ҁE�n���ɂȂ����ҁE����A�얞�ɂȂ����ҁE����� ��ῂ⓪�ɂɂȂ����҂Ȃǂ������B �i�Y��̕a�A�S�a�������ƌ����Ă��܂��B�j �����Y�Ȃ�����҂͖{����蔒�Q�U�̍����҂������B |
|
| �s�����E�t ���A�l�t������ΐ��I�� (�Ƃ��������Ⴍ��������䂵�傤���傤�Ƃ�) |
���A �j�} 䉖� �ؒ� �אh �Ñ� �垥 ���G ����� ���{�� |
�������i��ᝋہj ���₦�� ������ ������ ������ �������_�o�� �������₯ ���E�s ���q�f ���f���C ������ ���P ��� ���b�� ���畆�a �����C�m�[�a ���_�o�� ������� ���w���j�A�̒ɂ� ���{���� �������� ���w�l���Օ����� ������ ��etc�E�E�E�E�E�E |
���葫���₦�A�����͍����╠�����₦�ċꂵ�ގҁB ���葫�₽���A���قƂ�ǐG�ꂸ�A���ɂ�f���C�̂���ҁB ��������݂̒����₦�A����ɂ�苹���������ċꂵ�݁A�����͓f��������ҁB �����A�l�t�����Ă����ʂ��݂��Ȃ���A���̊�������Ă݂܂��傤�B �����̏����͎�Ƃ��āA�����̊���ƕ\�̊���������B |
|
| �s�����E�t ���A䉖�U (�Ƃ������Ⴍ�₭����) ��䉎U (�Ƃ����Ⴍ����) |
���A �췭� (�����{�|) 䉖� 䨗� ���Q �� ���{�� |
������(��ᝋ�) ���n���@���₦�� ����J�@�����o�s�� ���s���ǁ@������ �����Ɂ@�������_�o�� ���_�o�Ɂ@�����E�}�` �����g�s�� �������Ɂi���o�Ɂj ���q�{�o���@���щ� ���q�{����@���q�{�E ���X�N����Q �����Y��@���B�a�� �����o������ �������t���@���D�P�t ���s�D�ǁ@���r�C �����j�@���E�� ����A�ǁ@���~�^�� ���S�����i�� ����῁i�߂܂��j ���l�t���[�[�nj�Q ����^���p�N������ ���S�������� ���b��B�@�\�ቺ�� �������̋@�\�ቺ�� �������i����~������j �����ӊ��@�����d ������i�ނ��݁j �����Y�E���Y�� ���q�{�z�� �����o�~ ���m�C���[�[ ���q�X�e���[ ���݃A�g�j�[ ���݉����@�����z�� �������@���������� ���ጌ���� �����j�G�[���nj�Q ���o�Z�h�[�a ���S���ٖ��� ���A�k�t ���ݓ��␅ ������ ������ �������� ����ᬁi�j�L�r�j �����݁E������ ���C�{ ������ ���@�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���n�����͒ጌ�����͑̉����Ⴍ�A�₦�ǂŔ��₷���A���֏��Ȃ����͉����A���ɉ����������ɐr�������A
�߂܂���̂ǂ������Đ���~������ҁB ���D�w���A�}�ɕ��ɂ�����ҁB �����̃I(�ϲ��ځ{��)���i�����j�Ɛ��łɂ��Ǐ�̎ҁB |
|
| �s�����E�t �Ɗ��� (�ǂ����������Ƃ�) |
�Ɗ� �l�Q �h�� �`�ޮ�(�����{�{) �K�� �m�� ���G �j�} �c�d �췭�(�����{�|) �n�� ��� 䨗� �אh �t�Ñ� |
���߂�Ⴢ� ���߂̒ɂ� ������ ���w���� �����E�}�` �������_�o�� ���₦�� ������ ������ ���}���D������ ����etc�E�E�E�E�E�E�E |
���߂̂��т���u���悤�Ȓɂ݁A�����͓~�ɂȂ�ƈ�������߁A�����͈֎q���痧���オ�鎞��
�K�i�̏�艺��ɕG�߂��ɂށA�����͔w�����ɂ������ԍ����Ă����Ȃ��A
�����͕G�ɐ������܂�����Ȃ����̒ɂ݂�����҂������B ���̎��͐��E�����E�C�� |
|
| �� | ||||
| �� | �s�����E�t ���_�U (�ɂ債��) �@�_�U (�ɂ債��) ���h�� (�����Ƃ�) |
���A �췭�(�����{�|)���Q �j�} �l�Q ����� (�����{��) �F�P ���A �؍� �Ñ� ���� �剩 �����q |
���̂ڂ��� ���߂܂� �������� ������ �����̓��� ���T�a ���m�C���[�[ ���_�o���� �����j�G�[���a ���X�N����Q �������_�o������ ���Y��̐_�o�� ���ݒ��_�o�� �����o�s�� �����o����� ���s�D�� ���s���� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�������g���₦�₷���A�炪�Ђǂ��̂ڂ��A�����A�����͂߂܂������A�Ȃ��Ȃ��Q�ꂸ�A�֔邷��҂������B ���Y�O�Y��ɋN�����������_�o�Ǐnj�Q�ŁA�̂ڂ��Ƃ߂܂���i����ҁB ���̂ڂ��͂��܂�Ђǂ��Ȃ��A������A���ɁA�߂܂��A�s�����ȂǗL��҂ɂ́A����疗y�U���ǂ��B ����������������قNj����Ă��Ȃ��B |
| �s�����E�����v���t �l�Q�� (�ɂ�Ƃ�) ���������͊� (�肿�イ�Ƃ��܂��͂���) �j�������� �i�����Ԃ肿�イ�Ƃ��j |
�l�Q ���I ���Q �� |
�����Ɂ@���f���C�@ ���q�f�@�������@��� �������ǁ@������ ���C���t���G���U ���}�����J�^�� ���H���Ł@���Q�b�v ���ݒɁ@���ݒ��␅ ���₦�ǁ@�����Ă� ���ݎ_�ߑ��ǁ@����� ���(���т�)�@���֔� �����s�s�ǁ@ ���ݒ�� ���}���ݒ��J�^�� ���S���|�d�@���_�o�� �������ݒ��J�^�� ���]�Ԑ_�o�Ɂ@�����M ���ޏk�t�@���G�̒ɂ� ���\��w����� �������������@���P �������s�Ǐ� �����Ɂ@���p�A ��������@���\�� ���A�g�s�[���畆�� �����Ώǁ@ ���݉����� �������a ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���ݒ����₦�āA��������ݒɂ������蕠���ɂ�Ŏ葫���₦�ĉ������₷���ҁB �����������o�āA�M���������H����ƃ��Z����A����Ώ�������A�Q�b�v���o�₷���ҁB ���ݒ����ǂ��胀�J���J���₷���ҁB |
|
| �� | ||||
| �� | ||||
| �� | ||||
| �s�����E�t �r�^�U (�͂��̂�����) |
�k�� 䉖� �j�[ ���� |
���R���i������ ���j�L�r �����ł� ���G���B�� ���牺�^� ����A�� ���J���u���P�� �����o�� ���t�����P�� ���~�^�� ���Ƃт� ���`�����^�o�] �����^������ �����^���畆�� ������ ������ ����(�ϲ���+��) ���M��(�ϲ���+��) ��� ���j �������p�B�� �����B�� �����[�� ��ˮ�(�ϲ���+�[)�s �����j ���I�|�D�� ���؉� ���G���^� ���~�^�� �������� ����ꕉ� �������a �����̂��炢 ���߂��� �������� ���O������ ���O���� ������ �������͔畆�� ����� ��������� ���]��� ���_�O���X�|�^� ���x���s ���� ���^� ���^���� ����� �����щ� �������� ���牺�^� ���R�E �������^�R ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���k���͊����ْ̋����ɘa���Č��d��a�炰�A䉖�͞k���ɋ��͂��ċْ���������u�ɂ��y�����A�j�[�͉��^��h�~���͔^��r�o���B �����������肪�L��A�^�������ɂނ��́B �����ĔM������������́B ���牺�[���^������A�Ȃ��Ȃ��\�ɏo�Ă��Ȃ����́B ���u�ɂ����^���̎�ŁA�C���Ñ��A�������ْ����A�����Z�������r�^����ŁA���d�̏�Ԃ������Ă��鏔�����B ���r�^��A��ᇂɂȂ��Ă����͂̐Z���������ْ����A���d�̂��́B ���C���̋Ñ��J���A���^�𑣂��A�r�^�𑣐i������B ���r�^�U���I���A�^��ɂ݂�M�����a�炢�ŋ��ɂȂ�A����ȏ㎡��ɂ����ꍇ�́A�r�^���܂��͔r�^�U�y���ɑウ��B ���r�^�U�p���A�ݒɂ≺���ɂȂ�҂́A�r�^���܂��͔r�^�U�y���ɑウ��B�A����ῂ��ǂ������f���ׂ��B �����������F�ŁA����A�ɂ݂Ȃǂ��L��A�^�`���o�Ă�����́B �������^ᇂ▝���̎�ɂ́A�s�K�Ȃ��Ƃ������B | �s�����E�t �r�^�U�y�� (�͂��̂����イ�Ƃ�) |
�k�� 䉖� �j�[ ���I �垥 �Ñ� |
���R���i������ ���j�L�r �����ł� ���G���B�� ���牺�^� ����A�� ���J���u���P�� ���t�����P�� ���~�^�� ���Ƃт� ���`�����^�o�] �����^������ �����^���畆�� ������ ������ ����(�ϲ���+��) ���M��(�ϲ���+��) ��� ���j �������p�B�� �����B�� ��ˮ�(�ϲ���+�[)�s �����o�� �����j ���I�|�D�� ���؉� ���G���^� ���~�^�� �������� ����ꕉ� �������a �����B�� �����̂��炢 ���߂��� �������� ���O������ ���O���� ������ �������͔畆�� ����� ��������� ���]��� ���_�O���X�|�^� ���x���s ���� ���^� ���^���� ����� �����щ� �������� ���R�E �������^�R �����o�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���u�ɂ����^���̎�ŁA�C���Ñ��A�������ْ����A�����Z�������r�^����ŁA���d�̏�Ԃ������Ă��鏔�����B ���ݒ����キ�A���^�܂��͉��ǂ��L��ҁB |
| �s�����E�t �r�^�� (�͂��̂��Ƃ�) |
�j�[ �Ñ� �垥 ���I |
���R���i������ ���j�L�r �����ł� ���G���B�� ���牺�^� ����A�� ���J���u���P�� �����o�� ���t�����P�� ���~�^�� ���Ƃт� ���`�����^�o�] �����^������ �����^���畆�� ������ ����(�ϲ���+��) ���M��(�ϲ���+��) ��� ���j �������p�B�� �����B�� ��ˮ�(�ϲ���+�[)�s ������ �����j ���I�|�D�� ���؉� ���G���^� ���~�^�� �������� ����ꕉ� �������a �����B�� �����̂��炢 ���߂��� �������� ���O������ ���O���� ������ �������͔畆�� ����� ��������� ���]��� ���_�O���X�|�^� ���x���s ���� ���^� ���^���� ����� �����щ� �������� ���R�E �������^�R ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���\�ɔ^���o�Ă�����̖��͏o�����Ȃ��́B �����^�����܂��͐�����߂��ĊɏǂɂȂ�A���ŔM���̌`�̂��̂ŁA���^�ǁA���ǂ̂��́B ���Z�����キ�A������������_�炩���A�ْ����キ�A�^�╪�啨�����܂葽���Ȃ����́B ���r�^�U���I���A�^��ɂ݂�M�����a�炢�ŋ��ɂȂ�A����ȏ㎡��ɂ����ꍇ�́A�r�^�����͔r�^�U�y���ɑウ��B | |
| �� | �s�����E�t ������ (�͂��݂���) �����n���� (�͂��݂���������) �����t�C�� (�͂��݂�����) �t�C�� (������) �����t�C�� (��������) �j�������� (�����Ԃ͂��݂���) ���j������ (�Ԃ����͂��݂���) ���������� (�������͂��݂���) |
���P �� 䨗� �j�} ���n�� �R��� ���O�� �{���q |
���b���@���p�A ���c�A���@���A�� ������@���߂܂� �����Ɂ@���r�̒ɂ� ���葫�̉ΏƂ� ���葫�̂��т� ����J���@�����ӊ� ���ᐸ��J�@���s���� �����Ɂ@���Г��� ��������@�����̕��� �������@������ ���q�{�E �i�A�ցE�A�ہE�A�E�E �A���E�E�֎q���E �A���E�A���j ���V�l��� ���_�o��� ���A���ǁ@������ �������@������ ���s�D�ǁ@�������o ������@���t�f���� ���t᱉��@���t�����j ���`���A�@���N�����j ���N������ؖ�� ���N��������Q ����`���Ғŏ� ���Ŋԓ�w���j�A ���V���t�@���A��~�y�� ����ᝁ@����� ���b���@���x�C�� ���ƌ��@����� ���E��@���щ� ���m�C���[�[ �����Y�ǁ@�������낤�� ���X�N����Q�@�����A �������_�o������ �������E�}���t�� ���l�t���[�[�nj�Q ���t�d���ǁ@���������� ���щ��@��������p �������_�o�� ���V�l���s���� ���V�l���T�w���� �������̖�Ⴡ@�����A�a �����s����@���Ґ��� ��������@���Ɏq�̍��� �����ߐ���@���p���� ���Γ���i�����Ёj �����o���i�Ԗ��o���j ���Ԗ������@���ޏk�t ���V�l���畆�~�y�� ���V�l���N���ޏk ���@���]�@�����] ���N�����@���O���B�� ���O���B���@���A���� ���֔�@���A�~�E�z�~ ���C���|�e���c �����͌��� ����E���� ���A�s�d���ǁi�����a�j ���]�������� ���]�o���@�������d���� �����R�@����A�� ���ጌ���ǁ@���_�o���� ���₦�ǁ@���N���� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���g�̎キ�A���₷���A���������Ēɂ݁A���ɂ�����A���ւ̏o���������͏o�߂���ҁB �i���ɖ������d�˂Ĕ��ċN���������ɂɗǂ������B�j ���r�C�ɂ��r�≺���������т�ė͂��͂���Ȃ��ҁB ���̂ǂ��傢�Ɋ�������~������A�������߂Έ��������ւɏo��ҁB �i�钆�ɂ̂ǂ������Đ������ގҁA�����͏�������A�钆�ɖڂ��o�߂Č����������ҁA�����ۂ̏ؑ����B�j �����ւ̏o�͕��ʂ����A���ꂵ�₷���ҁB ���w�l�ő��ꂪ���āA�閰��Ȃ��A��⑫���ΏƂ�ҁB ������������A�A�ʂ������A�P������x�ɏ��ւ��k���ҁB ���щ���r�A�ɂɔ����ۂ��������A���_���̓��Ō�����������B �i����������炩���c��Ă���҂ɂ͔����ۂ̏��悭����B�j ���������`���牺�ӂ肪��㖳�͂ŁA�u���u�����Ď艞���̂Ȃ��ꍇ�ƁA�������������ōS�����čd���A���牺���������ċꂵ���� �i����҂Ƃ�����܂��B �����������A�����͌���������A���A���������A�p�A������A�r�A�ɂ�����҂ŁA�ݒ���Q������A���蓒�E�ܗ�U�Ȃǂ��l���܂��傤�B ���ݒ���Q�i���S�E�q�f�E�S���|�d�Ȃǂ݂̈̏Ǐ�������j������҂�A�ݓ��␅�������Ȏ҂ɂ͔����ۂ�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B �{�����ĐH�~����������A����������������A�����ۂ̓K���ǂł͂Ȃ��B |
| �s�����E�t ���Č��p�� (�͂����ڂ��Ƃ�) |
���� ���p 䨗� ���I �h�t |
���s���ǁ@������ ���̂ǂ̋l�芴(�~�j�C) ���̂ǂ̃C�K�C�K�� ���H������ ���H���e���� ���H���z�� �����啂�� �����킪�ꐺ �����ѕ���@���֔� ���_�o���H������ ����A���@���o�Z�h�[�a ���_�o���S�����i�� ���p�j�b�N�nj�Q ���p�A�@������ ���f���C�@�����Ă� ���H�~�s�U ���S���_�o�� �����̓��ǁ@���_�o�� ���ݓ��␅�@����ʕ��� ���A�X����@���t�� ���l�t���[�[ ���X�N����Q ���_�o���� ���C�T�ǁ@���T�a ���C�ǎx�� ���C�ǎx�b�� ���_�o���݉� ���P�@�������}���݉� ���_�o���q�f�@��� ���q�X�e���[�@�����|�� ���m�C���[�[�@���S���P �������_�o������ ���D�P�q�f�i���j �������o�@���s�D�� ���s�����@���E�я� ���葫�̂��т� ���ݒ������ ���݉����ǁ@�����d ���݃A�g�j�[�� ���T�a�@���G���� ���b���@������ ������ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���̂ǂ̒��ɉ������̉�ł��L�邩�̔@�������l�܂��Ă��銴�����L��A���ݍ������Ƃ��Ă����ݍ��߂��A�f������
���Ă��f�����A�����͋��̕ӂ�ɋl�܂����������L��A�����͂̂ǂɉ��ǂ����������C�K�C�K���ĊP����������A�l���݂ɏo�������
�߂܂����Ђǂ��Ȃ铙��i����҂������B ���C�����ǂ��A��A��H���Ɉٕ����������A���ɓ����A�߂܂��A�f���C�ȂǑi����҂������B ���C���㏸���Ă̂ڂ���̂ǂ̃C�K�C�K��������A��a�E����E���ɁE���d�E�����E�@���E�@�Â܂蓙��łɏǏ���ĕ֔�̎ҁB ���n���E���́E�������̐r�������҂́A���̏���������Ȃ����������̂Œ��ӂ��K�v�B ���Ђǂ����̎҂ɋ����Ђǂ��Ȃ邩��A���p�̔z������Ă�����܂�^���Ă͂Ȃ�Ȃ��B |
|
| �s�����E�����_�t ���ĎU�y�� (�͂��イ�Ƃ�) |
���� �j�} �� |
�������̒ɂ� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����A�a�ŁA�������j��ď��ɂȂ�A���𗘂����Ƃ��o�����A�����o�����Ƃ��Ă��o�Ȃ��ҁB �� ���쐬���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E |
|
| �s�����E�t �����b�S�� (�͂��Ⴕ��Ƃ�) |
���� ����� (�����{��) ���I �l�Q ���A �Ñ� �垥 |
�����@�������� ���}���݃J�^�� ���}���ݒ��J�^�� ���C���t���G���U �����j�@������ ��������@���݊g�� ���ݒ�ᇁ@�������݉� ���\��w����� �������s�Ǐ� ���ݒ��_�o�� ���H���Ł@���q�f ���ݎ_�ߑ��� ���݉����ǁ@�������� �����V�a�@���f���C ���A�����M�[���畆�� ���A�g�s�[���畆�� ���@���]�@���畆�a ���h�t�i���������j ���֔�@���_�o���� ���o�@���� �������a�@���H�~�s�U ���ݓ��␅�@���ߎ_�� �����y�������@���s���� ���s���ǁ@���m�C���[�[ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����̂����肪�ǂ���������������A���J���J�Ɠf���C������A�q�f������A�H�~�s�U�̎ҁB���̗l�ȏǏ�ŁA
�����̒����S���S���Ɖ��𗧂āA����������ҁB ���݂̂����肪�d�ꂵ���A�݂���������A��������A�ݒɂ����������肷��҂ŁA���J���J�Ɠf���C���Â��A���͋��Ă����������ҁB |
|
| �s�����E�t ���Ĕ��Q�V���� (�͂тႭ����Ă�܂Ƃ�) |
���� ���Q �� 䨗� �V�� ���G �_�� ���� �l�Q �� ���� ���I ���� ���Q |
�����j�G�[���a �������_�o������ ���݃A�g�j�[�� ���݉����� ���H��̓��� ���H��̓��d ���ጌ���ǂ̓��� ���������� ���ݒ����͏� ���߂܂� ���₦�� ���₦�ē��� ����J�� �������� �����S ���q�f�@���]�����d���� ���O��_�o�� ���������x���O�nj�Q ���]���Ǐ�Q �����@�o���i�~�^�ǁj ���H��̌��ӊ� ������ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
����������ݒ�����ňݓ��␅������A�O����_�o�I�V���b�N���͐H���̕s�ې��Ȃǂɂ��A�ݓ��̐��ł����h����
��t���A���C�������A�ጌ���̌X��������A��⑫���₦�āA�g�̂��d�����邭���₷���ҁB ���H�����Ƃ�Ɣ��A�g�̂����邭�Ȃ�A�������Ȃ�����A���ɂ⓪�d������ҁB |
|
| �� | �s�����E�t ���Q�U (�тႭ�������) |
���Q �췭� (�����{�|) 冞� ���a |
�� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���D�P���ɕ������₦�₷�����ɂ�����ҁB ���₦�₷����Ԃɂ��蔒���щ����o��ҁB �����Y�̕Ȃ�����ҁB ���D�P���̗{����B |
| �� | 䨗�j�}���Q�Ñ����� ��j�Q�Ó��ɋL�� |
|||
| ���j�����ہ������ۂɋL�� | ||||
| �s�����E�t ���q��ē� (�Ԃ������ׂ��Ƃ�) |
���q �d�� ���� �垥 �Ñ� |
������ ������ ���֔� �����ؒ�(����) ���q�f �����z�� ���H�勷��� ���ݒ�� ���_�Ώ� ���X���� �������� ���q�{�� ������ �����r�̒ɂ� �����l��(���l��) ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
������������A�S���S���Ɖ������āA���̂����肪������邩�̔@���ɂ݁A�e�����狹���։����グ�銴���Śq�f
����ҁB ���̎҂̂����͕������ؒɂ̎��A�����͊��������������A�]�v�ɂ���������o���A���̌�A�a���������������A������ �������g�܂�����̒��肪����҂ɗp����B �������Ɋ��₪�L��A�������ɂ݂�i����ҁB |
|
| �� | �s�����E�t ���ݎU (�ւ�������) |
���Q ���p �� �垥 ���I �Ñ� |
�������� ���ݒ���Q ���H�~�s�U ���ݕ��̂��� ���}�������݃J�^�� ������ ���b�� ���ݒ��_�o�� ���}�������s�Ǐ� ���S���a ���Ꮎ�� ����� ���畆�a ���݉����� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����̗͂�����A�ݒ��ɐH�������������A��������A�݂̂����肪�s���ŁA�����Ԃɂ����Ɩc����������ҁB
���͋}���݉���̐H�~�s�U�E�����݉��ŕ��������邪�C�������ǂ��Ƃ����ҁB ���ݒ�����ŕ��ׂ������₷���ҁB �����̗l�ȑ̎��̎҂œ��ɁE�P�E�b���E�S���a�E�Ꮎ���E��ጂ̎҂ɍL�����p�����B |
| �� | �s�����E�t �h�߉��˓� (�ڂ����������Ƃ�) |
�h�� ���� ���Q ���I �垥 �Ñ� |
||
| �s�����E�t �h���ʐ��U (�ڂ��ӂ������傤����) |
���A 䉖� �췭� (�����{�|) �A�� ���� ���G �t�H �h�� ���� �剩 䊏� �j�[ ����� (�����{��) �p �Ñ� ���� �R���q ���Q |
�������i��ᝋہj �����b�얞�� ���֔�� ���t���������� ��������@������ ���̂ڂ��� ���]�o�� �������d���� ����ԕ@�@�������� ���畆�a�@���~�^�� ����a�@�����A�a �������@���~�� �������Q �����т�@���܂̊��� ������@��� ���b���@������ ���C���t���G���U ���x���@���C�ǎx�� ���}���t�� ���}���̉� ���_�X���@���t᱉� ���N���� ���畆���^�� ���ݒ����@����� ���O�Ł@���Ô��� ���r�C ���^���_�o��� �����g�s���@���ޏk�t ���₦�Ɠ��� ���X�N����Q ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���̎��I�ɔ얞�������̎��ŁA�̂ڂ��ǂŁA�֔邪����A���͑�ł����������ďo�Ă���ҁB�������A������얞
���Ă��Ȃ��҂ɂ��g���܂��B ���̓��ɐH�ŁA���ŁA�~�ŁA���łȂǂ̎��ƒ��ł��A�w�\�𒆐S�Ƃ��ĕa�ł��[��(�T��)���Ă��� ���̂��A����A���ւɔr�o���A��ł����p������܂��B �������������[�����ė͂�����ҁB���������A�����̌X���̂��� �҂ɂ͗p���Ȃ��B |
|
| �s�����E�t ��C������ (�ق����イ�Ƃ�) |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
|||
| �s�����E�t �⒆�v�C�� (�ق��イ�������Ƃ�) �㉤�� (�������Ƃ�) |
�l�Q ���Q ���A �� �Č� ���� �Ñ� ���� ���I �垥 �i�����I�j �i���垥�j |
������҂̊��` ���s���ǁ@���ጌ�� ���N���������� �������_�o������ ���ݒ����@���̉� ���ؖ��͏� ���݃A�g�j�[ ���E��@���q�{�E ���V���t�@���w���j�A ���A�����M�[�������a �����������������a ���������@���q�{���� �������ǖ��͏� ���A�g�s�[���畆�� ���A�����M�[���畆�� �����Ɂ@���ᐸ��J ���������@���Q���� �����@���₦�� ���p�A�@������Q�� ������҂̔D�P ���S�g��J�� �����Ɂ@���߂܂� ����������� �������@������ �������@��枌� ���葫�̌��ӊ� ���Ă₹ �����������M�nj�Q �������o���� ���Y��̎q�{���Õs�S �����o�ߑ��@���p�����o ���s������o�� ���������M ���a��̔�J���j�� ���H�~�s�U ���݉����@�����g�s�� ���]�������� �������ǁ@������ ���щ��@���n�� ���C���|�e���c ���j���s�D�� ������̎��@���A�~ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���S�g�Ƃ��ɔ�J���āA�����͒�����̌��܂������ԂɐH�~�o��������������H���鎖���o�����A����ɂ��̂�
���Ă��������đӂ�����Ă���ҁB ���̂̉��̕��ɔM���L���ē��ɂ����Ă������ꂵ�݁A�������āA�������L��A������ �����{�^�{�^�Əo�₷�������͐Q���������A���ꂷ��ҁB ����F�Ԃ��������A���ɉ������������͓�ւ��o�āA��ɔ����ۂ� �L������������A�̂悤�ȑ����o�Ă߂������Ȃ�A�H���ɂ͖���������ꂸ�A�M�����H���D�݁A�`�̉��ӂ�ɓ���������������ҁB �a��̏d���҂͖���ɂ������o�����A�Ⴊ�[�����A���킲�Ƃ����������ł��Ȃ�����b���A�葫���d���邭�͂����炸�A���t���� ���͂Ȃ��A��ɂ��������͂��������Ȃ��ҁB ��������p���ア�҂ŁA��������e�ꖞ�≝�����M���������Ȃ��A���������� ��r�I���ŁA��J���₷���A�H�~���܂薳���A�̗́E�C�͂Ƃ������Ă���ҁB���{���̖ڕW�Ƃ��ā@�@�葫���Ӂ@�A�ꌾ�y���@ �B�ᐨ���́@�C��������������@�D�H�������@�E�M���D�ށ@�F�`�������@�G���U�喳 ���������B �����Čӓ��ŋ��̎҂ɗp����B ���g�̂�����ƐQ���������ƌ����҂ɂ͖{���������B ������������⒆�v�C�����̊Ö��܂��A����Ђǂ��Ȃ����҂ɂ͕�C���������ǂ��B ���H��������Ƒ̂����邭�A�������Ȃ�ҁA�{����p����ڕW�̈�ł���B |
|
| �s�����E�t �⒆�v�C����䉖�䨗� (�ق��イ�������Ƃ������Ⴍ�₭�Ԃ���傤) |
�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���⒆�v�C���Ť���ɁE����������҂������B | ||
| �⒆�v�C�����ܖ��q����~ �������v�C���ɋL�� |
||||
| ��x�U(�ق͂�����) �����P�U(�����傤����) �ɋL�� |
||||
| ��x���P�� (�ق͂������傤�Ƃ�) �����P�U(�����傤����) �ɋL�� |
||||
| �s�����E�t �������q�אh�� (�܂����Ԃ���������Ƃ�) �����אh���q�� (�܂�����������Ԃ��Ƃ�) ������ (�܂Ԃ���) |
���� ���q �אh | �@
�����j�G�[���nj�Q ���C�ǎx�b�� ���b���@�����` ���C���t���G���U �����ǐ_�o������ �i�N�C���P����j �����Ɂ@���Γ��� �������@����A�� �����̔�J�@���ߒ� �������_�o������ ���S�g�̌��ӊ� ���x���@����������� ����A�ǁ@����ʑ��� ���������͓�� ���x���@���~�^�� ���C�ǎx�� ���t������ ���߃��E�}�` ���_�o�Ɂ@������ ���A�����M�[���@�� ��������}���@�� �����Ɂ@�������� ���₦�� ������@���������@�o�� �����C�́@���n���� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����M���Ĉ����������A���͈��������œ��ɂ��A�g�u�A���͚b���A���͕@���l�܂�ҁB �����ז��͂��̑��Ŕ��M���āA���M�����Ă��Ă�������A�g�̉��ƂȂ��͖����A�C�͖����A�����Q�����ƌ����ҁB �����X�w���Ɉ���������A�������̂悤��ႂ��o�āA�A�͂قړ����F�ŔA�ʑ����A�����͕������A���o�ɂ����҂�����B ���a�C�������A�����Ɏӂ��Ĕ������������ꍇ�ɋN����B �����M�������Ă����Ȃǂ��₷�̂������B�����₦��Ɠ��ɂ���Ƒi����B ���K�����͒���ōׂ��͂��Ȃ��B ������ׂ̎����߁A�\�ɂ���M�Ɛ����ɂ����U�����鏈���ł���B |
|
| �s�����E�t ����ָ(�����{��)�Ó� (�܂��傤�������Ƃ�) (�܂��傤�悭����Ƃ�) �����ǐmָ䏊Ñ��� (�܂������傤�ɂ�悭�������Ƃ�) ����䏊Ó� (�܂��傤������Ƃ�) |
���� �ǐm �Ñ� ָ(�����{��)䏐m |
�������i��ᝋہj �����E�}�` ���b�� ���D�P�t �����` ���C���t���G���U ���Q�Ⴂ ������ ���z���r�nj�Q ������ �������_�o�� �������� ���C�{ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�������₦�鏊�ɋ�����A�g�̂��₦��悤�Ȏd����������A�������Ċ����R�������̎d���������肵���ׁA �g�̒����u�ɂ��ē��ɂP�T���`�P�U�����ɂȂ�ƈ�i�ƂЂǂ��A�����ĔM���o�Ă���i�g�̂��M���ۂ�������j�҂������B | |
| �� | �s�����E�t �����v�C�� (�݂��������Ƃ�) �⒆�v�C�����ܖ��q����~ (�ق��イ�������Ƃ��� �@�@���݂�������ǂ�) |
�l�Q ���Q ���A �� �Č� ���� �Ñ� ���� ���I �垥 �ܖ��q ����~ �i�����I�j �i���垥�j |
������ ���C�ǎx�� ���P�u ���x���j �� �� �� �� �� ��etc�E�E�E�E�E�E�E�E |
���⒆�v�C���̏ŊP�u�������҂������B ���ܖ��q���E�E�E�E�E�E�E�Â� �@����~���E�E�E�E�E�E�E�Â� |
| �� | ||||
| �� | ||||
| �� | ||||
| �� | ||||
| �� | ||||
| �� | �s�����E�t �}�̎U (�悭����) |
���A �췭� (�����{�|) ���Q 䨗� �Č� �Ñ� �ޓ��b |
����ԔF�m��Q(�F�m��) ���z���@������ �����M�@�����M ���q�f႟��@������ ���H�~�s�U�@����� �����c���̈����� ���_�o���� ������a�@������ ���߂܂��@�����s���� ���鋃���@���q�f ���q�X�e���[ ���������� ���_�o�ߕq�@��ᒕa ���_�o����@���]�o�� �����g�s�� ���X�N����Q ���s���ǁ@������� ���`�b�N�ǁ@���_�o�� �������_�o������ ���m�C���[�[ ���]���@���]�o������ ���]�����@���]��ᇏǏ� ���������� ���p�[�L���\���a ��ᒕa�@���� �����̓��ǁ@����� ���p�j�b�N��Q ���A�~�@�����͌��� �����j�@�����g�s�� ���l���ގ�� ���_�o������ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
����������g�̂��キ�A���F�����ꂸ�A�_�o����ᒂ����Ԃ�A�h���Ǐ������A�悭�����A�悭�{�����肵�A
�����s���̔M���o���A�����͔��M����x���z�����N�����ҁB ��������Ԃ�₷���A�{����ۂ��C���C�����A�葫�╠���̋ؓ����˂����������A�݂��������d���҂ŁA���ɁE�߂܂��� �N�����ҁB �� �������ْ̋�������҂������B |
| �s�����E�t �}�̎U���甼�� (�悭������҂͂�) |
���A �췭� (�����{�|) ���Q 䨗� �Č� �Ñ� �ޓ��b �� ���� |
����ԔF�m��Q(�F�m��) ���z���@������ �����M�@�����M ���q�f႟��@������ ���H�~�s�U�@����� �����c���̈����� ���_�o����@������a �����Ɂ@���߂܂� �����s����@���鋃�� ���q�X�e���[ ���q�f�@���������� ���_�o�ߕq�@��ᒕa ���_�o����@���]�o�� �����g�s�� ���X�N����Q ���s���ǁ@������� ���`�b�N�ǁ@���_�o�� �������_�o������ ���m�C���[�[ ���]�o������ ���]���@���]���� ���]��ᇏǏ� ���������� ���p�[�L���\���a ��ᒕa�@���� �����̓��� ���p�j�b�N��Q ���A�~�@�����͌��� �����g�s�� ���l���ގ�� �����j�@����� ���_�o������ ���ݓ��␅�@���q�f ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���}�̎U�̏ŁA���`�T����S�����ɂ����đ傫�������ӉZ�̗l�Ȍ`���������̂��G��哮���̓�����������
���i���A�����͑S�̂ɓ�炩���זv���A�H�~�������ҁB �������ْ̋�������҂������B ����E���Ă͋��ɑ�����ႂ̓������L��B ���Ă͈݂���t���~���A����B�����ɂ��ċC����B �Q�������킹��ΈC�̕s�a�ɂ��N����ݕ��̖c�����A���S�A�q�f������A�̂̔M���܂��B |
|
| �� | ||||
| �� | ������(��)���l�Q���ɋL�� | |||
| �s�����E�t �Z�N�q�� (������Ƃ�) ���B��႓� (����҂�����Ƃ�) �ĉv�C�� (���������Ƃ�) (���������Ƃ�) �Z���� (�낭�݂Ƃ�) |
�l�Q ���Q 䨗� ���� �� �垥 �Ñ� ���I |
�������݉� ���݉����� ���݃A�g�j�[�� ������������ ���݊� ���ݒ�� �������s�Ǐ� �����ƒ��ŏ� ���H�~�s�U ������ ���q�f �����j ���_�o����� �������� ���]�쌌 �������� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���ݒ�����ȑ̎��ŐS�����������A���H���������A�H�~�s�U�ŁA���₷���A�n���̌X��������A�₦���̎ҁB ���S�̓I�ɋ���̎��̎҂�ڕW�ɂ���B ���H�����Ƃ�Ɣ��A�g�̂����邭�Ȃ�A�������Ȃ�ҁB |
|
| �s�����E�t ���_�b�̓� (��イ���Ⴉ��Ƃ�) <1>��ѓ��̗��_���̓� <2>�L���\�Z��� �@�@�@�@�@�@���_�b�̓� |
���P�� ���A �췭� (�����{�|) 䉖� �n�� ���A ����� (�����{��) ���� �A�� �ؒ� �h�� ���b ���_ �R���q ���חt �ԑO�q (���@�R�A��) (���@ָ(�����{��)䏐m) (���@�Ñ�) ���Q�� ���A �n�� ����� (�����{��) ���b �ؒ� �Ñ� ���_ �R���q �ԑO�q |
���щ� ���r�A�� �������̉��� ���x�[�`�F�b�g�a ���A���� ���N���� ���o���g�����B�� ���щ� �������� ���ҕa ���~�� �����p ���A���y�� ���T�� ���A����� ���J���W�_�� ���S�g���R���i�X�� ���̍d�Ϗ� ������ �������_�o������ ���������� ���~����p ���q�{������ ���畆�� ���@���] ���r�A�� ���A�����] ���r�A�� ���� ������ ������ ���q�{�؎� ���Ίۉ� ���p�A ���A���@��ꋌa�����p�߉� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���P�� ����r�I�̗͂�����A���ɂ��͂�����A�������̋ؓ����ْ����ď[�����Ă���ҁB ���畆�����A��⑫�̗������C�ď����Ă���ҁB ���̌o�̎��Ǝ��M�������B ���̗͂������Ă�����A�₦�ǂ�n���̎҂ɂ͗p���Ȃ��B ���щ���r�A�ɂɗ��_���̓��i�������ْ����j���������A�����ہi�������ْ���j�Ō�����������B ����ɉ��ł̏������ɗp����B �����M���� ���Q�� ����r�I�̗͂�����A���ɂ��͂�����A�������̋ؓ����ْ����ď[�����Ă���ҁB ���������A���̑���̏����ǂŁA�[���E��E�u�ɂ��Ă���ҁB�}�������͈��}���̉��ǂ�����A���̎ҁB ���̌o�̎��Ǝ��M�������B �������̗������̊O���ɉ����āA���L�ْ̋��Ɖߕq�т��F�߂��A�����ɏ[������̏�Ԃ������B �����M���� |
|
| �s�����E�t ��ÛI���h�Đm�� (��傤���傤�݂��ɂ�Ƃ�) |
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� etc�E�E�E�E�E�E�E |
���M���Ȃ��A�C�����債�Ĉ����Ȃ����A�P������Ə��ւ��R��č���ҁB | ||
| �s�����E�t ��j�Q�Ó� (��傤�����������Ƃ�) 䨗�j�}���Q�Ñ��� (�Ԃ���傤�������тႭ��������Ƃ�) |
䨗� �j�} ���Q �Ñ� |
�������i��ᝋہj �����j�G�[���nj�Q ����῁i�߂܂��j ���s���ǁ@������ ���^�������� ���ݓ��␅�@���A������ ������@���S�����i�� ���S���ٖ��� ���S�s�S�@���S���b�� ���S���_�o�ǁ@���b�� ���_�o���� ���m�C���[�[ ���q�X�e���[ ������� ���s���_�o�� ���݉����� �������݉� ���A�k�t ���ዅ�Uṏ� ������@�������� ���p�������� ���o�Z�h�[���a �������������_�o�� ���N���������� ���_�o�z���͏� �������_�o������ ���Γ��Ɂ@������ ����蕨���� ���ጌ���ǁ@�������ߎ� ���������ǁ@�������ُ� �������C�ǎx�� ���ᒁ@���~�^�� ����@���̂ǂٕ̈��� ���n�� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���݂������̂����肪�����ς��ɋl�܂�������������A�������ɓ˂��グ���銴�������A�����ė����オ�鎞�̓O���O���Ƃ��ċC�������Ȃ�A�����͗����Ă���ƃt���t���Ɛg�̂��h��A���ւ��߂��A���ꂪ����ҁB���݂��キ�����Ĉݕ��ɐ���������A�C�̏�Ղɂ��߂܂�������҂ɗp����B���n���Ǐ�̋����҂ɂ͎l�����ƍ��킹�A�A����Ƃ��ĕ��p���܂��B | |
| ��j�Q�Ó����l������ �A����ɋL�� |
||||
| �s�����E�t ��j���Ó� (��傤�����݂���Ƃ�) ��j�ܖ��Ñ��� (��傤�������݂����Ƃ�) 䨗�j�}�ܖ��Ñ��� (�Ԃ���傤���������݂����Ƃ�) �j��ܖ��Ñ��� (�����ꂢ���݂����Ƃ�) |
䨗� �j�} �Ñ� �ܖ��q |
�����j�G�[���nj�Q ���C�ǎx�� ���P ���b�� ���葫�̗₦ ���葫�̂��т� ���̂ڂ� �����`���͓��d �����֓� ��� �������� ������ ���_�o�� ���m�C���[�[ �����̓��� �����o�������� ������ ���q�{�o�� �����g�s�� �������� ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
����⑫���₦�A��������A�ɂ����ē˂��グ�Ă���悤�Ȋ��������A�葫�����т�A�����͊�ʖ��͊ዅ���Ԃ�
�Ȃ�i�̂ڂ���ΏƂ�j�ҁB ���ւ̏o�������҂⓪�ɉ����킳�����悤�Ƀ{�[�b�Ƃ���җL��B�P�͑����Ɋւ�炸�o��ґ����B �������� ���l�Ƙb������Ɗ�ʂ��ΏƂ�����A�̂ڂ��₷���ҁB |
|
| �� | ||||
| �s�����E�t �A��� (��ア��) ����� (��ア��) ��j�Q�Ó����l���� (��傤�����������Ƃ� �@�@�@�@�@���������Ƃ�) |
���A 䉖� �췭� (�����{�|) �n�� ���Q �j�} 䨗� �Ñ� |
���n���� ���X�N����Q ���₦�� ���̂ڂ��� �������� ���s���� ������ ��῝�(�߂܂�) �����M ���S���ٖ��� ���\��w������(�b����) ������ ���֔� ����J�� �����ӊ� ����ʕ��� ������ ���s���� ������ ���މ��a ���܂̕ό` ���ꎤ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
���o���A�����͕n���ɂ�铮���A����A���ɁA�߂܂��A����A��ʕ���Ȃǂɗp����B ���ݒ�����̎҂ɂ͗p���Ȃ��B |
|
| �Z�������Z�N�q���ɋL�� | ||||
| �Z���� (�낭�݂���) |
||||
| �s�����E�t �Z���ۍ����A��œ� (�낭�݂���������ǂ��Ƃ�) |
�n�� �R�� �� 䨗� �I�� ����� (�����{��) �R��� ���O�� �R���q ���A ���� |
�����j�G�[���nj�Q ���_�o���� �����A�a ������ �������^�R �������_�o���� ���s���� ���������� �������d���� ���b��B�@�\���i�� ���r�A���� ���p�A ������� �������畆�a ���X�N����Q �������� ������ ����J�� ���畆�a �����̉ΏƂ� ������ ��etc�E�E�E�E�E�E�E |
�����₷���A�A�ʌ��������͑��A�ŁA���ɂ̂ǂ���������~������A�舽���͑����ΏƂ�A
�钆�ɖڂ��o�߂₷���ҁB ���ݒ�����̎҂ɂ͗p���Ȃ��B |
|
| �� |