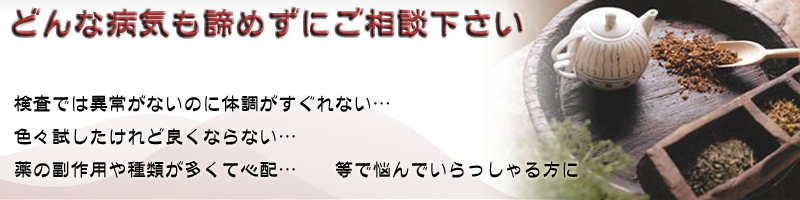
漢 方 相 談 無 料 メ ー ル と 問 診 票 ・ ど ん な 病 気 も 諦 め ず ご 相 談 下 さ い ! 漢方薬 専 門 店
佐 々 木 漢 方 薬 店 ホ ー ム ペ ー ジ
山 口 県 岩 国 市 元 町 2 丁 目 1 番 1 8 号 佐々木ビル 1階 TEL・FAX ( 0 8 2 7 ) 2 3 - 0 8 7 3
山 口 県 岩 国 市 元 町 2 丁 目 1 番 1 8 号 佐々木ビル 1階 TEL・FAX ( 0 8 2 7 ) 2 3 - 0 8 7 3
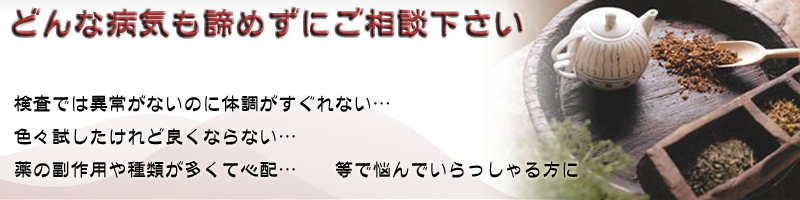
更新日 平成年月日〜令和5年6月1日
生薬大辞典
※ できるだけ薬草などを煎じる時は土瓶又はそれに類する物をお使い下さい。
そうすることにより火力の安定と、より効果の高い成分が出ます。
※ 煎じ終えたら熱いうちにカスを取り去ってください。
冷めてしまうと良い成分が生薬に戻ってしまうので。
※ 同類病名、又は同じような病名・病症がございますがご了承ください。
※ まだ完成いたしておりません、ご迷惑おかけいたします。
| あ | 植物名{アカメガシワ} 《別名》 {ゴサイバ} {アカガシワ} {サイモリバ} {アカベアメコサイバ} 《生薬名》 赤芽柏{あかめがしわ} 将軍木皮{しょうぐんぼくひ} 野梧桐{やごどう} 《気味》 苦 |
ト ウ ダ イ グ サ 科 |
樹皮 茎 葉 |
●胃潰瘍 ●十二指腸潰瘍 ●胃酸過多症 ●胃腸薬 ●胆石症 ●整腸剤 ●あせも ●皮膚病 ●おでき ●ニキビ ●吹き出物 ●胃癌 ●痔疾患 ●リウマチ ●etc・・・・・・・ |
◆樹皮、茎、葉を浴剤とし、あせもや皮膚病、リウマチや神経痛に効果があります。 ◆民間薬では、赤い新芽と新葉、赤い葉柄の干したものの方が胃癌や胃潰瘍などに効果があるとされています。 ◆痔や腫れ物には、乾燥させた樹皮の煎液を服用し、同時に乾燥葉3〜5gと、水200ccと共に弱火で半量まで煎じ、煎じあがった 液で患部を洗う。内服と外用を併用する事により、とても早く効果がみられます。 ◆胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃酸過多症、胆石症、腫れ物などには煎剤又は原末を1日3回1日量9〜15gを毎食後に服用します。 ◆アカメガシワの葉100gと、アケビの葉又はアケビのつる20gと、スイカズラの葉20gを煎じて服すると、腫れ物や癰に 効果が高いとされています。 ※注意!アレルギー症状を起こす場合があります。 |
| 植物名{アカヤジオウ} 《生薬名》 地黄(じおう)=根 地髄(ちずい)=根 <1> 乾地黄(かんじおう)=乾燥根 <乾生地(かんせいじ・かんしょうじ) =乾燥根 <2> 熟地黄(じゅくじおう)=酒蒸根 熟地(じゅくじ)=酒蒸根 <3> 生地黄(せいじおう・しょうじおう) =生根 鮮地黄(せんじおう)=生根 生地(せいじ)=生根 《気味》 甘寒 |
ゴマノハグサ科 | 根 <1>乾燥根 <2>酒蒸根 <3>生根 |
<1> ●補血作用 ●強壮作用 ●強精作用 ●解熱作用 ●糖尿病 ●吐血 ●月経不順 ●陰虚証 ●発熱 ●etc・・・・・・・ <2> ●補血作用 ●強壮作用 ●強精作用 ●解熱作用 ●糖尿病 ●吐血 ●月経不順 ●陰虚証 ●発熱 ●etc・・・・・・・ <3> ●止血作用 ●etc・・・・・・・ |
◆傷中、血痺を逐い、骨髄を充填し、肌肉を長ずる。煎薬として用いれば寒熱積聚を除き、痺を除き、
折跌絶筋を治療する。久しく服すれば身体を軽くし、老衰しない。特に生の地黄が良い。 ◆男子の五労、七傷、婦人の傷中、胞漏下血に効果あり、悪血、溺血を破り、大腸、小腸を利し、胃中の宿食、飽力の断絶を去り、 五臓内傷の不足を補し、血脈を通じ、気力を益し、耳目を利す。 ◆生地黄の性は、大寒で、婦人の傷中、血が止まらない時、及び産後血が上り、心が薄く悶絶し、傷身で胎動による下血、 胎が落ちないもの、墮墜?折の為の?血、留血、血衂、吐血に搗いて飲む。 ※熟地黄の気味は甘微温とされるそうです。 ※生地黄(乾地黄)は血を生ずるが、胃気の弱い者が服用すれば、食物の消化を妨げ、熟地黄は血を補するが痰飲の多い者が服用すれば 隔に泥む。生地黄(乾地黄)はお酒で炒れば、胃を妨げず、熟地黄は姜汁で炒れば隔に泥まない。 ※男子の陰虚には熟地黄を用い、婦人の血熱には生地黄(乾地黄)を用いる。 |
|
| 阿膠(あきょう)→ロバに記載 | |||||
| 植物名{アケビ} 《生薬名》 木通(もくつう) 通草(つうそう) 木通根(もくつうこん) 預知子(よちし) 通草子(つうそうし) 八月札(はちがつさつ) 《気味》 辛平 |
アケビ科 | 木質茎 果実 根 種子 葉 つる |
●腎臓炎 ●尿道炎 ●膀胱炎 (排尿痛・血尿・濁尿) ●消炎性利尿薬 ●鎮痛薬 ●腫れ物 ●排膿作用 ●睾丸腫痛 ●通経薬(閉経症) ●抗菌作用 ●浮腫 ●水腫 ●のどの痛み ●イライラ感 ●更年期障害 ●頻尿 ●排尿困難 ●乳汁不足 ●腰痛 ●月経痛(生理痛) ●尿管結石症 ●活血薬(貧血症) ●不眠症 ●頭痛 ●補腎補精薬 ●関節リウマチ ●月経不順(生理不順) ●冷え症 ●神経痛 ●子宮内膜症 ●脚気口内炎 ●淋病 ●胃熱 ●瘰癧 ●胸脇疼痛 ●慢性・急性肝炎 ●etc・・・・・・・ |
◆煎じた液を出来物の洗浄に外用薬として利用出来ます。 ◆木通を1日量3〜20g とお水約600ccと共に土瓶に入れ、半量になるまで弱火で煎じ、三回に分けて食前又は食間に温服 する。 ◆煎じて服用すれば消炎、利尿、鎮痛、抗菌作用があり、浮腫、尿閉、尿利減少、尿道炎、膀胱炎、妊娠腎、月経不順、血の道、 疝気、腹痛、肝臓炎、貧血性頭痛などに効果があります。 ◆ほぼ成熟した果実を採り乾燥した物を八月札と言い、鎮痛、除煩、利尿、治肝等の薬として血尿、濁尿、腰痛、月経痛、 尿管結石等に用いられます。 ◆根は去風、利尿、活血、補腎補精薬として関節リウマチ、尿不利、腰背痛等に用いられます。 |
|
| 植物名{アサガオ} 《生薬名》 牽牛子(牽牛子)=種子 《気味》 |
ヒルガオ科 | 種子 | ●利尿作用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●便秘 ●etc・・・・・・・ |
◆ | |
| 朝貌(あさがお)→ムクゲに記載 | |||||
| 植物名{アシタバ} 《気味》 |
セ リ 科 |
●便秘 ●高血圧症 ●皮膚病 ●虫さされ ●止痒作用 ●催乳作用 ●血管強化作用 ●血行促進作用 ●利尿作用 ●健胃整腸作用 ●etc・・・・・・・ |
◆ | ||
| 植物名{アズキ} 《生薬名》 赤小豆(せきしょうず)=種子 |
マ メ 科 |
種子 | ●ネフローゼ ●etc・・・・・・・ |
◆浮腫の者に赤小豆を炊いて食べさせると尿量増えてむくみが良くなる。 | |
| 植物名{アメリカニンジン} 西洋人参(せいようにんじん)= ()= ()= |
ウコギ科 | 根 |
・・・・・・・作成中・・・・・・・ | ||
| 植物名{杏(アンズ)} 《生薬名》 杏仁(きょうにん)=種子 《気味》 甘温 |
バ ラ 科 |
種子 | ●鎮咳去痰薬 ●咳 ●喘息 ●呼吸困難 ●息切れ ●咽喉痛 ●口渇 ●便秘 ●浮腫 ●消化不良 ●歯痛 ●犬傷 (犬に噛まれた時の傷) ●疣(いぼ) ●etc・・・・・・・ |
◆杏仁は、風寒・風熱・風湿・暑気などの外因により発生した咳で、口渇と咽痛があって口・鼻・皮膚などの乾燥と便秘を伴う様な症状に用います。 杏仁 1日量 3〜5gを煎じて服用。 ◆杏仁、咳逆上気・雷鳴・喉痺下気・産乳・・金瘡・寒心・奔豚を主る。 ◆咳嗽・浮腫・消化不良に、杏仁をすり潰したものや煎じた液を服用すると良い。 ◆虫歯に杏仁をすり潰したものをつめ、歯痛には杏仁を黒焼きにしたものを噛むと良い。(口中に入れた杏仁は後に吐き出す。) ◆顔や身体に出来たイボに、すり潰した杏仁を塗ると良い。 ◆犬に噛まれた時の傷には、すり潰した杏仁や汁を塗ると良い。 ◆疲労回復・鎮咳去痰薬としてアンズ酒を1日2回、1回量30ml 食間に服用します。アンズ酒の作り方は、果実 500gを採り水洗いし、 水をきった後に砂糖300gと共にホワイトリカー 1.8Lに漬けます。約3ヶ月で熟成します。 ◆種子から杏仁水が作られ、鎮咳去痰薬として用いられます。 ※杏仁を多量に服用すると、頭がふらつく・嘔吐・痙攣・意識障害・呼吸困難などの中毒症状が起こる事があるので、 注意しなければなりません。 ※杏仁の修治の仕方=杏仁を数分間ぬるま湯に浸し、種子が軟らかくなったら杏仁の尖(とが)った部分をつまんで取り去り、膨らんだ 部分を押して皮を剥がし、炒って乾燥させる。(注意 杏仁に含まれる脂肪油が酸化されやすくなるので使用直前に作業しましょう。) 渋みが出て飲みにくくなるから、皮を去る。 のぼせ等が出やすくなるから、尖った部分を取り除く。 |
|
| い | 苡米(いべい)→ハトムギに記載 | ||||
| 茵陳蒿(いんちんこう) →カワラヨモギに記載 |
|||||
| 印度犀(いんどさい)→サイに記載 | |||||
| う | ウサギウマ→ロバに記載 | ||||
| 動物名{牛又は水牛} 《生薬名》 牛黄(ごおう)=胆石 丑玄(ちゅうげん)=胆石 丑宝(ちゅうほう)=胆石 土精(どせい)=胆石 牛角(ぎゅうかく)=角 《気味》 牛黄=苦平 |
ウ シ 科 |
胆嚢結石 胆管結石 角 |
牛黄 ●強心作用 ●解熱作用 ●鎮静作用 ●鎮痙作用 ●免疫増強作用 ●抗炎症作用●利胆作用 ●抗ウイルス作用 ●血赤血球新生促進作用 ●肝臓保護作用 ●血圧降下作用 ●末梢神経障害改善作用 ●抗酸化作用 ●血栓溶解作用 ●熱病による意識障害 ●言語障害(構音障害) ●熱性痙攣 ●脳卒中 ●脳出血 ●脳溢血 ●脳梗塞 ●脳血栓 ●脳塞栓 ●血色不良 ●くも膜下出血 ●頭蓋内出血 ●口内炎 ●夏バテ ●動悸 ●息切れ ●めまい ●のぼせ ●不眠症 ●肩こり ●肉体疲労 ●冷え症 ●身体倦怠感 ●手足のしびれ ●更年期障害 ●のどの痛みや腫れ ●二日酔 ●貧血症 ●立ちくらみ ●腹痛 ●消化不良 ●歯槽膿漏 ●歯痛と腫れ ●出来物 ●腫れ物 ●悪性腫瘍 ●インフルエンザ ●胆嚢結石 ●腎結石 ●高血圧 ●低血圧 ●アレルギー性皮膚炎 ●アトピー性皮膚炎 ●蕁麻疹 ●難聴 ●眼底出血 ●躁・鬱病 ●リウマチ ●疳の虫 ●ヒステリー ●慢性・急性肝炎 ●浮腫膠原病 ●肝硬変 ●脳梗塞 ●動脈硬化 ●心筋梗塞 ●不整脈 ●咳 ●喘息 ●頭痛 ●悪酔 ●肺炎 ●耳鳴り ●下痢 ●口内炎 ●不安症 ●心配性 ●微熱 ●発熱 ●疲労感 ●消化不良 ●腹部膨満感 ●首筋の凝り ●血行障害 ●etc・・・・・・・ 牛角 ●止血作用●血便 ●下痢● ●etc・・・・・・・ |
◆牛黄は、急に何かに驚き突然意識を失い倒れて、昏睡状態又は意識不明になった者や、高熱が続き痙攣を起こし、
或いは熱の為にうわごとを言ったり精神に異常をきたし歩き回ったりする者を治す。 ◆牛黄は、奥の方(五臓六腑)のどこかに熱が滞り、それにより病気を発症する者を治す。(心臓の事もあり、肝臓のこともあり。) ◆牛黄は、昔から長期服用すれば全身の新陳代謝を活発にし、寿命をのばし、物忘れをしなくなるとされています。 ◆牛黄は、清熱瀉火、涼血、解毒、開竅、定驚。…作成中… ※牛角は犀角の代用品として使われる事がある。 |
|
| 植物名{ウラジロガシ} 《生薬名》 裏白樫(うらじろがし) 《気味》 苦 |
ブ ナ 科 |
葉 | ●膀胱結石症 ●尿路結石症 ●胆石症 ●胆嚢疾患 ●腎石症 ●結石瀉下 ●etc・・・・・・・ |
◆裏白樫葉乾燥刻み1日量50〜70gを水600ccと共に弱火で半分量になるまで煎じる。
1日数回に分けて服用する。 ◆腎石や胆石には裏白樫と連銭草1日量20gと共に煎じて服用すると、より効果的です。 |
|
| え | 植物名{エビスグサ} 《生薬名》 決明子(けつめいし) 草決明(そうけつめい) 馬蹄決明(ばていけつめい) 仮緑豆(かりょくず) 《気味》 |
マ メ 科 |
種子 | ●視力低下 ●眼病 ●便秘症 ●慢性胃腸病 ●消化不良 ●胃拡張 ●胃下垂 ●胃酸過多症 ●胃アトニー ●十二指腸潰瘍 ●胃潰瘍 ●口内炎 ●黄疸 ●蕁麻疹 ●腎臓病 ●腎盂炎 ●脚気 ●糖尿病 ●膀胱カタル ●婦人病 ●肝臓病 ●神経痛 ●下痢 ●二日酔い ●慢性肝炎 ●動脈硬化症 ●利尿強壮剤 ●高血圧 ●etc・・・・・・・ |
◆高血圧予防には、ゲンノショウコ10g、ドクダミ10g、決明子(少し炮じた物)5gを煎じて、お茶代わりに
服用すると良い。 ◆胃・十二指腸潰瘍や下痢又は下痢気味の時には、ゲンノショウコと決明子を一緒に煎じて服用します。 下痢の場合、ゲンノショウコの量は病の程度により、その都度加減しましょう。 ◆便通を整え、便通を良くし、目の周りの充血を去る事により、視力が回復する。 ◆慢性胃腸炎で、常に便秘がちの場合、決明子20〜25g、お水700㏄と共に半量まで煎じて1日回に分けて服用する。 ◆腎臓を強くし、肝臓の働きを良くする作用があるので、慢性の肝炎や黄疸に、利尿強壮剤としてお茶として服用します。 また動脈硬化症などの高血圧の場合も同じように服用します。 |
| オオツヅラフジ→ツヅラフジに記載 | |||||
| 黄柏(おうばく)→キハダに記載 | |||||
| 桜皮(おうひ)→桜に記載 | |||||
| 植物名{ドウカン或いはフシグロ} 《生薬名》 王不留行(おうふるぎょう)=全草 《気味》 苦平 |
●金瘡●切り傷●刀傷 ●止血作用●鎮痛作用 ●ひび●外傷●術後 ●催乳●通経●婦人難産 ●月経不順●乳癰 ●乳汁稀少●癰腫 ●疔毒●脳出血 |
◆刀傷・切り傷・外傷等を治すもので、血を止めて痛みを逐い去り、刺さった物を体外に排出させ、風気を主力とした風・寒・
湿の気に中てられ、血や気の流れが滞り、その為に痛んだり、痺れたりする風痺の病の元や、内臓や寒気が隠っているのを取り除き、
継続して服すれば、身体軽くなり、老化を防ぎ、長生きが出来る。 ◆ドウカン草(ナデシコ科)の王不留行1日量5〜10gを煎じて服用 ※妊婦は服用厳禁。 ◆外傷や |
|||
| 植物名{オオバコ} 《別名》 オバコ ギャーロッパ カエロッパ ゲェーロッパ マルコバ オンバコ 《生薬名》 車前草(しゃぜんそう)=全草 車前葉(しゃぜんよう)=全草 車前子(しゃぜんし)=種子 車前実(しゃぜんじつ)=種子 當道(とうどう)=種子 《気味》 甘寒 |
オ オ バ コ 科 |
全草 種子 |
●利尿作用 ●去痰作用 ●明目作用 ●消炎作用 ●止血作用 ●解熱作用 ●清熱作用 ●強壮作用 ●鎮咳去痰作用 ●慢性気管支炎 ●膀胱炎 ●排尿障害 ●小便不利 ●浮腫 ●水腫 ●膀胱炎 ●眼の充血 ●下痢 ●etc・・・・・・・ |
◆車前草は咳止め・利尿・下痢止め・止血・強壮に良く、1日量10〜15gとお水約300ccを半量になるまで
煎じ、3回に分けて服用する。お茶感覚で服用するも良し。*咳のひどい者には甘草 3g加えて煎用すると良い。 ◆咳止めに車前子を使う時は1日量 5〜10gを布又は和紙の袋に入れ、水300ccと共に半量まで煎じて服用する。 *車前子は煎じると粘液質が多いので、服用しにくい時は甘草を少量混ぜて煎じると良い。 ◆浮腫があり、小便の出にくい者は、新鮮なオオバコ葉を絞り、その絞り汁50mlと半量ほどの清酒と共に空腹時に服用する。 ◆腫れ物には、生の葉を火に炙って貼る。 |
|
| 動物名{オオヤモリ} 《生薬名》 蛤蠏(ごうかい) 蛤カイ(虫+介)(ごうかい) 仙蟾(せんせん) 大壁虎(だいへきこ) 《気味》 鹹平 |
ヤ モ リ 科 |
内臓除去物 尾 |
●気管支喘息 ●心臓喘息 ●肺結核 ●慢性咳嗽 ●神経衰弱 ●頻尿 ●老人の足膝萎弱 ●精力減退 ●ED ●インポテンツ etc・・・・・・・ |
◆肺気を補い、虚労咳嗽を治す。また腎を温め、腎虚・喘逆を治す。 ◆肺虚による咳嗽・腎虚による喘息に良い。 ◆腎の陽気が不足してきれいな血が弱り欠乏し、インポテンツや精力が減退した者に良い。 ※最強部位は尾 ※酒に浸けて服用すると効果的。 ※雄=蛤 雌=カイ(虫+介)一対で蛤カイ(虫+介)となる。 ※小児の食べすぎによる胃腸障害には頭の部分を粉にして服用させると効果があるといわれているそうです。 ※風寒、或いは実熱による喘息・咳嗽には禁忌。 |
|
| 植物名{オタネニンジン} 《生薬名》 朝鮮人参(ちょうせんにんじん) 朝鮮参(ちょうせんじん) 高麗人参(こうらいにんじん) 高麗参野山(こうらいじんやさん) 野山参(やさんじん) 養参(ようじん) 吉林参(きつりんじん) 遼東参(りょうとうじん) 白参(はくじん) 紅参(こうじん) 水參(すいじん) 白糖参(はくとうじん) ※生産地により沢山の名がある 《気味》 |
●強心 ●健胃補精 ●鎮静薬 ●食欲不振 ●消化不良 ●下痢 ●嘔吐 ●衰弱改善 ●息切れ ●倦怠感 ●喘息 ●咳 ●不眠症 ●夢幻 ●動悸 ●インポテンツ ●頻尿 ●血液流体欠乏症 ●高血圧症 ●肝疾患 ●糖尿病 ●貧血 ●癌 ●夢精 ●夜尿症 ●糖尿病 ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆五臓を補い、精神を安んじ、魂魄(こんぱく)を定め、驚悸(きょうき)を止め、邪気を除き、目を明らかにし、心を開、
智を益す ◆腸胃中冷、心腹鼓痛、胸脇逆満、霍乱吐逆を療し、中を調え、精渇を止め、血脈を通じ、堅積を破り、人をして忘れざらしむ。 ※紅参=皮ごと蒸して乾燥させたもの。 蒸しているため消化吸収に優れている。 ※白参=皮を剥ぎ取り乾燥させたもの。 周皮を剥いでいるためサポニン量に損失あり。 ※水参=生のままの状態。 ※白糖参=湯に浸して糖に漬けた後、乾燥させたもの。 ※1年根から6年根まで栽培年数によって等級が分けられ、6年根が最も上品とされている。 |
|||
| か | 海蛆(かいそ) →タツノオトシゴに記載 |
||||
| 海馬(かいま) →タツノオトシゴに記載 |
|||||
| 艾葉(がいよう)→ヨモギに記載 | |||||
| 貝名{カキ} 牡蠣(ぼれい)=殻 牡蠣(かき)=殻 《気味》 鹹平 |
イタボガキ科 | 殻 | ●寝汗 ●遺精 ●夢精 ●鎮静作用 ●etc・・・・・・・ |
◆傷寒、寒熱、温瘧で酒酒たるもの強恚、怒る気を主る。拘緩、鼠瘻、女子の帯下赤白を除く。
久しく服すれば骨節を強くし、邪鬼を殺し、年を延ばす。 ◆痰を化してやわらかくし、熱を清し、湿を除き、心、脾の気痛、痢下、赤白濁を止め、疝?積塊、?疾結核を消す。 |
|
| 植物名{カキ} 柿蒂(してい)=ヘタ 柿葉(しよう)=葉 柿餅(しべい)=干柿 柿霜(しそう) =柿餅表面の粉末状の滲出物 柿霜餅(しそうべい) =柿霜を加熱溶解した飴状物 柿渋(かきしぶ)=未熟果実 柿根(しこん)=根 《気味》 |
カキノキ科 | 果実 葉 根 蔕 |
●しゃっくり ●ゲップ ●鎮咳薬 ●止血薬 ●血小板減少症 ●吐血 ●喀血 ●血尿 ●痔瘻 ●下痢 ●のどの痛み ●咳 ●二日酔 ●止渇作用 ●慢性気管支炎 ●血圧降下作用 ●動脈硬化症 ●霜焼け ●かぶれ ●外傷による出血 ●胃中凝固作用 ●脳溢血 ●鼻血 ●夜尿症 ●膀胱炎 ●血便 ●眼底出血 ● ● ●・・・・・・・・・・ |
◆しゃっくり・ゲップには、柿蒂 1日5〜10gと丁子1gと生薑4gの三味を煎じて服用。 ◆鎮咳薬・内出血に対する止血薬・消化管の潰瘍による出血・肺結核による出血・子宮出血・血小板減少症には、柿葉を煎じて服用。 ◆吐血・喀血・血尿・痔瘻・下痢には、柿餅をそのまま食べさせる。虚弱者には、柿餅を煎じてその液を服用させる。 *柿餅の作り方* 柿の果実の皮をむき、昼は日に当て、夜は夜露に当て約1ヶ月乾燥させ、更に室内でむしろの中に約1ヶ月放置。その頃に表面に白い粉が出てくれば出来上がり。 ◆のどの痛み・風邪以外の咳に、柿霜餅をなめさせる。 *柿霜餅の作り方* 柿餅に付いた白い粉を加熱して溶かし飴状にする。 ◆鎮咳や止渇の作用があり慢性気管支炎などや二日酔に、完熟した柿を食べると良い。 ◆高血圧には、柿渋を盃一杯と大根おろしと共に服用。又は柿葉1日20gを煎じて1日3回に分けて温め服す。 *柿渋の作り方* 未熟な青い渋柿を採取し、ヘタを取り除き、突き砕いて容器に入れ、水を全体が浸かるまで加えてよく撹拌して蓋をする。3週間静置させ、 滓が分離してきたらその滓を取り除くと膠状の液則ち柿渋が出来る。 ◆止血薬として下血・吐血などに柿根が良い。 ◆・・・作成途中・・・ |
|
| 植物名{カキドオシ} 連銭草(れんせんそう) 金銭草(きんせんそう) 柿根通し(かきねどおし) カントリソウ 《気味》 |
シソ科 | 全草 | ●利尿 ●消炎 ●黄疸 ●胆道結石 ●腎臟結石 ●血糖降下 ●糖尿病 ●熱病 ●気管支炎 ●肺病 ●鎮咳 ●去痰 ●喘息 ●感冒 ●etc・・・・・・・ |
◆連銭草1日量10〜15gを水200ccと共に弱火で半量になるまで煎じ日に3回に分けて服用する。 ◆お酒に漬けたり、青汁として直接新鮮な葉を絞り、その汁を服用する。 ◆小児の疳症や虚弱体質には連銭草1日量5gを半量まで煎じ、3回に分けて服用する。 |
|
| 柿渋(かきしぶ) →カキに記載 |
|||||
| 柿根通し(かきねどうおし) →カキドオシに記載 |
|||||
| 植物名{ガジュツ} 莪朮(がじゅつ)=根茎 |
ショウガ科 | ●芳香健胃薬 ●・・・・・・・・・・ |
◆・・・作成途中・・・ | ||
| 植物名{カラスビシャク} 生薬名 半夏(ハンゲ)=塊茎(外皮除去) 《気味》 辛平 |
サトイモ科 | 球茎(外皮除去) | ●芳香健胃薬 ●咽中痛 ●咽喉腫痛 ●胸脹 ●頭眩 ●めまい ●不眠症 ●咳 ●心痛 ●鎮嘔作用 ●鎮吐作用 ●鎮咳作用 ●去痰作用 ●鎮静作用 ●つわり ●胃内停水 ●悪心嘔吐 ●胸騒ぎ ●動悸 ●頭痛 ●眼圧低下作用 ●急性緑内障 ●眼痛 ● ● ● ● ●・・・・・・・・・・ |
◆痰飲・嘔吐を主に治す。 ◆気を補い、水を去る。 ◆寒気におかされて生じた熱病の傷寒の病・悪寒と発熱を伴う寒熱の病・みぞおちが堅くなりつかえているいる者を治す。 また上衝した気や1カ所に留まった気を下す作用があるので、咽喉痛や腫れた時・めまい・胸脹の病・咳逆の病・腸鳴の病を治す。 更に異常に汗が出る者にも良い。 ◆生の塊茎をすり潰し、それを化膿して痛む部分に貼ると鎮痛としての作用がある。 皮膚炎には、生半夏をすりつぶした汁と酢を混ぜ合わせ外用すると良い。 ◆・・・・作成途中・・・・ ※半夏には弱い毒性が有り、生の半夏は少量でもえぐ味が有り、のどを刺激したり、舌が腫れたりするが、ミョウバンと甘草で処理した 法半夏・生姜とミョウバンを加えて煮る処理した姜半夏などには副作用はない。 |
|
| 植物名{カラタチ} 生薬名 枳殻(きこく) 枳実(きじつ) 《気味》 苦・寒 |
ミ カ ン 科 |
若未熟皮厚幼果 =枳実 成熟皮薄 =枳殻 |
●ハンセン病 ●癰腫 ●おでき ●理気薬 ●胸満 ●麻痺 ●腹満 ●腹痛 ●健胃薬 ●便秘 ●嘔吐 ●咽喉の炎症 ●めぼ ●麦粒腫 ●ものもらい ●etc・・・・・・・ |
◆ハンセン氏病の様な大風の病やそれらにより皮膚中に麻豆位のシコリができ、痒きを苦しむ者を治し、
悪寒と発熱を伴うような寒熱のもとや身体中に寒気や熱気が結集して堅くなった塊を破って除き、下痢を止め、肌肉の生長を促し、
五臓の機能をよくし、気を益し、身の動きを軽くする。 ◆胸満、痺、腹満、腹痛を治す。 ◆熱実病又は癰腫等で、熱を冷ましシコリを消し痛みを緩め腫れを去る。 ※橙・夏蜜柑・温州蜜柑等色々な種類が有るが、橙を上品とし、蜜柑を下品とする。 |
|
| 植物名{カワラヨモギ} 生薬名 茵陳蒿(いんちんこう) 綿茵陳(めんいんちん) 《気味》 苦平 |
キ ク 科 |
全草(花穂) | ●消炎性利胆薬 ●発熱(解熱作用) ●黄疸 ●利尿効果 ●延命効果 ●肝炎 ●血圧降下作用 ●抗菌作用 ●風湿病 ●寒熱病 ●熱結病 ●強壮剤 ●胆嚢炎 ●皮膚病 ●蕁麻疹 ●浮腫 ●去痰作用 ●胆石症 ●膀胱炎 ●尿毒症 ●高血圧 ●胃痙攣 ●口内炎 ●etc・・・・・・・ |
◆胆汁の分泌、排出を促進させる作用があります。消炎性の利胆薬として、尿量が減少し、口が渇き水分を欲しがり、
便秘がちで、発熱があり、黄疸の様な症状がある時に用いたり、鮮黄色の黄疸で、急性黄疸型肺炎や胆嚢炎などの急性炎症に用いられます。
茵陳蒿 1日 2〜20gを煎じ、日3回に分けて温め服します。 ◆皮膚の痒みには茵陳蒿の濃厚な煎液で洗うと良く効きます。 |
|
| 乾地黄(かんじおう) →アカヤジオウに記載 |
|||||
| 乾生地 (かんせいじ・かんしょうじ) →アカヤジオウに記載 |
|||||
| 乾地竜(かんじりゅう) →ミミズに記載 |
|||||
| 植物名{カンゾウ} 《別名》 イヌカンゾウ ナンキンカンゾウ ウラルカンゾウ 国老 《生薬名》 甘草(かんぞう)= 根及びストロン(走出茎) 炙甘草=根及びストロン(走出茎) 生甘草=根及び ストロン(走出茎) 甘草末= 根及びストロン(走出茎)去皮粉末 《気味》 甘平 |
マメ科 | 根及びストロン(走出茎) |
●筋肉痛 ●腹痛 ●咽喉痛 ●矯味薬 ●去痰薬 ●消化器性潰瘍 ●アジソン氏病 ●益気作用 ●解毒作用 ●消炎作用 ●緩和作用 ●etc・・・・・・・ |
◆乾燥させた甘草は、緩和薬・消炎薬・解毒薬として用います。 ◆生の甘草は、咽喉腫痛・消化器潰瘍・胃けいれん・食中毒などに用います。 ◆蜂蜜と共に焦がした炙甘草は、胃腸虚弱・食欲不振・腹痛・咳・発熱・下痢などの方に用います。 ※足の太陰・厥陰の経に入る。手足の十二経の何れにも入る。五臓六腑の寒熱邪気。筋骨を軽くし、 肌肉を長じ、気力を倍す。金瘡・ショウ(九+重)の毒、久しく服すれば身体を軽快にし、天年を延べる。 ※中を温め気を下す。煩満・短気・臓を傷めた咳嗽。渇を止め、経脈を通じ、血気を利し、あらゆる薬の解毒。 ※単味で大量に長期服用すると、電解質代謝に異常をきたすことが知られ、低カリウム血症・血圧上昇・脱力感・四肢痙攣・麻痺などが 起こる事があるので注意しなければなりません。 |
|
| 乾地黄(かんじおう) →アカヤジオウに記載 |
|||||
| き | 枳殻(きこく)→カラタチに記載 | ||||
| 枳実(きじつ)→カラタチに記載 | |||||
| 吉林参(きつりんじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 植物名{キハダ} 《生薬名》 黄柏(おうばく)=樹皮 黄檗(おうばく)=樹皮 檗木(ばくぼく)=樹皮 《気味》 苦寒 |
ミカン科 | 樹皮 | 苦味健胃整腸薬 下半身の炎症 充血 黄疸 下痢 etc・・・・・・・ |
◆ ※足の少陰の経に入り、足の太陰の引経の薬。五臓・腸・胃中の結熱・黄疸・腸痔。洩利を止める。 女子の漏下赤白・陰傷蝕瘡。 ※驚気が皮間に在って肌膚熱し、赤起するもの。目熱赤痛・口瘡を療ず、久しく服すれば神に通ず。 |
|
| 木波知春(きはちす) →ムクゲに記載 |
|||||
| 蚯蚓(きゅういん)→ミミズに記載 | |||||
| 杏仁(きょうにん)→杏に記載 | |||||
| 金銀花(きんぎんか) →スイカズラに記載 |
|||||
| 金銀藤(きんぎんとう) →スイカズラに記載 |
|||||
| 金銭草(きんせんそう) →カキドオシに記載 |
|||||
| 金不換(きんふかん) →サンシチニンジンに記載 |
|||||
| く | グァバ→バンジロウに記載 | ||||
| 植物名{クチナシ} 《生薬名》 山梔子(さんしし)=果実 《気味》 苦寒 |
アカネ科 | 果実 | ●消炎作用 ●止血作用 ●鎮静作用 ●不眠症 ●食道炎 ●胸痛 ●胃痛 ●めまい ●口内炎 ●歯肉炎 ●扁桃炎 ●打撲 ●頭部湿疹 ●酒?鼻 ●乳腺炎 ●抜け毛 ●etc・・・・・・・ |
◆五内の邪気・胃中の熱気・面赤酒皰・?鼻・白癩・赤癩・瘡瘍を主る。 ◆目赤熱痛・胸心・大腸小腸の大熱・心中煩悶を療し、小便を通じ、五種の黄疸を解し、大熱を治し、労復を起す。 ◆心煩を主治し、兼ねて発黄を旁治する。 ◆吐血・衂血・血痢・下血・血淋・損傷?血及び傷寒労復・熱厥頭痛・疝気・火傷を治す。 ※果実は、胃腸が弱く軟便気味の者には不適。 ※果実は、食品用着色料として、お正月のお節料理の栗きんとんや、節句やお祝いの時に食するご飯やお餅を黄色く染めるのに使われて います。 ※クチナシは果実が熟しても裂開しないことから、口無し(クチナシ)と名付けられた。 ※皮が薄くて丸く小さく、七稜から九稜まである刻房のものが良いそうです。 |
|
| 動物名{クマ} 《別名》 ツキノワグマ ヒグマ ヒマラヤグマ 《生薬名》 熊胆(ゆうたん)=胆嚢(胆汁) 熊の胆(くまのい)=胆嚢(胆汁) 《気味》 苦寒 |
ほ乳類 | 胆嚢(胆汁) | ●健胃薬 ●清熱 ●消炎 ●鎮痛 ●鎮静 ●鎮痙 ●発熱 ●高熱 ●痙攣 ●小児の熱性痙攣 ●小児の疳疾 ●肝炎 ●急性黄疸型肝炎 ●肝性昏睡 ●化膿症腫脹 ●炎症腫脹 ●急性咽頭炎 ●口腔潰瘍 ●結膜炎 ●帯状疱疹 ●胃潰瘍 ●十二指腸潰瘍 ●胆嚢炎 ●胆汁分分泌促進 ●利尿効果 ●下痢 ●黄疸 ●腸内寄生虫 ●痔疾患 ●肝硬変 ●高血圧症 ●胆嚢結石 ●動脈硬化症 ●糖尿病 ●腹部の腫瘤 ●心胸部痛 ●腹痛 ●精神疾患 ●食中毒 ●癲癇 ●寄生虫 ●水疱瘡 ●麻疹 ●小児の神経病 ●小児のひきつけ ●妊娠時の腹痛 ●産後の腹痛 ●etc・・・・・・・ |
◆伝染病による高熱・痙攣或いは熱傷・刺傷による発熱・譫語には、熊胆0.6〜1gを服用する。 ◆小児の熱性痙攣には、熊胆0.15gを服用し、あまり効果がない様なら服用量を少し増やす。 ◆劇症肝炎・急性黄疸型肝炎・肝性昏睡などに、熊胆0.3〜0.6gと茵陳蒿の煎薬と共に服用すると効果的です。 ◆帯状疱疹に散布すると鎮痛効果がある。 ◆消炎・鎮痛には0.6〜2.5gを服用する。 ◆痔疾患、炎症に外用する時は1日量0.3〜1.0g使用。 ※熊胆は煎じ薬としては使わず、直接服用するか外用、もしくは溶かして使用する事により、効果を発揮する。 ※熊胆と偽って、豚や牛の胆嚢が多いので注意しましょう。 ※とても苦味があります。お湯に溶かして服用出来ない方は、オブラートで服用してみて下さい。 |
|
| 黒犀()→サイに記載 | |||||
| 植物名{クワ} 《生薬名》 桑白皮= 桑根皮= 桑根柏皮= 桑椹=実 烏椹=実 桑実=実 椹=実 桑葉=葉 桑木= 《気味》 甘寒 |
クワ科 | 葉 枝 根皮 実 |
●解熱 ●去痰 ●鎮咳 ●抗菌 |
◆桑白皮は肺を瀉し、大腸・小腸を利し、気を降ろして、血を散ずる。 ◆咳嗽には桑白皮の粉末を服用する。 ◆消渇で尿が多い場合は桑白皮や桑葉を煎じて服用する。葉はお茶感覚で服用するも良し。 ◆金瘡かん椹には桑白皮を灰にして塗布する。 ◆抜け毛がひどい時や髪に艶が無くなった時は、桑白皮の煎液で洗う。 ◆小児の鵝口には桑の生の根の汁をつける。 ◆急性アルコール中毒には桑の汁を服用する。 ◆桑椹酒に醸して服用すれば、いらない水分を出し、腫れ物を治してくれる。 ◆桑木は、よく関節を利し、津液を補うもので、その火を用いれば毒気を抜き、風寒を駆逐する。 ※作成中・・・・・・・・・・ |
|
| け | 鶏子黄→鶏(ニワトリ)に記載 | ||||
| 鶏子白→鶏(ニワトリ)に記載 | |||||
| 決明子(けつめいし) →エビスグサに記載 |
|||||
| 植物名{ゲンノショウコ} 《別名》 現の証拠(げんのしょうこ) 玄草(げんそう)=全草 御輿草(みこしぐさ)=全草 たちまち草=全草 医者ゴロシ=全草 医者いらず=全草 ネコグサ=全草 《気味》 |
フウロソウ科 | 全草 |
●更年期障害 ●血の道 ●冷え症 ●食あたり ●下痢 ●止瀉薬 ●腹痛 ●しぶり腹 ●急性胃腸炎 ●慢性胃腸炎 ●便秘 ●緩下剤 ●健胃整腸剤 ●利尿剤 ●高血圧予防 ●強壮薬 ●胃潰瘍 ●十二指腸潰瘍 ●消化器潰瘍 ●腫れ物 ●しもやけ ●赤痢 ●血痢 ●疫痢 ●疫毒痢 ●関節痛 ●神経痛 ●皮膚病 ●湿疹 ●かぶれ ●風邪 ●頭痛 ●膀胱炎 ●強壮 ●扁桃炎 ●etc・・・・・・・ |
◆原末、煎剤、丸剤、どれも効果的である。煎剤として煎じる時は低い温度や短時間でも、エキスが充分出ます。 ◆ゲンノショウコは飲み過ぎても便秘などの副作用がないので、優れた健胃整腸剤と言えるでしょう。 ◆食あたりや下痢、慢性胃腸病、便秘に効果があります。 ◆下痢止めには1日量10〜20gを、お水500ccと共に半量になるまで煮つめ、2〜3回に分けて温め服します。 ◆胃腸の虚弱の方はお茶代わりに服用しても良く、利尿には1日量10g〜15gを、お水500ccと共に5〜10分位煎じ、それを 3回に分けて食前又は食間に服用します。 ◆高血圧予防には、ゲンノショウコ10g、ドクダミ10g、決明子(少し炮じた物)5gを煎じて、お茶代わりに服用すると良い。 ◆しぶり腹や冷え症や婦人の血の道(更年期障害)には、ゲンノショウコ風呂が良いです。 ゲンノショウコ100gとヨモギ100gを木綿の袋状になった靴下等に入れてお風呂に入れます。 ◆胃・十二指腸潰瘍には、ゲンノショウコと決明子を一緒に煎じて服用します。 ◆オオバコとゲンノショウコを一緒に煎じて服用すると胃酸過多による胃痛に効くとされています。 ◆腫れ物やしもやけ等には、煎液を外用剤として用います。 ◆かぶれには煎じた液を冷やしてから塗布します。 ◆昔、ゲンノショウコは疫痢や赤痢の治療に唯一の薬として用いられていました。 ※ゲンノショウコの若い時は、馬の足形(ウマノアシガタ・別名金鳳花・キンポウゲ科の野草)やトリカブト等の 有毒植物と大変よく似ているので、採集する時は注意しなければなりません。夏の開花時期に採取すれば安全です。 |
|
| こ | 蛤カイ(虫+介)(ごうかい)・ 蛤蠏→オオヤモリに記載 |
||||
| 紅参(こうじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 厚朴(こうぼく)→ホオノキに記載 | |||||
| 高麗参野山(こうらいじんやさん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 高麗人参(こうらいにんじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 牛黄(ごおう)→牛に記載 | |||||
| 五八霜(ごはっそう)→マムシに記載 | |||||
| キノコ名{コフキサルノコシカケ} 《生薬名》 梅寄生(ばいきせい) 《気味》 甘平  |
サルノコシカケ科 | 子実体 | ●抗癌作用 ●抗腫瘍薬 ●駆オ(ヤマイダレ+於)血作用 ●止血作用 ●帯下 ●肋膜炎 ●肺炎 ●解熱作用 ● ● ● ● ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆古来、梅の木に寄生するサルノコシカケ類という意味で名づけられたが、
現在は樫の木やブナの木に寄生するコフキサルノコシカケが主である。 ◆サルノコシカケ科の中では梅寄生が抗癌作用に効果が高いとされる。 ◆キノコの中ではマンネンタケ(霊芝)が抗癌作用が高いとされる。 ◆梅寄生1日量20g煎じる。1日3回温めて服用する。 ◆サルノコシカケの特徴=茎をのばさず樹幹から直接傘を開き子実体をつけ、 その形状が、まるで猿が樹木の背にもたれかかり腰かけているかの如し。 |
|
| 植物名{ゴボウ} 《生薬名》 牛蒡子(ごぼうし)=種子 悪実子(あくじつし)=種子 大力子()=種子 鼠粘子(そねんし)=種子 牛蒡根(ごぼうこん)=根 《気味》 |
キク科 | 種子 根 |
●抗菌 ●血糖降下 ●血管拡張 ●利尿 ●瀉下 ●肝臓病 ●扁桃腺炎 ●湿疹 ●あせも ●ただれ ●消炎 ●解熱 ●解毒 ●強壮 ●化膿促進排膿 ●胃痙攣 ●胃酸過多症 ●関節炎 ●乾癬 ●帯下 ●虫垂炎 ●食中毒 ●乳腺炎 ●乳房炎 ●麻疹 ●インフルエンザ ●etc・・・・・・・ |
◆牛蒡子1日量5〜50gを、水200cc〜600ccと共に弱火で半量になるまで煎じる。日に1〜3回に分けて
服用する。 ◆牛蒡子の粉末を日に3回に分け、1回量1gずつ服用する。 ◆湿疹・あせも・ただれ等に煎じた液を外用剤として塗布する。 ◆ゴボウの根は食欲増進・胆汁分泌促進・発汗・利尿に効果があります。 |
|
| さ | 動物名{サイ(黒犀・白犀・印度犀・爪哇犀・蘇門犀)} 《生薬名》 犀角(さいかく)=角 《気味》 苦寒 |
サイ科 | 角 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
◆全ての毒気や、特に虫を用いた呪いの蠱毒の毒気や、邪悪な気が人の体に入り込み、悪寒や発熱があり、
急に胸やお腹が痛んだり、精神錯乱を起こしたりして段々病が重くなり死に至る。1人が死ぬと次々に伝染して、集団で生活している所の
大半が死滅する。シュ(ヤマイダレ+主)病の毒気や、人に悪影響を及ぼす邪気や、死人の祟りの鬼気や、山や川から自然に発する毒気の瘴気に
あてられて生じた病を治す。 ◆毒草の毒や、毒鳥の毒や、毒蛇の毒を消し、人に悪い影響を与える邪気を除き、何事にも迷わず惑わされない健全な 精神状態にしてくれる。そうなると悪い夢にうなされる事もなくなる。 ◆毎日服用すると身体の動きが軽くなる。 |
| 植物名{サクラ} 《生薬名》 桜皮(おうひ)=樹皮 《気味》 |
|||||
| 植物名{サフラン} 《生薬名》 番紅花(ばんこうか)=雌しべ 西紅花(せいこうか)=雌しべ 蔵紅花()=雌しべ 泪夫藍()=雌しべ 《気味》 |
アヤメ科 | 雌しべ | ●メニエール症候群 ●冷え症 ●血の道症 ●更年期障害 ●月経困難症 ●無月経 ●月経過多 ●月経不順 ●小児の百日咳 ●喘息 ●ヒステリー ●不眠症 ●頭痛 ●めまい ●風邪の初期 ●鎮静 ●鎮痛 ●通経薬 ●発癌抑制作用 ●疲労回復 ●心臓病 ●アレルギー体質改善薬 ●血中コレステロール低下作用 ●子宮収縮作用 ●血液凝固抑制作用 ●血管拡張作用 ●利胆作用 ●鬱病 ●筋肉の痙攣 ●麻疹 ●食欲不振 ●腰痛 ●鼻血 ●腎臓病 ●月経痛(生理痛) ●子宮内膜症 ●卵巣嚢腫 ●精神分裂病 ●鬱病 ●のぼせ症 ●扁桃腺炎 ●パーキンソン病 ●レイノー病 ●変形性膝関節炎 ●ギックリ腰 ●骨粗鬆症 ●労作性狭心症 (心内膜下梗塞) ●不整脈 ●息切れ ●アルツハイマー型 初老期認知症 ●etc・・・・・・・ |
◆婦人の血の道の薬として、更年期障害、月経困難、無月経、月経過多などに常用します。気分が優れない時、
ヒステリー気味の時、なかなか寝付けない時、又は頭痛やめまい等に効果があります。1回 0.2〜0.3g です。 ◆民間薬として一般に飲用するには、サフランを5〜10本取り、湯呑みに入れて熱湯を注ぎ、数分放置すると橙色に染まり始めます。 風邪気味の時にも効き目があります。お湯の代わりにホワイトリカーやホワイトワインや、ホットウイスキーを直接入れて服用しても 構いません。 ※通経、子宮収縮作用が強いので、妊婦の方は服用しないで下さい。 |
|
| さ | 植物名{サルトリイバラ} 《生薬名》 バッ(草冠+抜)カツ(草冠+契)(ばっかつ)=根茎 《気味》 |
●清血作用 ●利尿作用 ●解毒作用 ●清熱作用 ●浮腫み ●腫れ物 ●出来物 ●ニキビ ●吹出物 ●化膿 ●おりもの ●帯下 ●陰部の痒み ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆土瓶に根茎の乾燥した物10g〜15g、水400ccと共に半量になるまで煎じ、1日3回に分けて服用する。 ◆陰部の痒みには、バッ(草冠+抜)カツ(草冠+契)を浴剤とし、煎じた汁をお風呂に入れる。 |
||
| 三七(さんしち)→サンシチニンジンに記載 | |||||
| 山漆(さんしつ) →サンシチニンジンに記載 |
|||||
| 植物名{サンシチニンジン} 《生薬名》 >生薬名 田七人参(でんしちにんじん)=根茎 三七人参(さんしちにんじん)=根茎 田三七(でんさんしち)=根茎 不換金(ふかんきん)=根茎 田七(でんしち)=根茎 三七(さんしち)=根茎 山漆(さんしつ)=根茎 参三七(じんさんしち)=根茎 人参三七(にんじんさんしち)=根茎 金不換(きんふかん)=根茎 《気味》 |
ウコギ科 | 根茎 | ●抗ウイルス作用 ●抗真菌作用 ●抗癌作用 ●強心作用 ●血圧降下作用 ●抗ストレス作用 ●血糖値降下作用 ●高血圧症 ●糖尿病 ●C型肝炎 ●慢性肝炎 ●肝硬変 ●打ち身 ●捻挫 ●産後の腹痛 ●脳卒中 ●胃・十二指腸潰瘍 ●鼻血 ●食欲不振 ●免疫力の低下 ●アルコール依存症 ●過食症 ●拒食症 ●動脈硬化症 ●心筋梗塞 ●狭心症 ●肩こり ●更年期障害 ●肉体疲労 ●精力減退 ●冷え症 ●生理不順 ●婦人病 ●二日酔い ●肝斑(しみ) ●老人性色素斑 ●アレルギー性鼻炎 ●アトビー性皮膚炎 ●湿疹 ●吹出物 ●顔面黒皮症 ●慢性腎炎 ●悪性腫瘍 ●古血下し (駆オ(ヤマイダレ+於)血剤) ●etc・・・・・・・ |
◆止血、消腫(しょうしゅ:腫れ物を消すこと)、鎮痛、消炎、強心薬として、打撲、ねんざ、吐血などの出血症状、冠状動脈疾患、狭心症、高血圧、
心筋梗塞などに用いられます。中国では臨床的に止血作用、抗真菌作用、強心作用が認められており、また急性、慢性肝炎などにも用いられています。 ◆採取した田七人参の皮をむいて乾燥させて粉末状にしたもを1回量1〜5g、1日1〜3回服用する。 ◆挫創・打撲には白湯また酒で田七末を1日2回〜3回、1回3〜5gずつ服用する。 ◆外傷出血に粉末を患部につける。 ◆身体外部の腫瘍の初期には等量の大黄末と酢を練って塗布する。 ◆挫創・打撲傷・内臓の痛みには外用・内服とも効果が早い。 ◆狭心症、コレステロール血症等には1日3回、1回量1g服用する。 ◆吐血、衄血、血便、産後出血等には1日2回〜3回 1回3〜5gを服用する。 ※人参の3倍以上のサポニンが含まれる。 |
|
| 三七人参(さんしちにんじん) →サンシチニンジンに記載 |
|||||
| 植物名{サンシュユ} 山茱萸(さんしゅゆ) 蜀棗(しょくそう) 《気味》 酸平 |
ミズキ科 | 果実 | ●メニエール病 ●寒熱病 ●補腎薬 ●強壮薬 ●眩暈(めまい) ●耳鳴り ●更年期障害 ●陰萎 ●遺精 ●頻尿 ●強精薬 ●小便不利 ●老人夜尿症 ●etc・・・・・・・ |
◆お酒に浸けたものを服用すれば老人や病後などの滋養強壮薬になり、強精薬にも効果があります。 ◆山茱萸酒の作り方は、種子を取り除き乾燥させたサンシュユの果肉200gとほぼ同量の氷砂糖をホワイトリカー1.8Lに浸し、 そのまま2〜3ヶ月冷暗所に放置した後、布などでこし、盃一杯ずつ服用します。 ◆煎じる時は山茱萸1日量5〜8gと、お水300ccと共に弱火で半量になるまで煎じ、三回に分けて食前又は食間に服用します。 ◆補腎、強壮剤として、眩暈、耳鳴り、陰痿、遺精、頻尿、老人の夜尿症などに効果があります。 ※種子を除いて果肉ばかりの物で、紫黒色で甘酸っぱい物が良品とされています。 |
|
| 山棗(さんそう)→ナツメに記載 | |||||
| 酸棗仁(さんそうにん) →ナツメに記載 |
|||||
| 山薬(さんやく)→ヤマノイモに記載 | |||||
| 地黄(じおう)→アカヤジオウに記載 | |||||
| 紫オウ(草冠+夭)(しおう) →ムラサキに記載 |
|||||
| 動物名{鹿・しか} 生薬名 鹿茸(ろくじょう)=雄の幼角 馬鹿茸(ばろくじょう)=雄の幼角 花鹿茸(かろくじょう)=雄の幼角 白膠(びゃっきょう)=馬鹿角膠 鹿角膠(ろっかくきょう)=馬鹿角膠 黄明膠(おうめいきょう)=馬鹿角膠 鹿歯(ろくし)=歯 鹿骨(ろっこく)=骨 鹿頭肉(ろくずにく)= 鹿蹄肉(ろくていにく)= 鹿脂(ろくし)= 鹿髄(ろくずい)= 鹿脳(ろくのう)=脳 鹿精(ろくせい)= 鹿血(ろくけつ)=血液 鹿腎(ろくじん)=腎臓 鹿鞭(ろくべん)=腎臓 鹿膽(ろくたん)= 鹿筋(ろくきん)= 鹿靨(ろくえん)= 鹿皮(ろくひ)= 鹿糞(ろくふん)= 鹿胎糞(ろくたいふん)= 鹿尾(ろくび)= 鹿陰茎(ろくいんけい)= 鹿茎筋(ろくけいきん)= 《気味》 甘温 |
シカ科 | 雄の幼角・袋角 馬鹿角膠 |
●強壮剤 ●強精剤 ●滋養強壮作用 ●インポテンツ ●目眩 ●耳鳴り ●帯下 ●頭痛 ●頭重 ●腰痛 ●運動麻痺 ●むち打ち ●打撲 ●神経痛 ●筋肉痛 ●鎮痛薬 ●首筋の痛み ●ふらつき ●四肢のしびれ感 ●疲労感 ●脱力感 ●自律神経失調症 ●無気力症 ●悪性腫瘍 ●視力障害 ●冷え症 ●低血圧症 ●不眠症 ●更年期障害 ●四十肩 ●五十肩 ●背痛 ●不正出血 ●子宮出血 ●夢精 ●不整脈 ●動悸 ●息切れ ●心臓疾患 ●小児発育不良 ●低体温症 ●項頚部痛 ●肩腕痛 ●etc・・・・・・・ |
◆鹿茸は、主にダラダラと子宮から出血する病、血のめぐりが悪く血液の滞りにより出来た病、悪寒と発熱を伴う病、
急に何かに驚きひっくり返ったりする病を治す。 ◆元気を益し腎機能の働きを良くして精力を強化し、年をとっても歯を強くするという作用が有る。 ◆悪性の皮膚病や比較的に根は浅いが悪性のおできの腫れを治す。 ◆身体に入り込み病気を引き起こす邪気や悪気や生殖器中に留まる不要な血を追い出す作用がある。 ◆男子の腰腎の虚冷や脚膝の無力を補う。 ◆夢精する者、婦人の不正出血や月経出血がダラダラと出て止まらない者、血が混ざったおりものが出る者には、 鹿茸を火で炙り粉にし、一回量2g前後を空腹時に酒と共に服用する。 ◆鹿茸炙粉末 1日0.5〜2.5g食前又は食間に服用する。 ◆鹿茸は、血と肉の精。よく人の陽を養い、腎命を補い、骨を堅くし、骨髄を補い、精を増し、血を養う。 虚している者を補い、損じている者を培い、絶している者を継ぎ、怯えやすい者の精神を強くし、 体が冷えている者を暖める効果があり、およそ真陽の精血衰微した一切の虚損の症に用いられる。 また、陰疽潰瘍で長く口が収まらないものに適用して内?補陽の助けとなる。 ※陰虚血熱の諸症には用いてはいけない。温腎・益火の効は附子や肉桂と同じですが、 附子・肉桂は薬性の温が烈しく、単味で陽を巡らし、逆を救う効果がある。 |
|
| 紫根(しこん)→ムラサキに記載 | |||||
| 柿根(しこん) →カキに記載 |
|||||
| ジジノキンチャク→ナズナに記載 | |||||
| 植物名{シソ} 生薬名 紫蘇(しそ) 紫蘇子 (しそし)= 紫蘇葉 (しそよう)= 《気味》 |
●鎮咳作用 ●鎮静作用 ●鎮痛作用 ●解毒作用 ●利尿作用 ●防腐作用 ●こしけ ●帯下 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆気を巡らし、血を和して蘇らせる働きがある。 ◆こしけ(帯下)には、紫蘇子10gを水600ccと共に弱火で半量になるまで煎じる。1日3回温めて服用する。◆ |
|||
| 紫丹(したん)→ムラサキに記載 | |||||
| シジウム | 花粉症 etc・・・・・・・ |
※シジウムとグァバは同類のシジウム属ですが、同じ物ではない。 | |||
| 紫草(しそう)→ムラサキに記載 | |||||
| 柿霜(しそう)→カキに記載 | |||||
| 柿霜餅(しそうべい)→カキに記載 | |||||
| 柿蒂(してい)→カキに記載 | |||||
| 自然生(じねんじょう) →ヤマノイモに記載 |
|||||
| 柿餅(しべい)→カキに記載 | |||||
| 自然薯(じめんじょ) →ヤマノイモに記載 |
|||||
| 三味線草(しゃみせんぐさ) →ナズナに記載 |
|||||
| 爪哇犀(じゃわさい)→サイに記載 | |||||
| 十薬(じゅうやく)→ドクダミに記載 | |||||
| 熟地(じゅくじ) →アカヤジオウに記載 |
|||||
| 熟地黄(じゅくじおう) →アカヤジオウに記載 |
|||||
| 植物名{ジュズダマ} 別名 唐麦(とうむぎ) 生薬名 川穀(せんこく)=苞鞘含果実 =苞鞘含果実 《気味》 |
イネ科 | 苞鞘含果実 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ ※ハトムギとジュズダマはジュズダマ属のイネ科なのでよく似ていますが、生薬のヨク(草冠+意)苡仁はハトムギで、 生薬の川穀はジュズダマです。間違えないようにしましょう。 |
|
| 柿葉(しよう)→カキに記載 | |||||
| 将軍木皮(しょうぐんぼくひ) →アケビに記載 |
|||||
| 生地黄(しょうじおう) →アカヤジオウに記載 |
|||||
| 薯蕷(しょよ)→ヤマノイモに記載 | |||||
| 地龍(じりゅう)→ミミズに記載 | |||||
| 地竜(じりゅう)→ミミズに記載 | |||||
| 地竜干(じりゅうかん) →ミミズに記載 |
|||||
| 地竜肉(じりゅう)→ミミズに記載 | |||||
| 刺老鴉(しろうあ)→タラノキに記載 | |||||
| 白犀(しろさい)→サイに記載 | |||||
| 辛夷(しんい)→モクレンに記載 | |||||
| 参三七(じんさんしち) →サンシチニンジンに記載 |
|||||
| す | 植物名{スイカズラ} 忍冬(にんどう)=葉 金銀花(きんぎんか)=花蕾 金銀藤(きんぎんとう)=花蕾 《気味》 |
スイカズラ科 | 葉 花蕾 |
・・・・・・・作成中・・・・・・・ | |
| 水參(すいじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 水馬(すいば) →タツノオトシゴに記載 |
|||||
| スギナ→つくしに記載 | |||||
| せ | 薺(せい)→ナズナに記載 | ||||
| 薺菜(せいさい)→ナズナに記載 | |||||
| 生地(せいじ)→アカヤジオウに記載 | |||||
| 生地黄(せいじおう)(西洋人参) →アメリカニンジンに記載 |
|||||
| 石蒜(せきさん)→彼岸花に記載 | |||||
| 接骨木(葉・花・根)(せっこつぼく) →ニワトコに記載 |
|||||
| 鮮地黄(せんじおう) →アカヤジオウに記載 |
|||||
| 仙蟾(せんせん)→オオヤモリに記載 | |||||
| 植物名{センナ} 番瀉実(ばんしゃじつ)=果実 番瀉葉(ばんしゃよう)=葉 センナ葉(せんなよう)=葉 《気味》 |
マメ科 | 葉 果実 |
●etc・・・・・・・ | ◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ | |
| そ | 棗(そう)→ナツメに記載 | ||||
| 草決明(そうけつめい) →エビスグサに記載 |
|||||
| 蘇門犀(そもんさい)→サイに記載 | |||||
| た | 植物名{大根・ダイコン} 《生薬名》 莱フク(草冠+服)(らいふく)=根 莱フク(草冠+服)子(らいふくし)=種子 蘿蔔子(らぶし)=種子 《気味》 |
アブラナ科 | 多肉根 全草 |
●解熱作用 ●鎮咳作用 ●健胃作用 ●去痰作用 ●胆汁分泌促進作用 ●咽喉痛 ●二日酔 ●打ち身 ●打撲 ●くじき ●捻挫 ●冷え症 ●神経痛 ●こしけ ●帯下 ●陰部の痒み ●etc・・・・・・・ |
◆冷え症・神経痛・こしけ・陰部の痒みには、干葉湯(干して乾燥させた葉を浴剤として使用する)にする。 お風呂に入れる量は、一回量15株程度の乾燥葉。 腰湯には5株程度の乾燥葉を大きな土鍋に水と共に煮てタライに移し、少しの塩を加え、火傷しない温度にする為水を足し、少し冷ます。 汗が出る位まで温めると効果的です。 ◆多肉根は、風邪の発熱・二日酔に良い。 ◆健胃薬としては、生の大根をおろし、その汁約20〜40ccを取り、1日2回に分けて服用する。 ◆打撲・捻挫には、おろし汁で冷湿布する。 ◆種子は、1日5〜10gを煎じるか、粉末にして服用する。 ◆咳やのどの痛みには、短冊切りにした大根をコップ一杯用意し、その中に蜂蜜又は水飴を2〜3杯入れ、その滲出液を服用する。 ◆腹痛には、種子を10粒位良く噛んで食べる。 ※葉の部分は清白(すずしろ)と呼ばれ、春の七草の一つ。 |
| 海魚名{タツノオトシゴ} 海馬(かいば)=内臓.皮膜除去物 水馬(すいば)=内臓.皮膜除去物 龍落子(りゅうらくし)= 内臓.皮膜除去物 海蛆(かいそ)=内臓.皮膜除去物 《気味》 甘温 |
ヨウジウオ科 | 内臓.皮膜 除去物 |
●ED ●勃起不能 ●インポテンツ ●精力減退 ●遺精 ●肉体疲労 ●滋養強壮 ●慢性腎炎 ●ネフローゼ ●腎不全 ●頻尿 ●尿失禁 ●夜間の多尿 ●前立腺肥大 ●前立腺癌 ●悪瘡 ●毒癰 ●排尿困難 ●不妊症 ●皮膚化膿症 ●免疫力強化作用 ●etc・・・・・・・ |
◆男性ホルモンのような作用があり強壮作用をもたらすので、 ED(勃起不能障害)や精力減退、遺精に効果があります。 ◆補腎(腎機能を強化する薬)作用があるといわれ、腎機能を強化するということから、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、老人の頻尿、 尿失禁、夜間多尿、前立腺肥大、前立腺炎による排尿困難などの治療にも用いられます。 ◆女性の子宮発育不良による不妊症にも効果があります。 ◆皮膚化膿症には海馬をスープにして服用すると効果があるといわれています。 ◆海馬1日量2〜6gを煎じて服用する。丸剤、散剤として服しても可。 |
|
| た | 大壁虎(だいへきこ)→オオヤモリに記載 | ||||
| タムシバ→コブシに記載 | |||||
| 植物名{タラノキ} 別名 鬼の金棒(おにのかなぼう) 生薬名 タラ根皮(たらこんぴ)=根皮 タラ木(たらぼく)=幹皮 刺老鴉(しろうあ)=根皮 《気味》 辛平 |
ウコギ科 | 根皮 幹皮・樹皮 葉 |
●健胃整腸薬 ●胃腸病 ●胃癌 ●糖尿病 ●高血圧症 ●消炎作用 ●利尿作用 ●強精作用 ●精神安定作用 ●神経不安 ●駆オ(ヤマイダレ+於)血薬 ●リウマチ性関節炎 ●腎炎 ●肝硬変 ●慢性肝炎 ●陰痿 ●血糖降下作用 ●血圧降下作用 ●腸管興奮作用 ●子宮興奮作用 ●健胃作用 ●整腸作用 ●強壮作用 ●etc・・・・・・・ |
◆糖尿病にはタラ根皮と連銭草と枇把葉各5gを水400ccと共に弱火で半量まで煎じて、1日3回に分け食間に
服用する。これにフジバカマの乾燥全草を5g加えても良い。 ◆タラ根皮1日量10〜20gと水300ccを弱火で煎じ、1日3回に分けて服用する。 ◆高血圧症にはタラノキの茎のトゲだけを集め、1日量5〜10gと水200ccと共に弱火で半量まで煎じ、3回に分けて服用する。 ◆胃腸病・神経痛などには樹皮を 1日量15〜25g 煎じて日に3回に分けて服用する。 ◆葉は健胃整腸薬に良い。 ※幹や樹皮には刺が有るが、根皮には無い事から、生薬のタラ根皮にはトゲの混入の無い物を良とするそうです。 ※根を煎じた物をタラ根湯と言う。 ※中国の?木白皮もタラ根皮とほぼ同様に用いられます。 |
|
| 植物名{タンジン} 丹参(たんじん)=根 赤参()=根 紅根()=根 紫丹参()=根 血参根()=根 大紅袍()=根 木乳羊()=根 活血根()=根 《気味》 |
シソ科 | 根 | 駆オ(ヤマイダレ+於)血作用 etc・・・・・・・ |
◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ ※丹参・人参・沙参・玄参・苦参を“五参”と呼び、五行説の思想に当てはめて、それぞれ主る色・臓器があると されている。 人参は脾に入るから黄参と言い、沙参は肺に入るから白参と言い、玄参は腎に入るから黒参と言い、 牡蒙(ぼもう)は肝に入るから紫参といい、丹参は心に入るから赤参といい、苦参は右腎、命門の薬。 |
|
| 植物名{タンポポ} 《生薬名》 蒲公英(ほこうえい)=全草 蒲公草(ほこうそう)=全草 蒲公英根(ほこうえいこん)=根 土公英(どこうえい)=全草 《気味》 甘平 
|
キク科 | 全草 根 |
●健胃薬 ●利胆薬 ●解熱薬 ●強壮薬 ●乳汁不足 ●乳汁欠乏症 ●催乳効果 ●抗癌作用 ●消炎作用 ●利尿作用 ●発汗作用 ●消化不良 ●胃痛 ●乳房の腫れ ●水腫 ●浮腫 ●皮膚潰瘍 ●便秘 ●眼疾腫痛 ●大便秘結 ●小便不利 ●淋病 ●感冒 ●咽喉炎 ●肝炎 ●ニキビ ●etc・・・・・・・ |
◆健胃・利胆・解熱・強壮には、蒲公英の刻みを1日量 10〜20gと共に水 500CCを加え、弱火で半量になるまで煮つめ、
1日3回に分けて毎食前に温かいうちに服用する。 又、症状が強い時は、蒲公英根の刻みを1日量 約 5〜10gと共に水 200〜400ccを加え、弱火で半量になるまで煮つめ、 1日3回に分けて、毎食前に温かくして服用する。 ◆タンポポは昔から特に催乳効果があり、乳汁欠乏症や乳房の腫れ、ニキビ等に、金銀花 5〜8gと、蒲公英根 5〜8gの同量を煎じると 効果を発揮します。 ◆全草を食すると、食毒を消し、乳腫を治す。又、母乳不足や浮腫みやすい人は、普段から生の葉を茹でて和え物にしたり、サラダにして 食べると良いでしょう。 ◆腫れ物には、葉や茎をすり潰し、患部につける。それと同時に、根 10gを煎じて服用すると更に効果がある。 ◆乾燥させた根を、適当な大きさに刻み、土鍋で炒り、それをミキサー等で粉砕して茶漉しに入れ、熱湯を注ぐ。 そうすると手軽に服用できるタンポポコーヒーの出来上がりです。 ◆便秘がちで、胃弱の人には、蒲公英根を1日量 15g煎じ、1日3回に分けて温かくして服用する。 ◆開花前のタンポポの全草を採集し、よく水洗いして天日で乾燥させる。 根を採集する時期は、秋から早春にかけて地上部の活動がない時に根を切らないように掘り起こし、よく水洗いしてから天日で乾燥 させる。 ※ タンポポは、内服・外用共に用いられる。 |
|
| ち | 丑玄(ちゅうげん)→牛に記載 | ||||
| 丑宝(ちゅうほう)→牛に記載 | |||||
| 朝鮮人参(ちょうせんにんじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 朝鮮参(ちょうせんじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 槿皮(ちんび)→ムクゲに記載 | |||||
| 槿花(ちんふぁ)→ムクゲに記載 | |||||
| つ | 通草(つうそう)→アケビに記載 | ||||
| 通草子(つうそうし)→アケビに記載 | |||||
| 植物名{ツクシ} 生薬名 杉菜(すぎな)=栄養茎 問荊(もんけい)=全草・栄養茎 つくしんぼう=胞子茎 接続草(せつぞくそう)=胞子茎 《気味》 |
トクサ科 | 栄養茎 全草 |
●制癌作用●抗炎症作用 ●止血作用●解熱作用 ●解毒作用●鎮咳去痰薬 ●回虫駆除作用 ●利尿作用 ●肺病●肺結核 ●浮腫●かぶれ ●汗疹●ニキビ●吹出物 ●アトピー性皮膚炎 ●アレルギー性皮膚炎 ●切り傷●下血 ●膀胱炎●尿道炎 ●肋膜炎(胸膜炎) ●腎炎●収斂作用 ●月経痛(生理痛) ●冷え症●不正出血 ●婦人病●尿路結石 ●脱毛症(抜け毛) ●淋病●急性・慢性肝炎 ●下痢●高血圧症 ●動脈硬化症●糖尿病 ●胃・十二指腸潰瘍 ●自律神経失調症 ●老化防止●夜尿症 ●etc・・・・・・・ |
◆生汁は、汗疹・化粧品かぶれやウルシにかぶれた時、直接患部に塗ると炎症を抑えてくれます ◆かぶれや湿疹のかゆみ、アトピー性皮膚等で浴剤として使う時は、沸騰したお湯の中に乾燥したスギナ又は生葉を入れ、 弱火で5〜10程煎じ、煎じ終えた液を浴槽に入れます。 ◆利尿、咳止め、解熱、回虫駆除などに用いる時は スギナを1日 5〜10gを煎じて服用します。 かぶれ・ウルシかぶれ・ニキビ・吹き出物・出血の時、直接患部に塗る。 ◆冷え症には、乾燥スギナをホワイトリカーの瓶中に入れ、10日間つけ込んだ後スギナを取り去り、冷暗所に保存し、服用する時は お湯又はお茶などに数滴たらし、1日数回効果が出るような量を服用して下さい。 ◆結気、瘤痛、上気、気急には、問荊の煎薬を服す。 ◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ |
|
| 植物名 {ツヅラフジ・オオツヅラフジ} 防已(ぼうい)= |
|||||
| 植物名{ツルニンジン} 《生薬名》 党参(とうじん)=根 上党人参(じょうとうにんじん)=根 黄参(おうじん)=根 《気味》 甘平 |
キキョウ科 | 根 | ●息切れ ●動悸 ●食欲不振 ●軟便 ●下痢 ●喘息 ●咳 ●慢性の咳嗽 ●糖尿病 ●血圧降下作用 ●強壮作用 ●健胃薬 ●肉体疲労 ●口渇 ●脱肛 ●消化吸収機能低下 ●自汗 ●栄養不良性貧血 ●etc・・・・・・・ |
◆1日量 9〜15gを煎じる。又は焼酎に浸ける。 ◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ |
|
| 田三七(でんさんしち) →サンシチニンジンに記載 |
|||||
| 田七(でんしち) →サンシチニンジンに記載 |
|||||
| ドウカン→王不留行に記載 | |||||
| と | 植物名{トウキ} 《生薬名》 当帰(とうき)= |
||||
| 植物名{トウゴマ} 《生薬名》 唐胡麻(トウゴマ)=種子 蓖麻子(ヒマシ)=種子 ヒマシ油(ヒマシユ)=油 《気味》 |
トウダイグサ科 | 種子 油 |
●ものもらい ●便秘 ●日焼け ●吹出物 ●水毒病 ●食中毒 ●急性胃腸炎 ●駆虫薬 ●水虫 ●タムシ ●いんきん ●etc・・・・・・・ |
◆ものもらいには皮を取り去った種子1個と同じ分量の梅肉を練り合わせ、就寝時にヘソの中に詰めて絆創膏などで
止め、翌朝取り去る。 ◆便秘には、ヒマシ油を1回量大人5〜25ml服用。(個人差が有りますので注意しましょう。) ◆吹出物や日焼けには、種子の皮を去り砕いた物を患部に塗る。 ※ヒマシは毒性が強いので出来るだけ服用には注意が必要です。 ※外用として使用する時は肌荒れなど起こす恐れがありますので十分注意して下さい。 ※月経時や妊婦、小児、痙攣性便秘、虫様突起炎、腹膜炎の人の服用は厳禁です。 |
|
| 党参(とうじん) →ツルニンジンに記載 |
|||||
| 植物名{トウシンソウ} 《生薬名》 灯心草(とうしんそう)=浮上茎髄部 燈心草(とうしんそう)=浮上茎髄部 《気味》 甘 微寒 |
イグサ科 | ●止血作用 ●利尿作用 ●解熱作用 ●鎮静作用 ●小便不利 ●浮腫 ●淋病 ●水腫 ● ● ● ● ● ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆浮腫がある者には、地上部または灯心を煎じて服用する。 ◆止血には、生の燈心草を潰して患部に貼る。 ◆心火を降ろし、血を止め、気を通じ、腫を散じ、渇を止める。 ◆五淋には生を煎じて服す。朽敗した席を煮て服するが更に良い。 ◆湿を利し、熱を切する。よく上部の鬱熱を小便の排出により下行させる。 ◆心煩して不眠症の者や産後の浮腫に効果あり。 ◆ ◆ ◆・・・・・・・作成途中・・・・・・ |
||
| 刀豆(とうず)→ナタマメに記載 | |||||
| 植物名{ドクダミ} 《生薬名》 十薬(じゅうやく) 魚腥草(ぎょせいそう) 《気味》  
|
●痔出血 ●すり傷 ●化膿止め ●水虫 ●こしけ ●帯下 ●冷え症 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆高血圧予防には、ゲンノショウコ10g、ドクダミ10g、決明子(少し炮じた物)5gを煎じて、お茶代わりに
服用すると良い。 ◆こしけや冷え症には、乾燥した全草30株をお風呂に入れる。 ◆・・・・・・・作成途中・・・・・・ |
|||
| 土公英(どこうえい) →タンポポに記載 |
|||||
| 土精(どせい)→牛に記載 | |||||
| 土精(どせい)→牛に記載 | |||||
| 植物名{とちゅう} 《生薬名》杜仲(とちゅう)=樹皮 杜仲葉=葉 思仙(しせん)=樹皮 思仲(しちゅう)=樹皮 木綿(もくめん)=樹皮 川仲(せんちゅう)=樹皮 漢仲(かんちゅう)=樹皮 ?芽(めんが)=若芽 《気味》 辛平 |
トチュウ科 | 樹皮 (最外層コルク層去) 葉 若芽 |
●強壮作用●強精作用 ●鎮痛作用●鎮静作用 ●降圧作用●安胎作用 ●流産防止作用 ●内臓脂肪除去作用 ●神経痛●腰痛●肩こり ●片頭痛●膝関節痛 ●身体疼痛●便秘 ●低血圧症●不眠症 ●高コレステリン血症 ●動脈硬化症●白髪 ●脳神経衰弱●めまい ●ED●インポテンツ ●頻尿●排尿困難 ●虚弱体質●抜け毛 ●筋無力症 ●神経衰弱●糖尿病 ●心臓疾患●腎臓疾患 ●生殖機能疾患 ●脳中枢神経疾患 ●肝臓疾患●薄毛 ●代謝障害●皮膚病 ●ストレス性症候群 ●リウマチ●関節痛 ●二日酔い●肥満症 ●水太り●脂肪太り ●健忘症(物忘れ) ●冷え症●耳鳴り ●妊婦の腰重痛 ●乳癌●前立腺癌 ●更年期障害●胃潰瘍 ●高血圧症●利尿作用 ●etc・・・・・・・ |
◆腰や膝や背の痛みを治し、内臓の諸機能を補い、元気を増し、筋骨を堅くし、意志・精神力を強くし、
常に服用すると身体の動きを軽くし老しない。 ◆陰部の周辺がグジュグジュと汁が出て痒い者や小便出るが残尿感がありスッキリしない者を治す。 ◆精力を使い果たし疲れきった肉体には、杜仲をお酒に漬けて服用すると効果的です。杜仲 100g お酒1L ◆若芽は脚気・リウマチに良い。 ※刻んだ杜仲樹皮を 1日量3〜30g 又、杜仲葉は 1日量10〜30g を煎じて服用する。 |
|
| な | 植物名{薺・ナズナ} 《別名》 ぺんぺん草(ぺんぺんぐさ) 撥草(ばちぐさ) 三味線草(しゃみせんぐさ) ジジノキンチャク 《生薬名》 薺(せい)= 薺菜(せいさい)= 《気味》 |
アブラナ科 | ●子宮収縮作用 ●下り物●帯下 ●血圧降下作用 ●止血作用●利尿作用 ●消炎作用●消腫作用 ●鎮痛作用●解熱作用 ●眼球充血●腹痛 ●子宮出血●下痢 ●高血圧症●便秘 ●陰部の痒み ●肝臓病●血便●血尿 ●生理不順●吐血 ●目の痛み●腸出血 ●浮腫●etc・・・・・・・ |
◆五臓を利し、目を明かにし、胃を益す。・・・・・・・作成中・・・・・・・ | |
| 植物名{ナタマメ} 白刀豆(はくとうず) 刀豆(とうず) |
マメ科 | 種子 | ●etc・・・・・・・ | ◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ | |
| 植物名{ナツメ} 大棗(たいそう)=果実 酸棗仁(さんそうにん)=種子 棘(きょく)=小果実 棗(そう)=大果実 サネブト=種子 《気味》 大棗=甘平 |
クロウメモドキ科 | 果実・種子 |
大棗 ●鎮痛作用 ●緩和作用 ●強壮作用 ●利尿作用 ●鎮痙作用 ●鎮静作用 ●滋養作用 ●身体の疼痛 ●腹痛 ●知覚過敏の緩和 ●牽引痛 ●筋肉の急迫 ●煩燥 ●咳 ●夜泣き ● ● ● etc・・・・・・・ 酸棗仁 ●神経不安症 ●催眠作用 ●鎮静作用 ●心因性神経症 ●不眠症 ●健忘症 ●神経虚弱 ●多汗症 ●降圧作用 ● ●子宮興奮作用 ● ● ● etc・・・・・・・ |
《大棗》 ◆胸や腹の部位の病や人に悪い影響を与える風・暑・湿・燥・寒・火(熱)の邪気が身体に入り込み 病気を引き起こされた病の者。 ◆内蔵の機能を安らかにし、脾臓の働きを育て養い、手の太陰肺経・手の厥陰心包経・手の少陰心経・手の陽明大腸経・手の少陽三焦経・ 手の太陽小腸経・足の太陰脾経・足の厥陰肝経・足の少陰腎経・足の陽明胃経・足の少陽胆経・足の太陽膀胱経の十二経脈の流れを助け、 飲食物から吸収されて全身を営養する胃気の動きを調え、耳・目・口・鼻・尿道口・肛門の九竅に滞りを通じさせ、 元気のない者や津液が少なくなったのを補う。 ◆体の中にある病や、諸々の陰と陽の気の不足によって生じた病や、物事に大変驚きやすい精神不安の病や、 手足が重怠い病を治す働きがある。 ◆ナツメの葉には麻黄をたすけ、よく汗を出させる働きがある ◆滋養強壮に大棗酒が効きます。 大棗酒の作り方 大棗刻み300gに対してホワイトリカー1.8㍑とグラニュー糖150gと共に2ヶ月以上冷暗所に保管後、布でこし、1日30mlを限度として就寝前に服用。 ◆小児の夜泣きに、大棗1日量3〜5gと水200〜600ccを土瓶に入れ、弱火で半分になるまで煎じて服用。 ※ 《酸棗仁》 ◆胸や腹の部位の病気や、悪寒と発熱を伴う寒熱病や、人に悪い影響を与える風・暑・湿・燥・寒・火(熱)の邪気が 一箇所に結集した病や、その様な異常が起こった所に防衛の為の衛気が集まり過ぎた病や、手足の病や、それが痺れて痛む病や、 湿気を主力とする風・寒・湿の気に中てられて、血や気の流れが滞り、その為に痛んだり、痺れたりする湿痺の病を治す。 ◆酸棗仁を毎日服用すると肝・腎・脾・肺・腎の五臓の働きを安らかにし、徐々に身の動きが軽くなり、年齢を延ばせる様になる。 ※ |
|
| に | ニオイコブシ→コブシに記載 | ||||
| 植物名{ニワトコ} 《生薬名》 接骨木(せっこつぼく)=茎 接骨木根(せっこつぼくこん)=根 接骨木葉(せっこつぼくよう)=葉・若枝 接骨木花(せっこつぼくか)=花 《気味》 |
スイカズラ科 | 花・根・茎・ 葉・若枝 |
●活血作用 ●鎮痛作用 ●発汗作用 ●利尿作用 ●骨接 ●挫傷 ●関節炎 ●筋骨疼痛 ●腎炎 ●水腫 ●痛風 ●打撲 ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆接骨木葉は、活血・鎮痛・利尿薬とし、骨接・挫傷・関節炎・筋骨疼痛・腎炎・水腫・痛風などに、
1日3〜10gを煎剤として内服又は罨法剤として用いる。 ◆接骨木及び接骨木根は、鎮痛・利尿薬とし、リウマチ・水腫・打撲・挫傷・筋骨疼痛などに、1日3〜10g 煎剤又は茶剤として用いる。 ◆接骨木花は、発汗薬として感冒などに、1日3〜10g 煎剤又は茶剤として用いる。 ◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ |
|
| 動物名{ニワトリ} 《生薬名》 鶏子黄(ケイシオウ)=卵黄 鶏子白(けいしはく)=卵白 鶏子穀(ケイシコク)=卵殻 《気味》 卵白=甘微寒 |
キジ科 | ● ● ● ● 卵白=●接合作用 ●etc・・・・・・・ |
◆鶏子黄よく、火瘡、癇痙の熱を除くことを主どる。 ◆鶏子黄、熱を鎮め煩を去る。 ◆鶏子白、目熱血痛、心下の伏熱を除き、煩満、ガイ(亥+欠)逆、小児下泄をとどめ、婦人産難にて胞衣の出でざるは、並び 生にて之を呑む。醋に浸すこと一宿したるものは黄疸を療して大煩熱を破る。 蛋白は、皮膚や膜の刺戟を緩和し、外より保護するの効あり。 ◆配合される漢方薬=黄連阿膠湯・排膿散・百合鶏子湯・・・・・ ◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ |
||
| 人参三七(にんじんさんしち) →サンシチニンジンに記載 |
|||||
| 人参(にんじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 忍冬(にんどう)→スイカズラに記載 | |||||
| ぬ | |||||
| ね | |||||
| の | |||||
| は | 梅寄生(ばいきせい) →コフキサルノコシカケ |
||||
| は | 白頸蚯蚓→ミミズに記載 | ||||
| は | 檗木→キハダに記載 | ||||
| 馬蹄決明→エビスグサに記載 | |||||
| 白参(はくじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 白刀豆(はくとうず) →ナタマメに記載 |
|||||
| 昆虫名{蜂} 《生薬名》 露蜂房(ろほうぼう)=巣 蜂房(ほうぼう)=巣 蜂腸(ほうちょう)=巣 《気味》 |
|||||
| 八月札(はちがつさつ) →アケビに記載 |
|||||
| 撥草(ばちぐさ)→ナズナに記載 | |||||
| 波知春(はちす)→ムクゲに記載 | |||||
| 植物名{ハッカ} 薄荷(はっか)=葉 《気味》 辛温 |
シソ科 | 葉 | ●芳香性健胃薬 ●駆風薬 ●解熱 ●発汗 ●etc・・・・・・・ |
◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ ※手の太陰、足の厥陰に入る。賊風傷寒に汗を発す。悪気・心腹脹満・霍乱・宿食不消化・下気。煮汁を服すれば 汗を発し、大いに労乏を解す。 ※咽喉・口歯の諸病を利す。各種でき物。汁でうがいすれば、舌胎・語澀を去る。蜂・蛇の毒。頭・目を清くし、風熱を除く。 |
|
| バッ(草冠+抜)カツ(草冠+契) (ばっかつ)→サルトリイバラに記載 |
|||||
| 植物名{ハトムギ} 《別名》 四国麦(しこくむぎ) 鳩麦(はとむぎ) 《生薬名》 ヨク(草冠+意)苡仁(よくいにん) =種皮去種子 ヨク(草冠+意)米(よくべい) =種皮去種子 苡米(いべい)=種皮去種子 《気味》 甘微寒 |
イネ科 | 種子 種皮去種子 根 |
〈ヨク(草冠+意)苡仁〉 ●浮腫●水イボ ●高血圧症●糖尿病 ●水太り●疼痛 ●肌荒れ●滋養強壮 ●排膿作用●清熱作用 ●消炎作用●鎮痛作用 ●肌荒れ●皮膚病 ●免疫賦活作用 〈根〉 ●リウマチ ●神経痛 ●肩凝り ●胃痛 ●胃潰瘍 ●咽喉痛 ●etc・・・・・・・ |
◆ヨク(草冠+意)苡仁は、筋がつまり、痙攣して引きつり、曲げることも伸ばすことも出来ない者や、久風湿痺を治し、気を下す。 ◆浮腫や疼痛には、ヨク(草冠+意)苡仁10〜30gを水400cc〜600ccと共に半量になるまで弱火で煎じ、1日3回に分けて服用する。 粉末の場合は1日3回、1回量1〜2gを服用する。 ◆ヨク(草冠+意)苡仁は、健胃、解熱、利尿、解毒の効果があり、慢性胃腸炎、潰瘍、下痢、リウマチや神経痛の痛みに、又は イボ取りと美容効果がある。それには、ヨク(草冠+意)苡仁20〜30gを煎じて服用する。 ◆リウマチ、神経痛、肩凝りに乾燥した根1日10〜15gを煎じて服す。 ◆鎮咳には根1日10gを煎じて服す。 ◆のどの痛みには、根の煎汁でうがいをする。 ◆駆虫に、根を煎じてお茶代わりに服用すると効があると言われている。 ◆ハトムギ酒の作り方 ハトムギ300gとホワイトリカー1.8Lで漬ける。 ◆急を緩め熱を消し、和を致す効果がある。だから胸痺・肺癰・風濕・腸癰等に用いられる。 ※ハトムギとジュズダマはジュズダマ属のイネ科なのでよく似ていますが、生薬のヨク(草冠+意)苡仁はハトムギで、 生薬の川穀はジュズダマです。 |
|
| 半夏(はんげ)→カラスビシャクに記載 | |||||
| 番瀉実(ばんしゃじつ)→センナに記載 | |||||
| 番瀉葉(ばんしゃよう)→センナに記載 | |||||
| 植物名{バンジロウ} 番石榴(ばんせきりゅう) 蕃果(ばんか)=果実 バンザクロ=果実 グァバ=葉 《気味》 甘 |
フトモモ科 | 果実 葉 |
●下痢 ●糖尿病 ●肥満予防 ●大腸癌予防 ●打撲傷 ●etc・・・・・・・ |
◆打撲傷に新鮮な葉の汁を塗布する。 ◆葉を1日量15g〜と、お水700ccと共に煎じ、1日3回に分けて食後に服用する。 ◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ ※シジウムとグァバは同類のシジウム属ですが、同じ物ではございません。 |
|
| 反鼻(はんび)→マムシに記載 | |||||
| ひ | 植物名{ヒガンバナ} 《別名》 マンジュシャゲ シビトバナ ホトケバナ ハカバナ 《生薬名》 彼岸花(ヒガンバナ) 彼岸根(ヒガンコン) 石蒜(セキサン) 《気味》 |
ヒガンバナ科 | 鱗茎 | ●肩こり ●浮腫 ●乳腺炎 ●いんきん ●タムシ ●ぜにたむし ●関節の腫れ ●関節炎 ●etc・・・・・・・ |
◆肩こり、浮腫などに鱗茎をすり下ろし、ひとさし指大の分量を就寝前に両足の土踏まずに貼りつけます。
唐胡麻の皮を去り彼岸根と(小麦粉を添加剤として用いても良い)同分量を砕いて一緒に貼ると更に効果が増します。 ◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ ※大昔は服用されていましたが、毒性が強いため現在では外用のみとされています。絶対に服用しないで下さい。 ※外用剤でも毒草なので、肌荒れ、ただれのする事が有りますので、注意して用いましょう。 |
| 蓖麻子(ひまし)・ヒマシ油 →唐胡麻に記載 |
|||||
| 植物名{ビワ} 枇把葉(びわよう) 《気味》 |
バラ科 | 葉 | ●あせも ●打撲 ●捻挫 ●胃腸病 ●疲労回復 ●食欲増進 ●etc・・・・・・・ |
◆あせもには葉3枚を取り、水500ccと共に煮出し、冷めた汁で患部を洗う。 ◆打撲や捻挫には葉30枚を取り、水洗いして刻み、水気を取り、葉を瓶に入れ、葉がかくれるまでお酒を入れる。2〜3週間漬け 込みんだ後、脱脂綿に浸して患部にあて、その上から乾いたタオルなどをのせてカイロなどで暖める。 ◆咳や胃腸病には葉2枚ほどを水400cc と共に半量まで煎じ日に3回に分けて服用する。 ◆疲労回復や食欲増進には、ビワ酒を作り、それを1日3回に分けて服用する。 |
|
| ふ | 植物名{フジバカマ} 蘭草(らんそう) 布知波賀万(ふじばかま) 藤袴(ふじばかま) 《気味》 |
キク科 | 全草 | 利尿 通経 黄疸 皮膚の痒み 糖尿病 etc・・・・・・・ |
◆皮膚の痒みに浴剤として全草300〜500gを刻み、布袋などに入れて煎じるか袋ごとお風呂に入れる。 ◆糖尿病には蘭草と連銭草と枇杷葉とタラノキの樹皮、各5gと水400ccと共に弱火で半量まで煎じ、日に3回に分けて服用する。 |
| 不換金(ふかんきん)→ サンシチニンジンに記載 |
|||||
| 蝮蛇(ふくだ)→マムシに記載 | |||||
| フシグロ→王不留行に記載 | |||||
| 傅致膠(ふちこう)→ロバに記載 | |||||
| へ | 植物名{ベニバナ} 《生薬名》紅花(こうか)=管状花 紅藍花(こうらんか)=管状花 臙脂花(えんしか)=管状花 紅花油(べにばなゆ)=種子の脂肪油 《気味》 苦平 |
キク科 | 管状花 種子の脂肪油 |
●更年期障害 ●便秘 ●血の道症 ●腹痛 ●産前産後病 ●頭痛 ●めまい ●肩こり ●のぼせ ●冷え症 ●血行障害 ●月経不順 ●通経 ●月経不通 ●打撲症 ●オ(ヤマイダレ+於)血症 ●腫瘍 ●排尿困難 ●駆オ(ヤマイダレ+於)血薬 ●脳出血 ●脳溢血 ●脳卒中 ●半身不随 ●高コレステロール症 ●動脈硬化症 ●冠動脈不全 ●ネフローゼ ●心筋梗塞 ●小便不利 ●神経痛 ●関節リウマチ ●血圧効果作用 ●免疫賦活作用 ●抗炎症作用 ●etc・・・・・・・ |
◆東洋医学では、通経・駆?血薬とし、月経不順・冷え症・産前産後病・更年期障害・その他の婦人病・心筋硬塞・
ネフローゼ・血行障害・便秘・頭痛・神経痛・リウマチ・小便不利などに用いられます。 紅花 1日3〜10g を煎じて温かいうちに服用する。 ◆紅藍花は、血液の流れを良くし、ドロドロとして停滞している?血を取り除く。 ◆婦人の者で、頭痛・めまい・肩こり・のぼせ・腹痛などの症候が有り、又は血の道症で常に腹痛し治らない者、紅藍花酒が良い。 ◆ガーゼ等に紅花30〜40gを入れて、お酒1.8Lと共に2ヶ月程漬け込み服用する。 ◆種子の脂肪油には、リノール酸が70%も含まれていますので食用油として使用すると、血液中のコレステロール濃度の低下・ 高コレステロール症による脳出血・冠動脈不全・動脈硬化などの予防に効果があると言われています。服用する時は1回0.5〜1g。 ※古来紅色の染料として使われ、口紅にも使用され、安全な着色料として現在も盛んに使用させています。 |
| ぺんぺん草→ナズナに記載 | |||||
| ほ | 防已→ツヅラフジに記載 | ||||
| 植物名{ホオノキ} 厚朴(こうぼく)=樹皮 |
etc・・・・・・・ |
◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ ※厚朴の配合されている方剤をひどい虚証の者には与えてはならない。虚がひどくなるから |
|||
| 蒲公英(ほこうえい) →タンポポに記載 |
|||||
| 蒲公英根(ほこうえいこん) →タンポポに記載 |
|||||
| 蒲公草(ほこうそう) →タンポポに記載 |
|||||
| 牡蠣(ぼれい)→カキに記載 | |||||
| ま | 植物名{マタタビ} 《生薬名》 木天蓼(もくてんりょう)=虫瘤 《気味》 |
マタタビ科 | 虫瘤 | ●etc・・・・・・・ |
◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ ◆ ◆ ※花が開く直前、花の中心の子房に、マタタビミタマカという昆虫が産卵すると、子房は正常な 果実に成れず、発育異常を起こし、凹凸(横突)した虫瘤状の物に成る。 ※晩秋に虫瘤状に成った果実を採取し、熱湯又は蒸気を通して幼虫を殺し、天日で充分乾燥させる。 |
| 爬虫類名{マムシ} 《生薬名》 反鼻(はんび)=内臓除去物 蝮蛇(ふくじゃ)=内臓除去物 五八霜(ごはっそう) 《気味》 甘温 |
クサリヘビ科 | 内臓.皮膜 除去物 胆 |
●強壮薬 ●興奮薬 ●疲労回復作用 ●滋養強壮作用 ●冷え症 ●扁桃腺炎 ●打撲 ●切り傷 ●神経痛 ●歯痛 ●腫れ物 ●眼病 ●化膿 ●解熱薬 ●痔疾患 ●腹痛 ●手足の痺れ ● ● ● ● ● ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆小児で虚弱の夜尿症に5㎝ほどを炙って長期間食べさせると良い。 ※鼻血がぬけたり、夜驚症等の症状がみられたら、すぐに中止する。 ◆強壮・興奮薬として疲労時・冷え症・肺病等に乾燥させた物を粉状にし、それを1日3〜6g服用。 または黒焼きにして服用する。 ◆マムシを乾燥させて粉末にし、黒焼きにした物を、切り傷・化膿性腫瘍に外用する。 ◆生の物を焼いて食すと…作成途中…。 ◆マムシの骨を乾かして煎じて服用すると、解熱作用があり、骨を黒焼きにして粉末にし、赤痢に用いる。 ◆マムシの皮を乾燥させた物は、打撲・神経痛・腫れ物・膿の吸い出し等に、患部に貼る。 また皮を灰にして疔腫・悪瘡・骨疽を療ず。…作成途中… ◆…作成途中…マムシ酒の服用。外用としては扁桃腺炎・打撲・切り傷・神経痛・歯痛 ◆蝮蛇肉を酒に…作成途中… ◆蝮蛇脂を綿で包み、耳に詰めれば聴力障害に良く、腫毒には塗布する。 ◆マムシの胆を乾燥させた物は、疲労・腹痛・眼病などに服用する。 ◆マムシの抜け殻は、身体のかゆみ・疥癬などに用いる。…作成途中… ◆マムシの糞を…作成途中… ◆蝮蛇を酒に醸して用いれば癩疾・諸瘻・心腹痛を療じ、結気を下し、蟲毒を除く。 …作成途中…マムシ酒を塗布すれば打撲に良い。 ◆五痔・腸風瀉血を治す。 …作成途中… ◆大風・諸悪風・悪瘡・瘰癧・皮膚の頑痺・半身枯死・皮膚手足臓腑間の重疾を主るとして、マムシ1匹を生きたまま器に入れ、 度数の高い酒1斗を注ぎ、馬が排尿する場所に埋める。1年後に取り出して服用する。 ※マムシの上顎にある2本の毒牙の根もとには毒腺があり、その牙の中は注射器の様に管状で牙の先 に毒液を出す穴があります。 マムシの毒は血液毒で、咬まれると血管組織・内臓などにも作用し、局所的に出血や腫脹を生じ、 多くの場合激痛を伴い、次第に腫れと痛みが全身に広がり、急性腎不全を起こして死亡することがあるので、捕まえる時は充分に 注意しなければなりません。 もしも咬まれた時は、慌てて動き回ることなく咬まれた所より10cm程離れた心臓に近いところを 包帯などで縛り(決して強く縛らず、口で吸い出さず、切開や冷却などもしない)、救急車を呼んで下さい。 |
|
| キノコ名{マンネンタケ} 《別名》 霊芝草(れいしそう) 幸茸(さいわいたけ) 門出茸(かどでたけ) 《生薬名》 霊芝(れいし) 《気味》 赤芝=苦平 黒芝=鹹平 青芝=酸平 白芝=辛平 紫芝=甘温  |
マンネンタケ科 | 全体 | ●抗癌作用 ●抗腫瘍薬 ●鎮静薬 ●鎮痛作用 ●神経衰弱 ●不眠症 ●消化不良 ●咳嗽 ●強壮薬 ●抗炎症作用 ●高コレステロール血症 ●動脈硬化症 ●悪性腫瘍 ●滋補強壮作用 ●肝臓保護作用 ●免疫機能増強 ●白血球増加作用 ●鎮咳作用 ●去痰作用 ●慢性気管支炎 ◆利尿作用 ●老人性気管支喘息 ●白血球減少症 ●冠状動脈硬化性心臓病 ●不整脈 ●ノイローゼ ●胃潰瘍●消化不良 ●更年期障害 ●etc・・・・・・・ |
◆古い梅や桃の木の根元に寄生するキノコ。 ◆キノコの中でもマンネンタケが抗癌作用が高いとされる。 ◆胸の中に血や気が滞って結ぼれる病。 ◆心臓の働きを増し、内蔵の機能を補い、脳の働きが良くなり思考力を増し物事を忘れないようにする。 ◆身体が軽くなり老いる事少なく長生きが出来る。 ◆霊芝には六種類の芝が有る。赤芝(せきし)・黒芝(こくし)・青芝(せいし)・白芝(はくし)・黄芝(おうし)・紫芝(しし) ◆癌には、霊芝を5〜20gと水600mlを土瓶に入れ、弱火で半量になるまで減らして滓を取り去り、 1日3回に分けて食前又は食間に温めて服す。 ◆肝臓疾患、更年期障害には1日量2.5〜5gを煎じて服用する。 ◆煎じ液が飲みにくい者は、霊芝を末とし、錬蜜で和して丸とし、噛んで食べる。 ◆霊芝の特徴=茎から傘が開く形状で傘に光沢がある。 梅寄生の特徴=茎をのばさず樹幹から直接傘を開き子実体をつけ、 その形状がまるで猿が樹木の背にもたれかかり腰かけているかの如し。 ◆昔、霊芝はサルノコシカケ科とされていたが、近年はマンネンタケ科に属することがわかった。 |
|
| み | 環形動物名{ミミズ} 《生薬名》 地竜(じりゅう)=全体 地龍(じりゅう)=全体 蚯蚓(きゅういん)=全体 地竜干(じりゅうかん)=全体 乾地竜(かんじりゅう)=全体 白頸蚯蚓(はくけいきゅういん)=全体 《気味》 |
フトミミズ科 | 全体 | ●解熱薬 |
◆傷寒、瘧疾 ・・・・・・・作成途中・・・・・・ |
| 霊芝(れいし)→マンネンタケに記載 | |||||
| む | 植物名{ムクゲ} 《別名》 波知春(はちす) 木波知春(きはちす) 朝貌(あさがお) 《生薬名》 木槿皮(もっきんび・もくきんぴ) =茎・幹・根の樹皮 槿皮(ちんび)=茎・幹・根の樹皮 木槿花(もっきんか・もくきんか)=花 槿花(ちんふぁ)=花 木槿子(もっきんし・もくきんし)=果実 木槿根(もっきんこん・もくきんこん) =根 木槿葉(もっきんよう・もくきんよう) =根 《気味》 |
アオイ科 | 茎・幹・根の樹皮 花 果実 |
●白癬菌●水虫 ●タムシ●皮膚病 ●胃腸炎●下痢 ●抗菌作用●胃腸カタル ●脳出血●嘔吐 ●頭痛●偏頭痛 ●咳●出来物●こしけ ●帯下●下り物●痔 ●etc・・・・・・・ |
◆木槿皮・槿皮は、抗菌作用があり胃腸薬や水虫など皮膚炎の薬に配合される。 ◆木槿花・槿花は、皮膚炎、胃腸炎、下痢止め等に用いる。 ◆下り物が多い時に、ムクゲの花の蕾を摘みとって陰干し、その乾燥花10gと水600ccと共に半量になるまで煎じ、 1日3回に分けて服用する。 ・・・・・・・作成途中・・・・・・ |
| 植物名{ムラサキ} 《生薬名》 紫根(しこん)=根 紫草(しそう)=根 紫丹(したん)=根 紫オウ(草冠+夭)(しおう)=根 《気味》 苦寒 |
ムラサキ科 | 根 | ●しみ ●アザ ●吐血 ●喀血 ●嘔血 ●血尿 ●下血 ●外傷 ●切り傷 ●すり傷 ●汗疱状白癬 ●悪性腫瘍 ●やけど ●凍傷 ●湿疹 ●水胞 ●便秘 ●黄疸 ●解毒作用●涼血作用 ●活血作用●清熱作用 ●抗腫瘍作用 ●浮腫抑制作用 ●抗炎症作用 ●強心作用 ●解熱作用 ●抗真菌作用 ●抗ウイルス作用 ●麻疹予防薬 ●円形脱毛症 ●水虫 ●麻疹の解熱 ●etc・・・・・・・ |
◆主に胸やお腹辺り病や、邪気に依って生じた病や、五臓に熱がこもって起こる五疸の病を治します。 ◆内臓の機能を補い、元気を増し、九竅の働きを良くし、体内の水分の巡行系統である水道に滞りが有ればそれを通じさせる作用が有ります。 ◆紫根を1日量3〜10g 煎じて服用する。 ◆麻疹の解熱や解毒に3〜6gを煎じて服用します。 ◆紫根水の作り方は、紫根15gと水300mlを土瓶に入れ、弱火で15分位煮込みます。 そして熱いうちに茶こしでこし、冷めたら出来上がりです。 ※出来るだけ新鮮な紫根水を付けるようにしましょう。 ※この紫根水をお風呂に入れ、浴剤として使うと、とても効果的です。その時はもう少し紫根の量を増やして煎じて下さい。 ◆外用に持ちいたい時は紫雲膏という漢方軟膏剤が有ります。 この軟膏剤はベト付きがありますが、紫根水よりも持続性が高いのでこちらがお勧めです。 湿疹(全身)・やけど・しもやけ・水虫・しみ・そばかす・脱毛症・耳の炎症・鼻の炎症・痔など、 あらゆる皮膚疾患に驚くほど良く効きます。 |
|
| め | |||||
| 綿茵陳(めんいんちん) →カワラヨモギに記載 |
|||||
| も | 木槿花(もっきんか・もくきんか) →ムクゲに記載 |
||||
| 木槿根(もっきんこん・もくきんこん) →ムクゲに記載 |
|||||
| 木槿子(もっきんし・もくきんし) →ムクゲに記載 |
|||||
| 木槿皮(もっきんび・もくきんび) →ムクゲに記載 |
|||||
| 木槿葉(もっきんよう・もくきんよう) →ムクゲに記載 |
|||||
| 艾(もぐさ)→ヨモギに記載 | |||||
| 木通(もくつう)→アケビに記載 | |||||
| 木通根(もくつうこん)→アケビに記載 | |||||
| 植物名{モクレン} 《生薬名》 辛夷(しんい)=蕾 《気味》 |
モクレン科 | 蕾 | ・・・・・・作成中・・・・・・・ | ||
| 植物名{モモ} 《生薬名》 桃仁(とうにん)=種子 白桃花(はくとうか)=シロバナモモ花蕾 桃花(とうか)=花蕾 白桃葉(はくとうよう)=葉 桃葉(とうよう)=葉 《気味》 |
バラ科 | 種子 花蕾 葉 |
<桃仁> ●更年期障害 ●鎮咳去痰薬 ●消炎性 駆オ(ヤマイダレ+於)血薬 ●通経緩下薬 ●排膿作用 ●抗炎症作用 ●抗凝血作用 ●血小板凝集抑制作用 ●血の道症 ●月経不順 ●便秘 ●あせも ●下腹部の膨満感 ●腹部の血液停滞 ●etc・・・・・・・ <白桃花> ●利尿作用 ●緩下薬 ●etc・・・・・・・ <桃葉> ●腹痛 ●下痢 ●あせも ●汗疹 ●etc・・・・・・・ |
◆桃仁は駆オ(ヤマイダレ+於)血薬・鎮痛・消炎・解毒・緩下薬として、血の道症・月経不順・月経痛・無月経・
産後の腹痛・更年期障害・打撲・捻挫などによる内出血・疼痛・便秘・頭痛などに用います。 1日量3〜5gを煎じて服用します。 ◆漢方では、利尿・活血・緩下薬として、白桃花を乾燥させ、1回量2〜3gを煎じて服用します。 ◆あせもには新鮮な葉を取り、水洗いして500gをお風呂に入れて・・・・・。 ◆桃葉は解熱作用・去痰作用・利尿作用・緩下作用・鎮静作用があり、慢性の気管支炎に用います。新鮮な桃葉 1日量30〜50g 煎じて、3回に分けて服用。 ◆桃仁はオ(ヤマイダレ+於)血を去り、血の乾きを潤し、血液のめぐりを良くし、しこりの病を主治する。実熱の血証を主る。 ※アンズの種子の杏仁から杏仁水が作られ、鎮咳去痰薬として用いられますが、桃仁も杏仁水の代用として用いることができます。 しかし漢方的には鎮咳薬として使う事はなく、用途が異なります。 ※緩下作用があるので、妊婦の者は注意して服用しなければなりません。 |
|
| 問荊→つくしに記載 | |||||
| や | 野梧桐→アケビに記載 | ||||
| 野山参(やさんじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| 植物名{ヤマノイモ} 《別名》 ジネンジョウ 山芋(やまいも・さんう) =根茎(周皮除去) 山の芋(やまのいも)根茎(周皮除去) 自然薯(じめんじょ) =根茎(周皮除去) 自然生(じねんじょう) =根茎(周皮除去) 淮山芋(わいさんう) =根茎(周皮除去) 《生薬名》 山薬(さんやく) =根茎(周皮除去) 薯蕷(しょよ) =根茎(周皮除去) 《別名》 《気味》 薯蕷=甘温 |
ヤマノイモ科 | 根茎(周皮除去) | ●滋養強壮作用 ●強精作用 ●止瀉作用 ●鎮咳去痰作用 ●止渇作用 ●etc・・・・・・・ |
◆傷中を主る。虚羸を補し、寒熱邪気を除き、中を補し、気力を益し、肌肉を長じる。久しく服すれば耳、
目を聡明にし、身を軽くし、飢えず長生きをする。 ◆腎を益し、脾、胃を健やかにし、泄利を止め、痰涎を化し、皮、毛を潤す。 ◆堅く腫れている出来物には、生をすり潰して貼りつける。 |
|
| ゆ | 熊胆(ゆうたん)→クマに記載 | ||||
| 養参(ようじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| よ | ヨク(草冠+意)米→ハトムギに記載 | ||||
| ヨク(草冠+意)苡仁(よくいにん) →ハトムギに記載 |
|||||
| 預知子(よちし)→アケビに記載 | |||||
| 植物名{ヨモギ} 《生薬名》艾葉(がいよう)=葉及び枝先 艾(もぐさ)=葉裏毛 熟艾= 生艾= 《気味》 |
キク科 | 葉 枝先 葉裏毛 |
●吐血 ●下血 ●鼻血 ●冷え症 ●痔疾患 ●傷寒病 ●咽喉痛 ●歯痛 ●湿脚気 ●etc・・・・・・・ |
◆傷寒・吐血・下血などには艾葉を煎じて服用する。 ◆咽喉腫痛には生葉を搗いた汁を服用する。 ◆鼻血が止まらない時は艾葉の灰を鼻に吹き入れる。 ◆歯痛には艾葉を焼いた煙で鼻や口の中を薫じる。 ◆老人で丹田の気が弱い者や臍腹に冷えを感じる者には、熟艾を布袋に入れた物で臍腹を覆い温める。寒湿脚気には靴下の裏に挟む。 ◆冷え症や痔疾の者には乾燥した葉で座布団や腰当てを作ると良い。 ※下痢・吐血・下部のちく瘡・婦人の漏血を止め、陰気を利し、肌肉を生じ、風寒をしりぞけ、人に子を有らしめる。 ※艾葉を用いるには、長くく置いた古い物を修治し、細軟にして用いなければならない。これを熟艾と言います。 生艾を用いて灸すれば、肌脈を傷める。だから孟子に七年の病に三年の艾が好ましい。 ※艾は疾をおさめ得るもので、久しく経ったものほど善い。 |
|
| ら | 蘭草→フジバカマに記載 | ||||
| り | 植物名{} 《生薬名》 竜脳(りゅうのう) 《気味》 |
◆・・・・・・・作成中・・・・・・・ | |||
| 龍落子→タツノオトシゴに記載 | |||||
| 遼東参(りょうとうじん) →オタネニンジンに記載 |
|||||
| る | |||||
| ろ | 動物名{ロバ} 《別名》 ウサギウマ 《生薬名》 阿膠(あきょう)=黒驢除毛煮皮製 傅致膠(ふちこう)=黒驢除毛煮皮製 《気味》 甘平 |
ウマ科 | 驢除毛煮皮製 |
●補血薬 ●止血薬 ●子宮出血 ●不眠 ●神経衰弱 ●肺結核の喀血 ● ● ● ● ●etc・・・・・・・ |
◆胸や腹中の六腑の力が衰え、締まりが弱まり疲れ衰え、内臓に出血があり、水を浴びたようにゾクゾクと悪寒し、
瘧状の病の様に腰やお腹が痛み、手足が痺れて痛む病や、、女性の陰部からの下血を治す。また、産中の胎児の発育を安らかにし、
常服すれば身を軽くし、元気を益す。 ◆肌肉の傷れを治し、急を緩める事を主る。だから出血を止め苦しみを去る。 ◆1日量 3〜15gを溶かして服用。 ※阿膠は、消化しにくく胃腸障害が起こりやすいので、胃腸が元々弱い者・食欲不振・嘔吐・下痢などの者には用いない。 (服用中に食欲不振・胸焼け・吐き気・下痢などの胃腸障害がおこる方は服用を中止して下さい。 ※牛皮を製する事もある。 ※悪臭がする物は下品とする。 ※この原料となる動物は牛・豚・鯨などである。 |
| ● | ◆ | ||||
| わ | ● | ◆ |