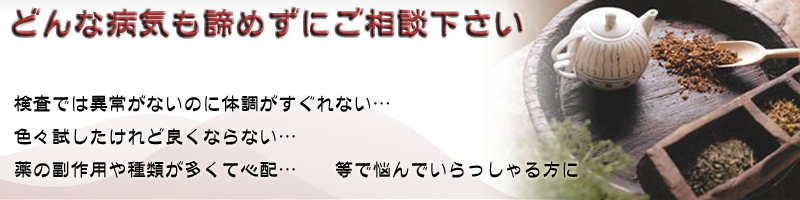
漢方相談無料メールと問診票・どんな病気も諦めずご相談下さい!漢方薬専門店
佐々木漢方薬店ホームページ
山口県岩国市元町2丁目1番18号 佐々木ビル1階 TEL・FAX(0827)23-0873
山口県岩国市元町2丁目1番18号 佐々木ビル1階 TEL・FAX(0827)23-0873
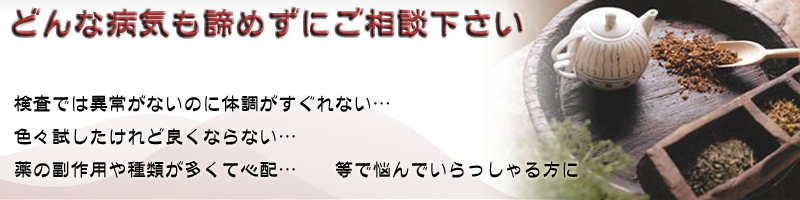
傷寒雑病論・解説・目次
傷寒雑病論・解説・目次
※ 突然の解説変更ございます。
お伺いします、飲病には四種類あるそうですがどういうのを言うのですか。
師曰はく、痰飮有り懸飮有り溢飮有り支飮有り。
師匠が言われるには、痰飲が有り、懸飲が有り、溢飲が有り、支飲が有る。
(2)問ふて曰はく、四飮何を以て異なりと為す。
お伺いします、四飲はどう違うのですか。
師の曰はく、其の人素盛ん今痩せ水腸間を走りて瀝瀝と聲有り、之を痰飮と謂ふ。
師匠が言うには、その病人は元々体格がよく元気で丈夫だったが、今では痩せて水が腸の間を走り、
その為に胃や腸から水の音がする。これを痰飲(胃)という。
飮後水流れて脇下に在りガイ(亥+欠)唾引痛す、之を懸飮と謂ふ。
水を飲んだ後、その飲んだ水が脇に在り、咳をすると痰が出て、咳をする度に脇下へ引かれる様に痛むのを懸飲(肝)という。
飮(後)水流行して四肢に歸し當に汗出づべくして汗出で不身体疼重する、之を溢飮と謂ふ。
水を飲んだ後、飲んだ水が腕や足に回り(浮腫)、当然汗が出るはずなのに汗が出ず、身体が痛んで重いのを溢飲(脾)という。
ガイ(亥+欠)逆倚息短氣臥することを得ず、
咳がこみ上げてきて横になることが出来ず、物などに寄りかかって息をし、息が切れて寝ることが出来ず、
其の形腫れたるが如きを、之を支飮と謂ふ。
その病人の外観が、水気有り浮腫んでいる様に見えるのを支飲(肺)という。
(3)水心に在れば、心下堅築短氣水を惡み飮むを欲せ不。
水が心臓に在れば、心下堅くなり息切れがして水を嫌がり飲みたがらない。
(4)水肺に在れば、涎沫を吐き水を飮まんと欲す。
水が肺に在れば、薄い痰を吐き、水を飲みたがる。
(5)水、脾に在れば、少氣し身重し。
水が脾臓に在れば、呼吸に力がない為深く息を吸い込むことが出来ず身体が重い。
(6)水、肝に在れば脇下支滿嚏して痛む。
水が肝臓に在れば、脇腹が突っかい棒でもされている様に張り咳や欠伸やクシャミをすると響いて痛む。
(7)水、腎に在れば心下悸す。
水が腎臓に在れば、みぞおちで動悸する。
(8)夫れ心下に留飮有れば其の人背寒冷なること手大の如く。
もし胸下に捌けない水が有れば、その人の背中に冷え冷えと冷たく感じる。 その範囲は手の平の大きさくらいである。
(9)留飮の者は、脇下痛み缺盆に引きガイ(亥+欠)嗽すれば則ち輙ち已む。
留飲を病んでいる者は、脇腹が痛み、その痛みが鎖骨上窩辺りまで繋がってくる。
咳が出ると気が外に発散されその部位の痛みが止む。
(一に轉た甚だしに作る)
(逆に咳が出ると痛む。ではないだろうか。)
(10)胸中に溜飲有りその人短氣して渇し四肢歴節疼み脉沈なる者は、溜飲有り。
胸中に留飲の証候が有り、その人息切れして喉が渇き、腕や足の関節が次々と痛み、
脈沈(水が停滞すると脈は沈む)になっている者は、間違いなく留飲が有る。
(11) 膈上痰を病み満喘咳吐発すれば則ち寒熱背痛腰疼目泣自ら出で、
胸の辺りで痰を病んでいる為に胸の中が一杯に詰まった感じがしてゼェゼェと言い、
咳して吐けば寒気や発熱が起こり、背中が痛み、腰が疼き、目から涙がひとりでに出て、
その人身シン(目+門+王)劇しきは必ず伏飲有り。
ブルブルと体を震わせ劇しい人には必ず隠れ潜んでいる飲の病が有る。
(12)夫れ病人水を飲むこと多ければ必ず暴に喘満す。
そもそも病人が水を飲む量が多すぎれば、必ず急に劇しくゼェゼェし胸が一杯に満ちる。
凡そ食すること少なく飲むこと多ければ水心下に停まる。
誰でも食べるのが少なく飲物ばかり多ければ、水が心下に停まる(胃の陽気が少ないから)。
(食を陽と為し、水を陰と為す。)
甚だしき者は、則ち悸し微なる者は短気す。
食少飲多の劇しい者は動悸し、食少飲多の少ない者は息切れがする。
(13)脈雙弦の者は寒也。皆大いに下して後裏虚す。
脈が左右両手共に弦の者は、寒によるものである。これは全部大いに下した為に裏が虚したからだ。
脈偏弦の者は飲也。
脈が片方だけ弦の者は、水を飲んで冷えたからだ。
(14)肺飲は弦ならず但喘短気を苦しむ。
肺飲は、飲の病だが弦脉を生じない。但だゼェゼェとし息が切れるだけだ。
(15)支飲も亦喘して臥する能は不加うるに短気し其の脈平也。
支飲の病もまたゼェゼェして寝る事が出来ない。その上息切れがし、その脈は余り特徴のない脈である。
(16)病痰飲の者は、当に温薬を以って之を和すべし。
病が痰飲の者(陽気不足)は、当に温薬をもってその寒を収めてやれ。
(17)心下に痰飲有り胸脇支満目眩するは、苓桂朮甘湯之を主どる。
心下に痰飲が有る為に胸脇が突っかい棒でもされている様に張り目眩がする者は、
苓桂朮甘湯が中心となる。
茯苓桂枝白朮甘草湯の方 茯苓四両 桂枝三両 白朮三両 甘草三両
茯苓桂枝白朮甘草湯(苓桂朮甘湯)の作り方 茯苓4g 桂枝3g 白朮3g 甘草2g
右の四味を水六升を以って煮て三升を取り分温三服す。小便則ち利す。
右の四味と水240ccをもって煮て120㏄を取り、一日三回に分けて温め服す。そうすれば小便がよく出る。
(18)夫れ短気微飲有り当に小便從り之を去るべし。苓桂朮甘湯之を主どる。
現在息切れして少し心下に水有る者は、小便から水を去りなさい。これには苓桂朮甘湯が中心となる。
(方見上)腎氣丸亦之を主どる(方見婦人雑病中)
八味腎気丸もまた小便から水を去ってくれる。(後方の婦人雑病19項を見よ)
(19)病者脈伏し其の人自利せんと欲するに返って快く利すると雖も心下続いて堅満なるは、
病人の脈が深く隠れてなかなか指に触れず、思っていた以上に気持ちよく小便が出ているにもかかわらず、
心下が張ってずっと堅満が続いているのは、
此れ留飲去らんと欲するが故と為す也。甘遂半夏湯之を主どる。
これは留まった水が自分から去ろうとしているからである。これには甘遂半夏湯が中心となる。
甘遂半夏湯の方 甘遂大者三枚 半夏十二枚(水一升を以って煮て半升取り滓を去る) 芍薬三枚
甘草指大の如く(一枚を炙る一本無)
甘遂半夏湯の作り方 甘遂0.3g 半夏1g(水40㏄と共に煮て20㏄を取り半夏を去ったもの) 芍薬1g 甘草0.7g
右の四味を水二升を以って煮て半升を取り滓を去り、蜜半升を以って薬の汁に和し煎じて八合を取り頓に之を服す。
右の四味と水60㏄をもって煮て20㏄にし滓を去り、蜂蜜20㏄を加えて
更に30㏄になるまで煮詰めてこれを頓服する。
(20)脈浮にして細滑なるは飲に傷らる。
脈が浮いて細く滑らかな者は、飲により傷つけられたのである。
(21)脈弦數なるは寒飲有り。冬夏は治し難し。
脈が弦で数なる者は、冷えた水が留まっている飲病が有る。冬と夏は治すのが難しい。
(冬は極寒で夏は猛暑、こういう極端な気候の時期は治すのが難しい。)
(22)脈沈にして弦なる者は懸飲内痛す。
脈が沈んで弦の者は、懸飲で脇腹が痛む。
(23)病懸飲の者は、十棗湯之を主どる。
懸飲の病の者は、十棗湯が中心となる。
十棗湯の方 芫花(熬る) 甘遂 大戟各等分
十棗湯の作り方 芫花火で熬る 甘遂 大戟各等分
右の三味を搗きて篩水一升五合を以って先ず肥大棗十枚を煮て八合を取り滓を去り、薬末を内れ、
右の三味を搗いて篩にかけ末とし、水60㏄と大棗4gをもって煮て半量を取り、滓を去って、先に搗いた三味の末を入れ、
強き人は一錢匕を服し、羸れたる人は半錢を服す。平坦に温めて之を服す。
元気で丈夫な人には1gを服させ、疲れやすく痩せて弱々しい人には0.5gを服さす。
朝食前の早朝(朝四時頃)に温めて服させなさい。
下ら不る者は明日更に半錢を加う。快下を得て後糜粥にて自ら養う。
服した後、大便が出ない者には次の朝0.5g与えなさい。
大便が気持ちよく出た後、よく煮つくした薄粥をすすらせれば元気になる。
(24)病溢飮の者、当に其の汗を發す。大青竜湯之を主どる。小青竜湯亦之を主どる。
溢飲(手足浮腫)の病の者には、当に汗をかかせなさい。大青龍湯が中心となるが小青竜湯もまたそうである。
大青竜湯の方 麻黄六両(節を去る) 桂枝二両(皮を去る) 甘草二両(炙る) 杏仁四十箇(皮と尖を去る)
生薑三両 大棗十二枚 石膏鶏子大の如く(砕く)
大青龍湯の作り方 麻黄6g節を去る 桂枝2g皮を去る 甘草火で炙る 杏仁2g皮を去り先の尖った芽を去る
生姜3g 大棗4g 石膏10g
右の七味を水九升を以って先ず麻黄を煮て二升を減じ上沫を去り諸薬を内れ煮て三升を取り、
滓を去り、温めて一升を服す。微似汗を取る。
先ず、麻黄と水360㏄と共に煮て80㏄減じて灰汁を取り去り、残りの六味を入れて120㏄にし滓を去り、
1回40㏄を温め服し、汗を少しだけかかせる。
汗多き者は、温粉にて之を粉す。
汗が出過ぎる者は、これ以上汗をかかせないよう、温かい米粉(小麦粉?麻黄根粉?)を
体に叩きながら付けてやりなさい。
小青竜湯の方 麻黄三両(節を去る) 芍薬三両 五味子半升 乾薑三両 甘草三両(炙る)
細辛三両 桂枝三両(皮を去る) 半夏半升(湯で洗う)
小青竜湯の作り方 麻黄3g節を去る 芍薬3g 五味子3g 乾姜3g 甘草3g火で炙る
細辛3g 桂枝3g皮を去る 半夏5g丸のまま湯で洗う
右の八味を水一斗を以って先ず麻黄を煮て二升を減じ上沫を去り諸薬を内れ三升を取り滓を去り、温めて一升を服す。
先ず麻黄と水400㏄と共に煮て80㏄減らし灰汁を取り去り、残りの七味を入れて煮て120㏄にして滓を去り、
1日3回に分けて温め服す。
(25)膈間支飲、其の人喘満、心下痞堅、面色リ(禾+勿+黒)、
支飲(水の停滞) が、胸腔と腹腔の間にある者は、ゼィゼィといって息がよく吸い込めず、心下が痞えて堅く、 顔色が黄黒く、
其の脈沈緊之を得て数十日。醫之を吐下して癒え不るは木防已湯之を主どる。
脈が沈緊で堅く、この様な症状になり数十日も経っていて、その間に医者が吐かせたり下したりしてみたが癒えない者は
木防已湯が中心となる。
虚なる者は即ち愈ゆ。実なる者は三日に復た発す。復た与えて癒え不る者は宜しく木防已去石膏加茯苓芒硝湯之を主どる。
症状が軽い者は直ぐに治るが、症状が重い者は一時的に治まるが、3日後に復た元に戻る。
もう一度木防已湯を与え、治らない者は、この処方では駄目だから木防已去石膏加茯苓芒硝湯を与えなさい。
木防已湯の方 木防已三両 石膏十二枚鶏子大の如く(砕く) 桂枝三両 人参四両
木防已湯の作り方 木防已3g堅い物を用いる 石膏10g 桂枝2g 人参4g
右の四味を水六升を以って煮て二升を取り分ち温めて再服す。
右の四味を水240㏄と共に煎じ80㏄まで煮つめて滓を去り、1日2回に分けて温め服す。
木防已加茯苓芒硝湯の方 木防已二両 桂枝二両 芒硝三合 人参四両 茯苓四両
木防已去石膏加茯苓芒硝湯の作り方 木防已2g 桂枝2g 芒硝4g 人参4g 茯苓4g
右の五味を水六升を以って煮て二升を取り滓を去り芒硝を内れ、再び微に煎じ分ち温めて再服す。微に利すれば則ち愈ゆ。
右の五味を水240㏄と共に煎じ80㏄まで煮つめて滓を去り、芒硝を入れて再び小し煎じ、
1日2回に分けて温め服す。少し小便が出れば治る。
(26)心下に支飲有り其の人冒眩を苦しむは沢瀉湯之を主どる。
心下に支飲が在る為に、いつも帽子をかぶっている感じで目眩を起こし苦しむ者は、沢瀉湯が中心となる。
沢瀉湯の方 澤瀉五両 白朮二両
沢瀉湯の作り方 沢瀉5g 白朮2g
右の二味を水二升を以って煮て一升を取り分ち温めて再服す。
右の二味を水80㏄と共に煎じて40㏄まで煮て滓を去り、一日二回に分けて温め服す。
(27)支飲胸滿する者は、厚朴大黄湯之を主どる。
支飲の病で胸満する者は、厚朴大黄湯が中心となる。
厚朴大黄湯の方 右の三味を水五升を以って二升をもて、分ち温め再服す。
厚朴大黄湯の作り方 厚朴10g 大黄6g 枳実2.8g
右の三味を水五升を以って煮て二升を取り分ち温めて再服す。
右の三味を水200㏄と共に煮て80㏄取り、一日二回に分けて温め服す。
(28)支飲息するを得不るは、テイ(草冠+亭)レキ((草冠+歴)大棗瀉肺湯之を主どる。
支飲の為に胸が苦しくて息が出来ない者は、テイ(草冠+亭)レキ((草冠+歴)大棗瀉肺湯が中心となる。
(29)嘔家本渇し渇する者は解せん欲すと為す。
元々吐き気の病が有る者が、喉が渇いて水を欲しがりだしたら、病が治ろうとしているが、
今反って渇せ不るは心下支飲有るが故也。小半夏湯之を主どる。
逆に喉が渇いていた者が渇かなくなってしまったのは、心下に支飲が有る為である。
そういう者には、小半夏湯が中心となる。
小半夏湯の方 半夏一升 生薑半斤
小半夏湯の作り方 半夏10g 生姜8g
右の二味を水七升を以って煮て一升半を取り分ち温めて再服す。
右の二味を水280㏄と共に煎じて60㏄まで煮詰めて滓を去り、一日二回に分けて温め服す。
(30)腹滿し口舌乾燥するは、此腸間に水気有り。已椒レキ(草冠+歴)黄丸之を主どる。
腹が満ちて口中や舌がパサパサに乾くのは、腸の間に水気が有る。已椒レキ(草冠+歴)黄丸が中心となる。
防已椒目テイレキ(草冠+亭)レキ((草冠+歴)大黄丸の方 防已二両 椒目二両 テイレキ(草冠+亭)レキ((草冠+歴)二両(熬る) 大黄二両
防已椒目テイレキ(草冠+亭)レキ((草冠+歴)大黄丸の作り方 防已1g 椒目1g テイ(草冠+亭)レキ(草冠+歴)1g 大黄1g
右の四味之を末とし蜜にて丸すること梧子大の如くし食に先立ち飲にて一丸を服す。日に三服す。稍増す。
右の四味を搗いて末とし、錬蜜にて0.3gの丸とし、食事より先に一回一丸を水またはお湯で服す。
一日三回服す。大便が出にくいようなら丸の量を少し増やしてやれ。
口中に津液有って渇する者は、芒硝半量を加う。
口舌乾燥している中で、口中に多少唾があり口渇する者は、芒硝0.5gを加えて丸とする。
(31)卒に嘔吐し心下痞し膈間に水有り眩悸する者は、小半夏加茯苓湯之を主どる。
急に嘔吐して心下が痞え、胃の辺りに水があり、目眩や動悸がする者は、小半夏加茯苓湯が中心となる。
小半夏加茯苓湯の方 半夏一升 生薑半斤 茯苓三両一云四両
小半夏加茯苓湯の作り方 半夏10g 生姜8g 茯苓3g~4g
右の三味を、水七升を以って煮て一升五合を取り、分ち温めて再服す。
右の三味を水280㏄と共に煎じ、60㏄まで煮詰め滓を去り、一日二回に分けて温め服す。
(32)例令ば、痩人臍下に悸有り涎沫を吐して癲眩するは之水也。五苓散之を主どる。
例えば仮に痩せた人がいて、臍の下で動悸を感じ、泡が混じった唾を吐き、倒れる様に目が眩む者は、水のせいである。
これには五苓散が中心となる。
五苓散の方 沢瀉一両一分 猪苓三分皮を去る 茯苓三分 白朮三分 桂二分皮を去る
五苓散の作り方 沢瀉3.05g 猪苓1.8g皮を去る 茯苓1.8g 白朮1.8g 桂枝1.2g皮を去る
右の五味を末と為し白飮にて方寸匕を服す。日に三服す。多く暖水を飮めば汗出でて兪ゆ。
右の五味を搗いて末にし、重湯と一回分1.5gの薬を混ぜて服す。一日三回温めて服す。
服用後、多量の生ぬるい湯を飲めば汗が出て治る。
(33)外臺茯苓飮心胸中に停痰宿水有りて自ら水を吐出して後、
外台秘要という古医書に書かれている茯苓飲は、心胸の中に停滞した水が有る為、ひとりでに水を吐き出した後、
心胸の間虚し氣滿して食する能わ不るを治し痰氣を消し食せしむ。
心胸の間が虚し、気だけが詰まった様な感じがして、食事をする事が出来ないのを治し、
その心胸にある痰の気を消し、よく食事が出来るようになる。
(外臺茯苓飮の方) 茯苓三両 人参三両 白朮三両 枳実二両 橘皮二両半 生姜四両
外台の茯苓飲の作り方 茯苓3g 人参3g 白朮3g 枳実2g 橘皮2.5g 生姜4g
右の六味を水六升を以て煮て一升八合を取り、分ち温めて三服す。人の八九里を行くが如くして之を進む。
右の六味を水240㏄と共に煎じ、72㏄まで煮詰めて滓を去り、一日三回に分けて温め服す。
一時間半を置いてまた与えよ。
(34)ガイ(亥+欠)家其の人脈弦なるは水有りと為す。十棗湯之を主どる。
咳を患っている者で脈浮の者は、病は水から来ている。これには十棗湯が中心となる。
(35)夫れ支飲家にガイ(亥+欠)煩し胸中痛む者有り卒に死せず一百日に至り、或は一歳に至り。十棗湯に宜し。
現在、支飲を患っている者で、咳が連続して出て胸中が痛む者がいる。
急には死なないが三ヶ月から場合によっては一年位しか命が持たないだろう。そういう者には十棗湯がよい。
(36)久ガイ(亥+欠)數歳其の脈弱き者は治すべし。実大數の者は死す。
幾年も咳が治らないもので、その人の脈が弱いのを治してやりなさい。
(治し方は、飲の持病のある人の治し方に従う。)
脈が実大数の者は死ぬ。
其の脈虚なる者は必ず冒を苦しむ。其の人本支飲在りて胸中に在るが故也。
その脈が虚なる者は、必ず頭が塞がった様な苦しみが有る。
その人は以前から支飲の病があり、その場所が胸中にあるからである。
(37)ガイ(亥+欠)逆倚息し臥する得不るは、小青竜湯之を主どる。
咳は酷く込み上げてきて物に寄りかかり息をし、横になることも出来ない者は、小青竜湯が中心となる。
(38)青竜湯を下し己多唾口燥し寸脈沈尺脈微、手足厥逆氣少腹從り上って胸咽を衝き手足痺、
小青竜湯を与え服用した後、唾が多く出て口中がはしゃぎ寸脈は沈み尺脈が微になり、
手足が冷え上がり臍の辺りから何か物が上がってきて胸から喉を突く様な気がし手足が痺れ、
其の面翕然として醉状の如く復た下陰股に流るるに因って小便難く、
あたかもお酒で酔った様に顔がカーッと熱くなり、上に突き上がっていた気が今度は下がって
逆に陰股の方へ流れる感じがして小便が思うように出ず、
時に復た冒する者には、茯苓桂枝五味甘草湯を与えて其の気衝を治せ。
時には気が再び上がり、その為に頭冒する者には苓桂味甘湯を与え、
桂苓五味甘草湯の方 茯苓四両 桂枝四両皮を去る 甘草三両炙る 五味子半斤
桂苓五味甘草湯の作り方 茯苓4g 桂枝4g皮を去る 甘草3g炙る 五味子3g
右の四味を水八升を以って煮て三升を取り滓を去り分ち温めて三服す。
右の四味を水320㏄と共に煎じて120㏄まで煮詰め滓を去り、一日三回に分けて温め服す。
(39)衝氣即ち低れ而も反って更にガイ(亥+欠)し胸滿する者には、
苓桂味甘湯を飲んだところ、上に突き上がっていた気が直ぐに治まったが、
今度はその代わりに咳が出始め胸満する者には、
桂苓五味甘草湯を用い桂を去り乾姜細辛を加えて以って其のガイ(亥+欠)滿を治せ。
桂苓五味甘草湯の中の桂枝を去って乾姜と細辛を加え、その咳と胸満を治してやりなさい。
苓甘五味薑辛湯の方 茯苓四両 甘草 乾姜 細辛各三両 五味半升
苓甘五味薑辛湯(苓甘姜味辛湯)の作り方 茯苓2g 甘草1.5g 乾姜1.5g 細辛1.5g 五味子1.5g
右の五味を水八升を以って煮て三升を取り滓を去り半升を温服す。日に三服す。
右の五味を水160㏄と共に煎じ、60㏄まで煮詰め、滓を去り、一回に20㏄を一日三回に分けて温め服す。
(40)ガイ(亥+欠)滿即ち止んで更に復た渇し衝氣復た発する者は、細辛乾姜熱薬爲るを以って也。
苓甘姜味辛湯を服したら直ぐに咳満が止み、また喉が渇いて気が上に突き上げるのは、
細辛と乾薑は熱薬であるからである。
之を服すれば当に遂に渇すべし。而るに渇反って止む者は支飲と爲る也。
これをこのまま呑めば、呑んでいる内に恐らく喉が渇きだすはずだ。
この処方により逆に乾かなくなった者は、支飲の病が有る。
支飲の者は法当に冒すべし。冒する者は必ず嘔す。
支飲の病の者は、頭冒がなくてはならない。頭冒が有る者は、必ず嘔するものである。
嘔する者には復た半夏を内れ以て其の水を去る。
嘔を発する者には、その処方の中に半夏を入れ、その支飲の水を去ってやりなさい。
桂苓五味甘草去桂加細辛半夏湯の方 茯苓四両 甘草 細辛 乾姜各三両 五味 半夏各半斤
桂苓五味甘草去桂加細辛半夏湯(苓甘姜味辛夏湯)の作り方
茯苓2g 甘草1.5g 細辛1.5g 乾姜1.5g 五味子1.5g 半夏2.5g
右の六味を水八升を以って煮て三升を取り、滓を去り、半升を温服す。日に三服。
右の六味を水160㏄と共に煎じて60㏄になるまで煮詰めて滓を去り、一回に20㏄ずつ一日三回温め服す。
(41)水去り嘔止み其の人形腫れたる者は、加杏仁之を主どる。
支飲の水が去り、嘔も止み、見ただけでもわかる位の浮腫みが出た者は、前方に杏仁を加えてやりなさい。
(苓甘姜味辛夏仁湯)
其の證麻黄を内るるに應ずるども其の人遂に痺するを以って故に之を内れ不、
その人の証が麻黄を与えた方が良いと思っても、その人はすでに痺が有る為、麻黄が入れられない。
若し逆して之を内るれば必ず厥す。
もしも麻黄を入れると、必ず手足が冷える。
然る所以の者は、其の人血虚するに麻黄其の陽を發するを以っての故也。
なぜ手足が冷えるかというと、麻黄というものは陽を発する働きを持っているからである。
だから血が虚している人に麻黄を用いて陽を発すると、必ず冷えるのだ。
苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯の方 茯苓四両 甘草三両 五味半斤 乾薑三両 細辛三両 半夏半斤 杏仁半升皮と尖を去る
苓甘五味加姜辛半夏杏仁湯(苓甘姜味辛夏仁湯)の湯の作り方
茯苓2g 甘草1.5g 五味子1.5g 乾姜1.5g 細辛1.5g 半夏2.5g 杏仁2.5g皮を去り先端の芽を去る
右の七味を水一升を以って煮て三升を取り滓を去り温服す。半升日に三服。
右の七味を水200㏄と共に煎じ、60㏄になるまで煮詰めて滓を去り、一回20㏄ずつ一日三回温め服す。
(42)若し面熱っすること酔えるが如きは、此れ胃熱上衝して其の面を熏ずると為す。
もしも顔が熱して、あたかも酒で酔っている様な者は、これは胃の熱が上に突き上げてきて、
その顔を燃やしているのだ。
大黄を加えて以って之を利せ。
その様な者には、前方に大黄を加えて、その熱した顔を治してやりなさい。
苓甘五味加姜辛半杏大黄湯の方 茯苓四両 甘草三両 五味半升 乾薑三両 細辛三両 半夏半升 杏仁半升 大黄三両
苓甘五味加姜辛半杏大黄湯(苓甘姜味辛夏仁黄湯)の作り方
茯苓2g 甘草1.5g 五味子1.5g 乾姜1.5g 細辛1.5g 半夏2.5g 杏仁2.5g 大黄1.5g
右の八味を水一升を以って煮て三升を取り滓を去り温めて半升を服す。日に三服す。
右の八味を水200㏄と共に煎じ、60㏄まで煮詰めて滓を去り、一回20㏄ずつ一日三回温めて服す。
(43)先ず渇して後に嘔するは、水心下に停まると為す。飲家に属す。
病が始まる前に盛んに喉が乾いて水を飲みたがり、水を飲んだ後で嘔する者は、
水が心下に留まって去らないからである。こういう者は飲の病に属するのだ。
小半夏加茯苓湯之を主どる。
小半夏加茯苓湯が中心となる。
《痰飮ガイ(亥+欠)嗽病脉證并治・第十二》